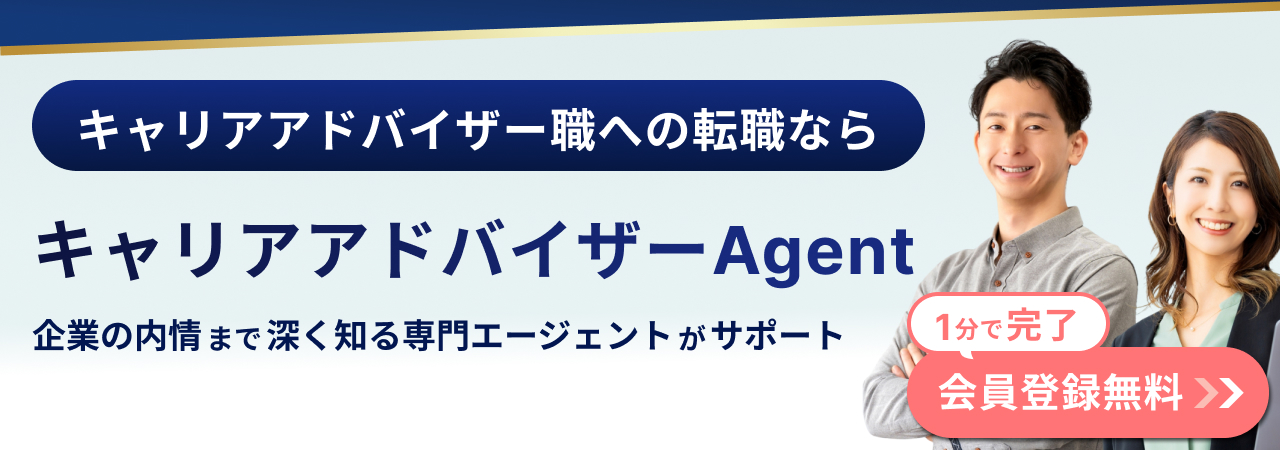2025年1月10日公開
最終更新日:2025年12月5日
人材業界は市場が望む人材と企業をつなぐビジネスモデル! 仕事内容の解説に加え市場規模や動向についても紹介
人材業界は企業の求人需要と人材の求職需要を満たすことを仕事とするビジネスモデルです。人材業界には有料職業紹介事業や労働者派遣事業、人材コンサルティング事業、求人広告事業といった業種があります。仕事内容は業種独自のものもあれば重なるものもあるなど様々です。
この記事では仕事内容だけでなく、市場の規模や動向も含め、人材業界のビジネスモデルについて解説します。
【関連記事】当社が運営する「キャリアアドバイザーAgent求人ナビの転職支援サービス」の特徴や登録のメリットについてご紹介。
人材業界のビジネスモデル~有料職業紹介事業
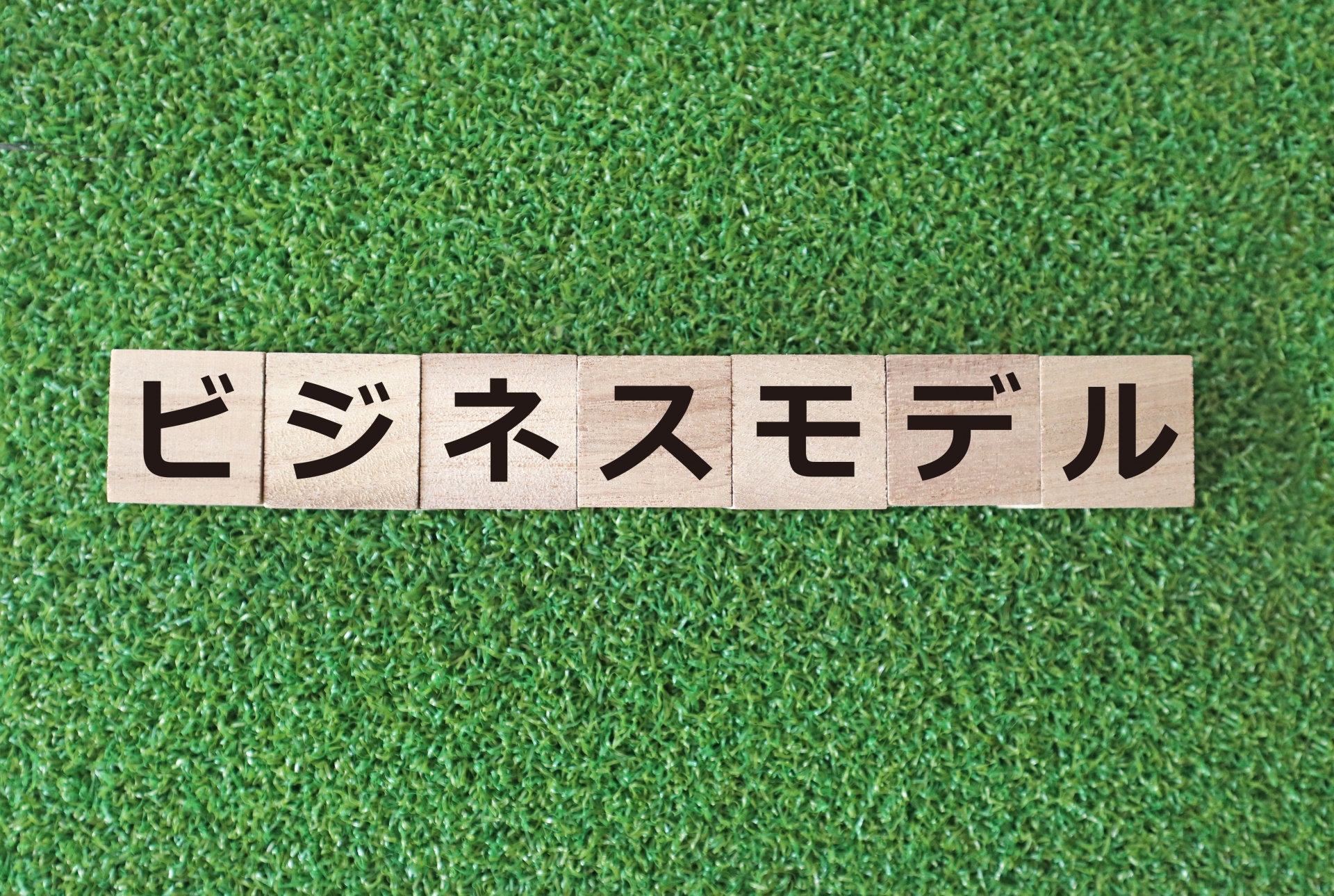
人材業界のビジネスモデルは業種によって異なります。人材業界の主な業種は下記一覧のとおり4つです。
ここでは有料職業紹介事業のビジネスモデルについて解説します。
求人企業と求職者をマッチング
人材業界の主要4業種のひとつである有料職業紹介事業は、求人企業と求職者のマッチングを主な業務とする業種です。有料職業紹介事業を行っている企業は、一般に人材紹介会社や転職エージェントなどと呼ばれています。呼び方に決まった定義があるわけではないものの、求人企業に向き合う仕事では人材紹介会社と呼ばれ、求職者の転職支援を行う仕事では転職エージェントと呼ばれやすいといえるでしょう。
有料職業紹介事業は職業安定法で規定されている事業であり、厚生労働大臣の許可が必要です。
総合型と特化型
有料職業紹介事業のビジネスモデルには取り扱う範囲による分類として、幅広く業種・職種をカバーする総合型のサービスと、特定の業種・職種に限定する特化型のサービスがあります。一般に大手企業には総合型が多く、中小企業は特化型として活躍するケースが目立つようです。大手には資金力とマンパワーがあることから業務範囲を広げやすく、そこまでの体力がない中小は専門性を高めることで勝負しているともいえます。
マッチング型とヘッドハンティング型とアウトプレースメント型
サービス内容による分類として、マッチング型とヘッドハンティング型、アウトプレースメント型があります。
・マッチング型
自社に登録している求職者を求人企業に紹介するサービスがマッチング型です。有料職業紹介事業では一般的なタイプです。求人企業も求職者も自社のサービスを利用している顧客であることから、円滑なマッチングがしやすいといえるでしょう。マッチング型は登録型や一般紹介型などとも呼ばれています。
・ヘッドハンティング型
ヘッドハンティング型はサーチ型やスカウト型などとも呼ばれており、自社の登録者だけでなく他社の登録者やSNSその他のメディア、手段を通じて紹介できる求職者を探すタイプのサービスです。ハイクラス層の求人や高いスキルを持った人材需要に適しています。
・アウトプレースメント型
一般にイメージする求人・求職とは異なる需要に応えるサービスの形がアウトプレースメント型です。再就職支援型などとも呼ばれており、リストラ要員となった人たちの転職を支援する点が、アウトプレースメント型の大きな特徴となっています。雇用継続が困難になった企業の依頼を受けて、希望者の転職成功をまとめてサポートするビジネスモデルです。
キャリアアドバイザーとリクルーティングアドバイザー
有料職業紹介事業の特徴的な職種として主に求職者対応を行うキャリアアドバイザーと、求人企業対応を行うリクルーティングアドバイザーがあります。
・キャリアアドバイザー
キャリアアドバイザーは登録されている求職者の転職活動を、スタートから入社(または転職をやめる)まで全般的に支援する仕事です。二人三脚で求職者の相談に乗り、アドバイスを行い、転職成功に向けた手助けを行います。
・リクルーティングアドバイザー
リクルーティングアドバイザーは求人企業を担当する職種で、有料職業紹介事業において営業職と呼ぶ場合、一般にリクルーティングアドバイザーを指すと考えてよいでしょう。求人企業のニーズにマッチする求職者の紹介をはじめ、求人企業の採用に関する課題解決を支援します。
さて、キャリアアドバイザーが求職者対応を担当し、リクルーティングアドバイザーが求人企業を担当するという役割分担になっている有料職業紹介事業ですが、必ずしも分業する仕組みになっているとは限らない点に注意が必要です。会社によってはキャリアアドバイザーがリクルーティングアドバイザーの仕事を兼ねているケースがあります。分業制におけるキャリアアドバイザーを片手型と呼ぶのに対し、兼業のキャリアアドバイザーを両手型と呼ぶことで区別が可能です。
▼キャリアアドバイザーの基本知識や具体的な仕事内容についてはこちらの記事でも総合的に解説しています。
キャリアアドバイザー(人材紹介)ってどんな仕事内容?業務の詳細を徹底解説!
人材紹介利用の流れ
有料職業紹介事業者を求人企業が人材紹介会社として利用する場合の流れは以下のとおりです。
1.相談・見積もり・契約締結
2.条件設定や作成についての支援を受けつつ求人票を作成
3.人材紹介を受けて検討
4.書類選考
5.求職者とのスケジュール調整を受けて面接実施
6.内定後に条件のすり合わせを行い採用決定
7.紹介手数料を支払う
8.入社手続き
9.フォローを受ける
面接まで求職者と直接会うことがない点は有料職業紹介事業者を利用しない場合と同じですが、全期間を通じてほとんどのやり取りを任せられる点が大きなメリットです。
求人企業のリスクとして、紹介を受けて採用した人材がすぐに辞めてしまった場合には、紹介手数料が無駄になってしまう点が懸念されます。そのため、一定の条件下で返金対応とする契約が一般的になっているようです。また、まるごとお任せにしてしまうと、自社にノウハウが蓄積されません。
転職エージェント利用の流れ
転職活動にあたり有料職業紹介事業者を転職エージェントとして利用する場合の流れを以下に示します。
1.利用したい転職エージェントを選んで登録
2.1社では希望する転職につながらない可能性があるため他社にも登録
3.希望条件やプロフィールなどの聞き取り、カウンセリングを受ける
4.求人企業の募集のなかからマッチ度が高い案件の紹介を受け、気になる求人の紹介を希望するなどし、応募先を選定する
5.サポートを受けつつ職務経歴書などの書類を作成し提出
6.面接スケジュールの調整依頼、模擬面接などの準備を経て面接に臨む
7.内定後の条件すり合わせを行い入社を決定
8.入社手続き
9.フォローを受ける
有料職業紹介事業者を利用しないで個人で活動する場合、求人企業の詳細な情報を得たり、やり取りをしたりといったことはまずできません。各段階でそれが可能になる点が大きなメリットです。
有料職業紹介事業の収益構造
有料職業紹介事業の実務では、基本的に求職者ではなく求人企業からの紹介手数料を主な収益源としています。紹介した求職者が採用されることによって紹介手数料が発生する成功報酬制が一般的です。紹介手数料の相場は想定年収の30%程度となっています。
30%の場合、年収600万円の人材であれば、紹介手数料は180万円です。かなりの高額に感じるかもしれませんが、求職者には基本的に無料でサービスを提供していることや、採用に至らない限り売上にならない点を考えれば納得の報酬額だといえるのではないでしょうか。
ちなみに、紹介手数料の決定には職業安定法が関係しており、有料職業紹介事業者は同法の規定にしたがわなければなりません。上限制手数料と届出制手数料があり、多くの有料職業紹介事業者が、自社で手数料の額を決定できる届出制手数料を採用しています。ただし、手数料が著しく不当と判断される場合は、変更命令が出される点に注意が必要です。
有料職業紹介事業のやりがい
有料職業紹介事業のスタッフとしてのやりがいは大きいといわれています。
・人の役に立つ仕事
有料職業紹介事業の仕事は求職者にとって一生を左右しかねない転職をサポートする仕事であり、求人企業の業績にも影響する仕事です。それぞれのニーズを満たすことは人の役に立つことであり、そんな仕事にやりがいを感じる人は少なくありません。
・目標達成と自己の成長
有料職業紹介事業の仕事が人の役に立つとはいっても、営利企業である自社にとっても利益になる必要があります。キャリアアドバイザーもリクルーティングアドバイザーも目標達成が求められる仕事です。高い目標をクリアしたときに得られる達成感がやりがいにつながります。また、困難な仕事を通じて自己の成長を実感したときにもやりがいを感じるものです。
・頑張り次第で高額報酬
キャリアアドバイザーやリクルーティングアドバイザーの給料体系には、実績に応じた歩合が設定されているケースが少なくないようです。つまり、頑張り次第で高額報酬を得ることができ、大きなやりがいにつながっています。
▼人材紹介のビジネスモデルについてはこちらの記事でも詳しく解説しています。
人材紹介事業のビジネスモデルとは?事業として気になる利益率なども合わせて徹底解説
人材業界のビジネスモデル~労働者派遣事業

有料職業紹介事業と並ぶ人材供給の業種である労働者派遣事業のビジネスモデルについて解説します。
欲しいときに欲しい人材を派遣
労働者派遣事業は企業による人材採用をサポートする有料職業紹介事業とは異なり、企業が欲しいときに欲しい人材を派遣して派遣料を得るビジネスモデルです。労働者派遣事業は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(略称は労働者派遣法)」に規定されており、業務を行うには厚生労働大臣の許可が必要になります。労働者派遣事業を行う労働者派遣事業者は一般に派遣会社と、派遣労働者は一般に派遣社員と呼ばれています。
労働者派遣事業は、長期の人材需要を前提としていない点に大きな特徴があるといえるでしょう。派遣期間は基本的に3年が上限であり、数ヶ月の短期派遣も活発に利用されています。
企業にとっては繁忙期や急な人材需要が発生したときに、便利に利用できる点が大きなメリットです。一時的に人員補充したいケースなど、自社採用するまでもないとき、特定のスキルを持っている人材を早急に用意したいときなど、利用目的は様々あります。
労働者派遣事業者の収益源は主として派遣先企業から得られる派遣料です。
常用型派遣と登録型派遣
派遣労働の形態には常用型派遣と登録型派遣の2種類があります。どちらの形態でも派遣労働者は労働者派遣事業者に雇用された従業員の立場です。
・常用型派遣
一般的な会社の従業員と同様に常時雇用関係にある派遣労働者を派遣する形態で、派遣先がなくても派遣労働者の収入源が確保されます。
・登録型派遣
派遣先企業との契約期間中、つまり派遣期間中のみ労働者派遣事業者に雇用される派遣労働者を派遣する形態です。契約が終われば派遣労働者は無職の状態になります。派遣期間に制限があるのは、登録型派遣の場合です。
紹介予定派遣
人材の採用を予定しているが、採用の手間を省きたい、よい人材かどうかを見極める期間が欲しいといった企業ニーズに応えるのが紹介予定派遣です。最長6ヶ月という短期間の派遣を経由して、企業と労働者に合意があれば派遣先での雇用となる前提で行われます。派遣労働者にとっては、「いきなり正社員になるのは不安だがお試し期間があるなら」「よい会社があればずっと働きたい」といったニーズにマッチするなど、メリットの多い派遣の形態です。
派遣社員教育が重要
労働者派遣事業では、派遣労働者の雇用主として派遣先のニーズに応える人材を派遣する必要があるため、円滑な就業を支援する各種教育が重要です。マナー教育や資格取得の支援など、他社との差別化も含めて力を入れています。
労働者派遣の利用の流れ
企業が利用する際の流れは以下のようになります。
1.派遣希望のヒアリング
2.派遣労働者選定の連絡、紹介を受ける
3.ケースにより職場見学を行う
4.条件のすり合わせ
5.最終確認を経て契約
6.就業受け入れ
注意すべきは、派遣される労働者の選考ができない点です。選考はあくまでも労働者派遣事業者が行います。
次に、派遣で働きたい労働者が利用する流れを以下に示します。
1.登録、1社では希望に合わない可能性があるため複数社に登録
2.求人紹介、求人選択
3.応募してニーズに合ってれば派遣候補となる
4.必要に応じて職場見学を行う
5.就業するか否かを決断して意思表示、就業する場合は手続きへ
6.就業
登録型派遣の場合、契約終了による無職化で収入がなくなる点が懸念されるため、労働者自身も次の派遣先を早めに探すなどの対応が重要です。
▼人材紹介と人材派遣の違いについてはこちらの記事で詳しく解説しています。
人材紹介会社と人材派遣会社の違いとは? それぞれの特徴やメリット・注意点について解説
人材業界のビジネスモデル~人材コンサルティング事業

続いて人材コンサルティング事業のビジネスモデルを解説します。
人事部門の業務をトータル支援
人材コンサルティング事業の特徴は人材の採用を中心にフォーカスするのではなく、人材教育や評価制度など、人材に関する業務を制度面も含めトータルで戦略的にサポートする点です。人事部門の業務に関する課題解決に寄与し、業務の効率化を促進します。
採用に関する部分では有料職業紹介事業者が行うコンサル業務と共通する部分が多いものの、そもそもの目的が異なる業種です。
コンサル料が収益源
人材コンサルティング事業では、コンサルティング料が主な収益源です。他の業種では採用という結果や労働者の派遣、広告の掲載など目に見える形のあるサービスが収益源となっているのに対し、必ずしも形があるわけではないコンサルティングそのものが商品になっています。
ただし、近年では人材コンサル事業を行う事業者のなかで、人事に関するアウトソーシング業務を兼業している事業者が増加しているようです。
人材業界のビジネスモデル~求人広告事業

人材業界における主要4業種のビジネスモデル解説の最後は、求人広告事業です。
メディアへの求人掲載
求人広告事業は求人雑誌や求人サイトなどのメディアに求人広告を掲載する、また掲載する求人広告を集める業種です。広告掲載に関連して広告作成のサポートも行います。求人広告事業については、職業安定法の募集情報等提供事業、特定募集情報等提供事業の規定に注意する必要があります。たとえば、2024年1月時点では求人サイト経由での就業にボーナスを付与する求人広告事業者などがありますが、2025年4月からの規制により原則禁止です。
求人広告を扱う業者は2種類ある
求人広告を扱う業者は2種類あります。広告が掲載される媒体を運営している企業と広告代理店です。広告媒体の運営会社は通常、出稿主である企業には自社メディアしか提案できないのに対し、広告代理店は複数社のメディアを提案できる違いがあります。
報酬の発生は2種類に分かれる
求人広告のビジネスモデルでは、報酬の発生が2種類に分かれています。
・求人広告の掲載について掲載料が発生する
・掲載は無料で求職者からの応募があったときに報酬が発生する
前者は従来からある一般的なビジネスモデルであり、後者は反響次第となっている点で収益の安定性がないと考える向きもあります。しかし、無駄な広告を打ちたくないニーズの高まりもあってか、成功報酬制ともいえる後者が増えている状況です。
人材業界のビジネスモデルに向いている人

人材業界のビジネスモデルに向いているのはどのような人かについて解説します。
コミュニケーション能力が高い・コミュニケーションが好きな人
人材業界は人材、つまり人によって成り立つ業界です。そのため、人との密接なコミュニケーションなくしては仕事になりません。コミュニケーション能力が高い・コミュニケーションが好きな人は人材業界に向いています。
人の人生に寄り添う仕事がしたい・役に立ちたい人
転職成功や人材採用、人事業務の効率化といったニーズに応え、人や企業に寄り添い、役に立つのが人材業界の仕事です。仕事を通じて役に立ちたい思いのある人は人材業界に向いています。
様々な仕事と触れ合いながら働きたい人
人材業界の仕事はどの業界、職種であってもやることが多いといえます。たとえばキャリアアドバイザーは、求職者の募集、電話や面談でのヒアリング、スケジュール調整、書類作成、模擬面接、リクルーティングアドバイザーや他部門との連携、数字の管理などをマルチタスクでこなす職種です。様々な仕事と触れ合いながら働きたい人は人材業界に向いています。
新しい情報の収集に意欲的な人
常に新しい情報、幅広い情報を活用して動いているのが人材業界です。そのため、新しい情報の収集に意欲的な人は人材業界に向いています。
コンサルティングセールスで結果を出した人
人材業界の仕事は職種にもよりますが、顧客の課題解決に向けたヒアリング力、発想力や提案力が必要です。つまりはコンサルティングセールスの要素、方法論が強く、コンサルティングセールスで結果を出したい人は向いているといえます。
向上心の強い人
日々あらたな課題の解決に向けて努力し、さらなる業績のアップを目指して動いているのが人材業界です。そのため、向上心の強い人は人材業界に向いています。
人材業界の市場規模と動向

ここでは人材業界の市場規模と動向について解説します。
売上高で10兆円に迫る市場規模
矢野経済研究所の調査データによれば、人材派遣業、人材紹介業(ホワイトカラー)、再就職支援業の2023年度の売上高が9兆7,156億円で、2024年度見込みでは10兆円を超えるとされています。10兆円規模の業界といえば、日本に数ある業界のなかでも上位に位置する存在です。
出典:株式会社矢野経済研究所「人材ビジネス市場に関する調査を実施(2024年)」
https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3661
2019年からのグラフを見ると、人材業界は年々右肩上がりで大きく成長を続けていることがわかります。7兆2,831億円だった2019年度と比べて、2024年度は5年間で1.4倍以上に拡大する見込みです。
労働力人口の減少
労働力人口の減少が人材業界にプラスとなる可能性もあります。直近のデータでは上昇している年もあり、必ずしも減少が続いているわけではないものの、今後進む少子高齢化、人口減少が労働力人口の減少につながることは必然といえるでしょう。人材確保が急務となる企業による人材業界へのニーズの高まりが予測されます。人材業界自体の人材需要も増えそうです。
人材業界の魅力と将来性と注意点

人材業界の魅力と将来性、注意点について解説します。
人材業界の魅力
人材業界にはキャリアアドバイザーやリクルーティングアドバイザー、その他の営業職やマーケターなど、積極性や創造力が活かせる職種があります。企業と求職者双方の課題解決に役立てる、とくに求職者にとって人生を左右する場面でかかわれることや、激動の社会を肌で感じる業界であることから、刺激的な毎日を送れることなど魅力も大きい業界です。
人材業界の将来性
売上高の増加傾向からも将来性が有望な人材業界です。また、雇用の流動化の促進、人材不足を反映した外国人労働者の増加や女性の社会進出、高齢者雇用の促進、副業推奨などの社会の変化まで含めると、人材関連の支援ノウハウや経験を積んでいる求人業界が頼りにされる条件も揃っています。人材業界の仕事はさらに増えるでしょう。
人材業界の注意点
右肩上がりの人材業界ではありますが、一方で景気の変動に影響を受けやすい点も忘れてはならないでしょう。リーマンショックや消費増税による市場の冷え込みといったリスク要因には注意する必要があります。
人材業界のビジネスモデルを理解して自分のキャリアを考えよう
人材業界には有料職業紹介事業や労働者派遣事業だけでなく、人材コンサルティング業や求人広告業など、特徴の異なる業種があります。それぞれに興味深いビジネスモデルが構築されており、転職先として選ぶ際にはビジネスモデルを理解したうえで、自分のキャリアにとって何が有利かを考えることがポイントです。
キャリアアドバイザーAgentの転職支援サービスはキャリアアドバイザー職を初めとして、人材業界での転職を考えている方向けに特化し、応募書類作成のサポートや企業ごとの面接対策など徹底した伴走型の転職支援を提供。「書類も面接もこれまでより通過率がダントツに上がった」「年収交渉をしてもらい希望年収が叶えられた」などGoogle口コミでも高い評価をいただいているサービスです。
人材業界への転職を検討している方はぜひ以下ボタンから面談予約してください。
この記事の監修者
長沢 ひなた
外資系アパレルで販売・チーム運営を経験後、美容クリニックのカウンセラーに転身。60名中3名のみのトップカウンセラーとして表彰され、マネージャーとして大規模なチームマネジメントも経験する。
「人生単位での変化」を支援したいとの想いからキャリアアドバイザー職へ転身し、入社半年での異例の昇格、1年でリーダーに就任。現在は、キャリアアドバイザー職への転職を専門に、業界構造を熟知した的確な支援を行っている。(▶︎詳しく見る)
基礎知識のおすすめ記事
-
2024/11/20
キャリアアドバイザー(人材紹介営業)で成果を出すコツとは?売上を伸ばす方法を8つのステップで徹底解説
-
2026/01/23
人材業界に向いている人の特徴とは? 仕事内容やスキルを鍛える方法を解説
-

2024/10/16
キャリアアドバイザー(人材紹介営業)職でホワイト企業に転職する方法
-

2024/10/16
キャリアアドバイザー(人材紹介)は未経験からでも転職できる?営業未経験でも応募可能な求人例あり