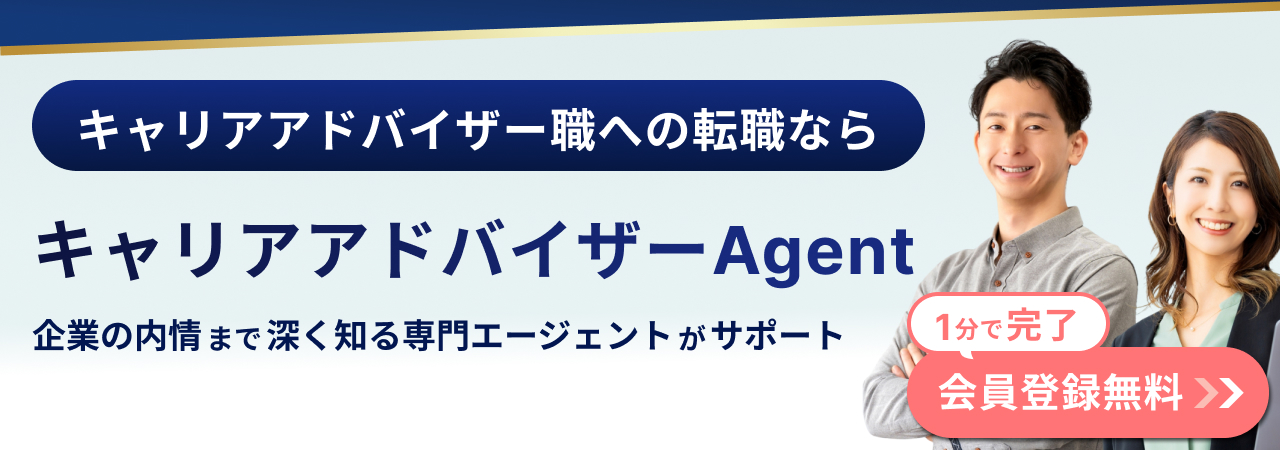2025年7月14日公開
最終更新日:2025年12月10日
今の人材紹介業界はなぜオワコンと言われるのか?そうでない視点も解説
「人材紹介業界はオワコンだ」「将来性がない」
そんな声をSNSや口コミで見かけたことはないでしょうか。実際、離職率の高さや競争の激化など、厳しい現実もあります。
しかし一方で、社会の変化に伴って新たなニーズが生まれ、成長を続けている領域も存在しているのです。
本記事では、人材紹介業界がオワコンと言われる理由を整理しながら、そう断じるには早いポジティブな側面にも目を向けていきます。
「自分に向いている業界なのか」「今後も活躍できるのか」を判断するための材料を探している方は、ぜひ読み進めてください。
【関連記事】当社が運営する「キャリアアドバイザーAgent求人ナビの転職支援サービス」の特徴や登録のメリットについてご紹介。
人材業界は本当に「オワコン」?そういわれる理由を徹底解説
そもそも、なぜ人材業界はオワコンと言われるのでしょうか。その背景にある3つの理由を見ていきましょう。
競争激化と差別化の難しさ
人材業界がオワコンと言われる背景には、業界全体のレッドオーシャン化があります。
厚生労働省によると、人材紹介会社の数は平成元年以降増加の一途をたどり、令和5年度には3万1,000社を超えました。さらに、人材派遣やSaaS型サービスなど多様な形態の参入が進み、企業・求職者双方にとって選択肢が過剰となり、各社の強みが見えにくくなっています。
こうした状況下では、価格競争に走る企業も少なくありません。
手数料の引き下げや無料サービスの提供が利益率を圧迫し、差別化の難しさを一層深めるという悪循環に陥っています。専門性や支援体制といった見えにくい価値も、十分に伝わりにくい状況です。
その結果、人材紹介会社の多くが「どこも同じ」に見え、集客コストや営業負荷が増大。競争の激化と差別化の困難さが、業界の限界感というネガティブな印象を生み出しているのです。
離職率の高さと精神的負荷
人材紹介業界の離職率の高さは、ネガティブな業界イメージの一因です。
離職の主な原因は、求職者と企業の間で板挟みとなる精神的プレッシャーでしょう。人生を左右する転職支援と、企業からの高い成果要求の両立は大きな負荷となります。
加えて、成果主義の評価制度も負担を増加させます。売上や面談数などの数値で評価され、「成果が出ないと価値がない」と感じる若手も多く、バーンアウトの一因となっています。
さらに、短期成果重視や詰め文化が残る職場では、精神的ケアが不足し、孤立感を抱えやすく、早期離職に繋がりやすい傾向があります。
これら複合的要因が、業界全体に対する否定的な印象を強めています。
成果主義と高いノルマ
人材紹介業界の実態として避けられないのが、成果至上主義とノルマの厳しさです。
仕組みは「売上 = 成約件数 × 手数料率」と明快である反面、数字を追うプレッシャーは相当なものです。
- 月数件の成約を求められるが、求職者や企業側の状況で成果が左右される
- 成果に至らなければ「支援が不十分」と評価され、不安や焦りが常に伴う
- ノルマ不達が続くことで心が折れてしまう
成果主義は努力が数字に直結する魅力を持つ一方、短期成果に偏る雰囲気が強まると、本来の使命である最適なマッチングが犠牲にされるリスクがあります。
こうした構造的なプレッシャーが、人材業界を消耗的で続けにくい仕事とする要因となり、オワコンといったネガティブな印象を生み出しています。
【断言】人材業界がオワコンではないと言える3つの理由

人材業界がオワコンと言われる理由を見てきましたが、実はそれは間違い。ここでは、人材業界がオワコンではないと言える3つの理由を解説します。
複雑な「人と企業の縁結び」はAIでは代替できない
生成AIの発展により、「AIに仕事を奪われるのでは」と不安を感じる方はいるのではないでしょうか。多くの業界がAIによる危機を抱えている中、人材紹介における本質的な仕事は、今なお人間にしかできません。
たとえば、求職者の営業を希望という言葉の背景にある動機や価値観を読み取り、相性の良い企業を提案するには、人間の共感力や洞察力が不可欠です。また、企業の求人票に載らない本音や空気感を理解する力もAIには難しい領域です。
人材紹介の価値は、情報をつなぐだけでなく、言語化されないニーズを可視化し、最適なマッチングへと導く翻訳者としての役割にあります。AIは補助的なツールにすぎず、この仕事の本質は、今も人に託されています。
今後AIがさらなる発展を遂げても、人材紹介会社は大きな危機にさらされないと言えるでしょう。
労働人口減少社会における人材流動化のキープレイヤー
日本は少子高齢化と人口減少が進み、生産年齢人口は1995年をピークに減少し続ける一方で、2050年には2021年から約30%減の5,275万人まで減少すると見込まれています。
これにより、労働力不足があらゆる企業の課題となり、人材紹介業界の重要性が増しているのです。
企業の持続的成長には、適材適所、つまり限られた人材を適切に配置しなければいけません。スタートアップの事業推進や大企業の即戦力採用など、あらゆる場面で人材流動性の向上が求められています。
人材紹介は、スキルや価値観のミスマッチを減らし、キャリアの再構築を支援する社会の橋渡し役としての機能を果たしているのです。
さらに、正社員化の支援、柔軟な働き方の提案、外国人材の活用など、働く人の多様性を支える役割も担っています。人材紹介は今や、社会インフラの一端を担う存在といえるでしょう。
キャリア形成における専門的な伴走支援の必要性
「自分に合う求人かわからない」「キャリアに自信が持てない」という不安を抱える人は多いです。そんな中で重要なのが人材紹介業界の伴走支援です。
かつては終身雇用が前提でしたが、今や転職やスキルチェンジによるキャリアの再設計が当たり前になっています。市場価値の見極め、将来の選択肢、中長期のビジョンなどを一人で考えるのは難しく、ここにキャリアアドバイザーの出番があります。
たとえば、未経験から人気のIT業界を目指す人には、業界研究から職務経歴書の書き方、面接対策、内定後の不安までを包括的に支援します。こうしたきめ細やかな支援は、求人票やAIでは実現できません。
人のキャリアには感情や不安がつきものです。
伴走支援とは、ただ仕事を紹介するだけでなく、相談相手として励まし、問い直しながら自信を引き出す人生支援の役割でもあります。人材紹介の本質は、まさにここにあるのです。
人材業界がオワコンではない理由をデータをもとに解説

ここでは、客観的なデータをもとに人材業界がオワコンではない理由を紹介します。
人材サービス市場は成長傾向にある
人材紹介業界はオワコンどころか、むしろ市場規模という観点では安定した成長を続けています。
矢野経済研究所の発表によれば、2024年度の人材サービス市場規模は10兆2,602億円に達する見込みです。これは、コロナ禍による一時的な停滞を乗り越え、企業の採用意欲が回復していることの証でもあります。
この成長を支えているのが、深刻な労働力不足という社会課題です。
少子高齢化の進行により、生産年齢人口は減少を続け、多くの企業が慢性的な人手不足に悩まされています。実際、帝国データバンクの2024年の調査によると、5割以上の企業が人手不足と回答しています。
特に中小企業や地域密着型の事業者にとっては、自前で必要な人材を確保することが難しく、外部の人材サービスへの依存度が高まっています。
また、事業の多角化やDX推進により、従来とは異なるスキルセットを持つ人材へのニーズも急速に増加しています。
たとえば、デジタルマーケティングを推進するには、SNS運用のスキルやMAツール導入経験を持つ人材が求められます。こうした多様なニーズに対しては、求人広告だけでは対応が難しく、個別最適なマッチングを実現できる人材紹介サービスの価値が見直されています。
さらに近年では、企業が採用を単なる空席の補充ではなく、事業成長のドライバーと捉える傾向が強まっており、質の高い人材を確保する手段として人材紹介の活用が定着しつつあります。
このように、人材サービス市場の拡大は単なる景気変動によるものではなく、構造的な社会課題に根ざした持続的成長である点に特徴があります。
HRテックがもたらす新たな可能性
人材業界は今、HRテックによる変革期を迎えています。HRテックとは、採用、育成、評価、定着などにテクノロジーを組み合わせた領域です。
市場は急拡大しており、Xenobrainによると2025年の国内市場規模は3,934億円であり、2030年までに42.7%増の5,614億円まで伸びると予測されています。これは、業界が単なる紹介業からデータ・テクノロジーで組織課題を解決する産業へ進化している証です。
具体的には、AIによるスキル可視化、応募プロセスの自動化チャットボット、動画面接中の感情分析ツールなどが普及し、適性や将来性まで評価可能になっています。
これは業界にとって大きなチャンスです。
従来の成果報酬モデルに加えて、SaaSやコンサルティングも組み込む複合モデルへの転換が進展。収益源の多様化と高付加価値サービスへの移行が期待されています。
つまり、HRテックは人材業界を時代遅れではなく、進化する産業へと導いている流れなのです。
人材業界で働く魅力

人材紹介業界には厳しさもありますが、「やりがい」「社会貢献性」「成果が報われやすい環境」といった他業界にない魅力があります。
まず、求職者の人生と企業の未来に直接関わる仕事であり、両者の最適なマッチングが深い充実感につながります。感謝の言葉を直接受け取れる場面も、この業界ならではです。
また、少子高齢化や地方の人材不足といった社会課題に対し、質の高いマッチングを通じて貢献できるのも大きな意義です。単なる紹介ではなく、長く活躍できる接続を支援する姿勢が求められます。
さらに、成果主義が根づくことで、努力が評価されやすい環境でもあります。年齢や経験に関係なく昇進のチャンスがあり、若手にも成長実感を得やすい点が特長です。
人と向き合う難しさはありますが、自分の関与が誰かの人生を動かすという実感は、この仕事ならではの魅力です。
関連記事:人材業界の魅力とは?職種・働き方・向いている人を解説
人材業界の主要職種

人材業界では、キャリアアドバイザー、法人営業(リクルーティングアドバイザー)、両面型コンサルタントが中核職種として活躍しています。
キャリアアドバイザーは、求職者と面談し、希望やスキルを踏まえた求人提案を行います。入社がゴールではなく、長期的なキャリア支援が求められ、傾聴力と洞察力が重要です。
法人営業は企業の採用課題をヒアリングし、要件に合う人材を提案する職種です。採用計画や選考プロセスに踏み込む支援もあり、課題解決力と信頼構築力が求められます。
両面型コンサルタントは、求職者と企業の双方を担当し、マッチングの質とスピードを両立する役割です。その分、業務量や調整も多く、高い自己管理力が求められます。
いずれの職種にも共通するのは、人と企業の未来に関わる責任感。営業力以上に、人間性と誠実な姿勢が問われる仕事です。
人材業界でオワコンにならないためには

人材業界に将来性がないと感じる背景には、変化に適応できていない個人や企業の存在があります。
しかし、裏を返せば、時代の流れを見極め、求められる力を磨き続けることで、これからの時代に活躍できるキャリアへと進化させることが可能です。ここでは、人材業界で長く活躍するために不可欠な視点とスキルを整理します。
まず前提として、人材紹介業の業務は今後もAI利用の影響を強く受ける分野の一つです。
たとえば、候補者情報のレコメンド、スカウトメールの自動送信、面談内容の要約など、定型業務の多くはすでに自動化を行っています。この流れは業界の効率化を促進する一方で、従来のやり方に固執するプレイヤーが淘汰されるリスクも高めています。
こうした時代において鍵となるのが、人間にしかできない仕事を極めることです。
具体的には、求職者や企業の本音を引き出す共感力、ニーズの背後にある課題を見抜く洞察力、利害の異なる双方をつなぐ交渉力、そして中長期的な関係性を築く力が挙げられます。
たとえば、求職者が語るやりたいことの奥にある価値観を見抜き、将来的なキャリア像まで含めて提案する力は、AIでは実現できません。
また、求職者に対しては、選択肢の提示にとどまらず、なぜその企業が合うのか、このタイミングで転職すべきかといった、意思決定の質に踏み込む支援方法が求められます。一方、企業に対しては、採用要件や面接基準の改善、定着率を高めるフォロー体制の提案など、コンサルティング的な支援が重視されつつあります。
このように、人材紹介という仕事は、情報提供型から課題解決型へと進化しているのです。
この変化に適応し、人にしかできない価値を提供し続けることができれば、AI時代においても活躍し続けることは十分に可能です。
つまり、オワコンかどうかは業界の問題ではなく、自分自身がどのように進化できるかにかかっているのです。
人材業界でビジネスをするポイント

人材業界でオワコンと言われないビジネスをするポイントをご紹介します。
専門性に特化する
レッドオーシャン化している人材業界で成功するには、全方位的なアプローチでは限界があります。選択肢が増えた今、特定分野での専門性こそが最大の競争優位となります。
たとえば、医療・介護分野では資格要件や現場環境に精通していることで、高精度のマッチングが可能です。IT領域でも、開発言語や業務経験に基づいた深い理解が信頼につながります。こうした知見が、わかってくれる担当者として選ばれる理由です。
専門性を持つことで、企業からのリピート依頼や求職者からの推薦につながりやすくなります。また、単なる紹介を越え、採用戦略やスキル育成まで踏み込んだコンサルティング提供が可能となり、価格競争からも脱却できるでしょう。
これはつまり、誰に、何を、どう届けるかを明確にしたポジショニング戦略です。専門分野に特化することで、その領域に欠かせないパートナーとしての地位を確立できます。
コンサルティング機能の強化
人材紹介ビジネスを持続的に成長させるには、人材紹介を超えたコンサルティング機能の強化が不可欠です。
企業の採用課題は人手不足だけではなく、選考フローや評価制度など、根本にある構造的な問題が背景にあります。そこに踏み込み、制度や人材戦略の改善まで提案できる存在こそ、信頼されるパートナーとなります。
たとえば、急成長中の企業には、短期の即戦力と同時に中長期のリーダー候補の確保も求められます。こうした経営視点を持ち、組織課題全体を見渡せる支援者になることで、紹介会社から事業の伴走者へと役割を広げられるわけです。
また、近年では育成支援や評価制度、チームビルディングなど、人事全体に関わるニーズも拡大しています。採用を入口に、継続的なコンサルティングへ展開することで、単発取引から長期的関係構築へとつなげられます。
競争が激しい市場だからこそ、企業変革を支える人材戦略のプロとしての価値提供が、信頼と継続取引のポイントとなるのです。
新たな収益源の創出に取り組む
人材紹介業の多くは成功報酬型手数料モデルに依存しており、マッチングが成立しない限り売上が発生しません。単価は高いものの、不安定さは否めず、事業の安定化には収益源の分散が不可欠です。
実際に先進企業では、紹介事業に加え、キャリア研修や人材育成などの継続課金型サービスを導入し、収益の多角化を図っています。若手や中途社員向けのオンボーディング研修、リーダー育成、キャリア支援はその代表例です。
また、求人要件の設計や選考プロセスの改善を含む採用コンサルティングにより、固定フィーや月額契約といった新たな収益形態を構築する動きも広がっています。スカウト代行や採用ブランディングなども有効でしょう。
さらに、SaaS型のマッチングプラットフォームや人材管理ツールの提供により、テクノロジーを収益源とするモデルも増加しています。
このように、周辺サービスを組み込んだ複合的なビジネス展開こそが、人材業界の収益安定と成長に欠かせない戦略といえます。
人材業界が「オワコンかどうか」は自分次第
「人材業界はオワコン」と言われる背景には、競争激化、厳しいノルマ、高い離職率といった現場課題があります。しかし一方で、社会的ニーズの高まりとテクノロジーの進化により、再成長の可能性も広がっています。
キャリアアドバイザーは、求人紹介だけでなく、求職者や企業の将来に関わる選択を支援する重要な存在です。責任の重さに戸惑う場面もありますが、その分、影響力とやりがいの大きな仕事です。
また、AIが進化しても、人間特有の共感力や関係構築力は依然として必要です。今後は、コンサルティングや育成支援、SaaSなどへサービスを広げることで、新たな価値創出も可能になります。
この業界が終わるかどうかは、外部環境ではなく、自らの意識と行動次第です。自分の強みをどう活かし、どんな未来を描くのか、その問いを持ち続けることが、活躍を続ける鍵となるでしょう。
キャリアアドバイザーAgentの転職支援サービスではキャリアアドバイザー職を募集している企業の裏側まで熟知したエージェントが転職を支援いたします。推薦文でも、なぜキャリアアドバイザーを目指しているのかなど言語化を行い書類通過率を高めます。
さらに、応募書類作成のサポートや企業ごとの面接対策など徹底した伴走型の転職支援を提供。「書類も面接もこれまでより通過率がダントツに上がった」「年収交渉をしてもらい希望年収が叶えられた」など口コミでも高い評価をいただいています。自身の志向にあったキャリアアドバイザーを目指している方はぜひ以下ボタンから面談予約してください。
この記事の監修者
長沢 ひなた
外資系アパレルで販売・チーム運営を経験後、美容クリニックのカウンセラーに転身。60名中3名のみのトップカウンセラーとして表彰され、マネージャーとして大規模なチームマネジメントも経験する。
「人生単位での変化」を支援したいとの想いからキャリアアドバイザー職へ転身し、入社半年での異例の昇格、1年でリーダーに就任。現在は、キャリアアドバイザー職への転職を専門に、業界構造を熟知した的確な支援を行っている。(▶︎詳しく見る)
基礎知識のおすすめ記事
-
2024/11/20
キャリアアドバイザー(人材紹介営業)で成果を出すコツとは?売上を伸ばす方法を8つのステップで徹底解説
-
2026/01/23
人材業界に向いている人の特徴とは? 仕事内容やスキルを鍛える方法を解説
-

2024/10/16
キャリアアドバイザー(人材紹介営業)職でホワイト企業に転職する方法
-

2024/10/16
キャリアアドバイザー(人材紹介)は未経験からでも転職できる?営業未経験でも応募可能な求人例あり