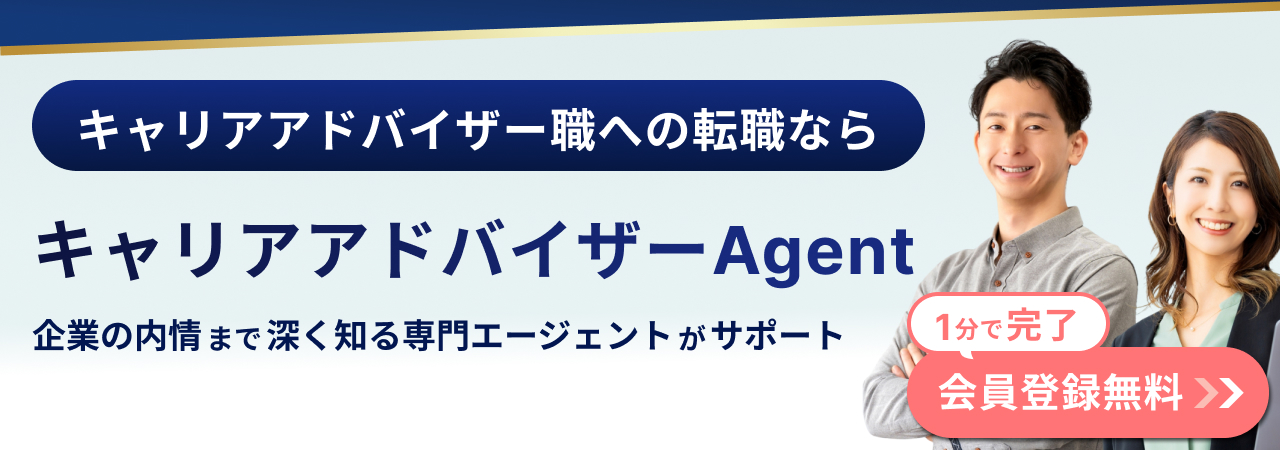2025年4月19日公開
最終更新日:2025年9月8日
人材紹介会社は多すぎる? 事業数の推移や倒産件数、市場規模から見る将来性とは
2025年現在、転職エージェントやスカウトサービスといった人材紹介会社が多数存在します。中には、「人材紹介会社は多すぎる」と感じる人もいるかもしれません。実際のところ、人材紹介会社は多すぎるのでしょうか。この記事では、人材紹介会社が多い理由や倒産状況、市場規模を解説します。
なお、人材紹介会社が多すぎて自分にあった会社をどう選んでよいか分からない、という不安を抱えている方はキャリアアドバイザーAgentの転職支援サービスへご相談ください。ご志向・ご経験を踏まえ適切な人材紹介会社をご提案させていただきます。
人材紹介会社は多すぎるのか? 統計から見る事業数の推移
新たな人材紹介サービスが次々と登場する状況を受けて、人材紹介会社が多すぎると感じる人もいるでしょう。しかし、人材紹介会社は本当に需要を超えて、あまりにも多く設立されているのでしょうか。ここでは、さまざまな統計情報を参照して、客観的なデータから人材紹介会社の実情を確認します。
人材紹介会社は「有料職業紹介事業」にあたる
前提として、人材紹介会社は「有料職業紹介事業」に分類されるビジネスです。有料職業紹介事業は、事業所の構造、資本金、紹介手数料の料率に関する厳格なルールが職業安定法によって決められています。新たに事業を立ち上げる際は、厚生労働大臣へ必ず届け出る必要があります。守るべきルールは多くありますが、港湾運送業務と建設業務以外の職種であれば自由に人材紹介が可能です。人材紹介会社は、以下のような業態があります。
なお、無償で行われる「無料職業紹介事業」は、ハローワークが該当します。
有料職業紹介事業は1985年以来増加している
有料職業紹介事業は、1985年の職業安定法の改正によって登場した業態です。その後、1999年に再度行われた職業安定法の改正により、港湾運送業務と建設業務を除く多様な職種の職業紹介が解禁されました。加えて、同法改正によって「届出制手数料」の仕組みも導入されています。届出制手数料とは、事前に厚生労働大臣に届け出た手数料の範囲内で紹介手数料を決定できる仕組みです。実務上は採用決定社の理論年収×最大50%の料率を設定できますが、一般的な料率は30〜35%が目安です。
こうした1999年の職業安定法の改正によって、有料職業紹介事業の「取り扱える職種」と「紹介手数料による収益」の双方が大きく増加しています。結果的に、1999年以降に有料職業紹介事業は急増しました。厚生労働省の資料によると、1999年度には3,727だった事業所数が、2023年度には30,113もの事業所が存在しています(※1)。わずかに減少する年度はありながらも成長を続けており、右肩上がりの増加傾向が続いています。
人材派遣会社と比較すると多すぎるわけではない
人材紹介会社と似ている業種が、同じ人材業界に位置する人材派遣会社です。人材派遣会社は、自社で雇用しているスタッフをクライアント企業へ派遣する業態です。自社がスタッフを直接雇用する形態に対して、人材業界会社は求職者と雇用契約を交わしません。
2023年度時点で、人材紹介会社は30,113の事業所が開設されています。非常に多い事業所数ですが、近い業種の人材派遣会社と比較してみると多すぎるとは言えません。厚生労働省の統計によれば、人材派遣事業の事業所数は2023年6月時点で43,736でした(※2)。人材派遣事業は、人材紹介事業所よりも数多くの事業所が存在しています。統計の観点からは、人材紹介会社が過剰に多いとは言えないでしょう。
※1 参照:厚生労働省「需要調整事業課税業務統計 - 民営職業紹介事業所数の推移」
※2 参照:厚生労働省「労働者派遣事業の事業報告の集計結果について - 労働者派遣事業の令和6年6月1日現在の状況(速報)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000079194.html
人材紹介会社が多い理由
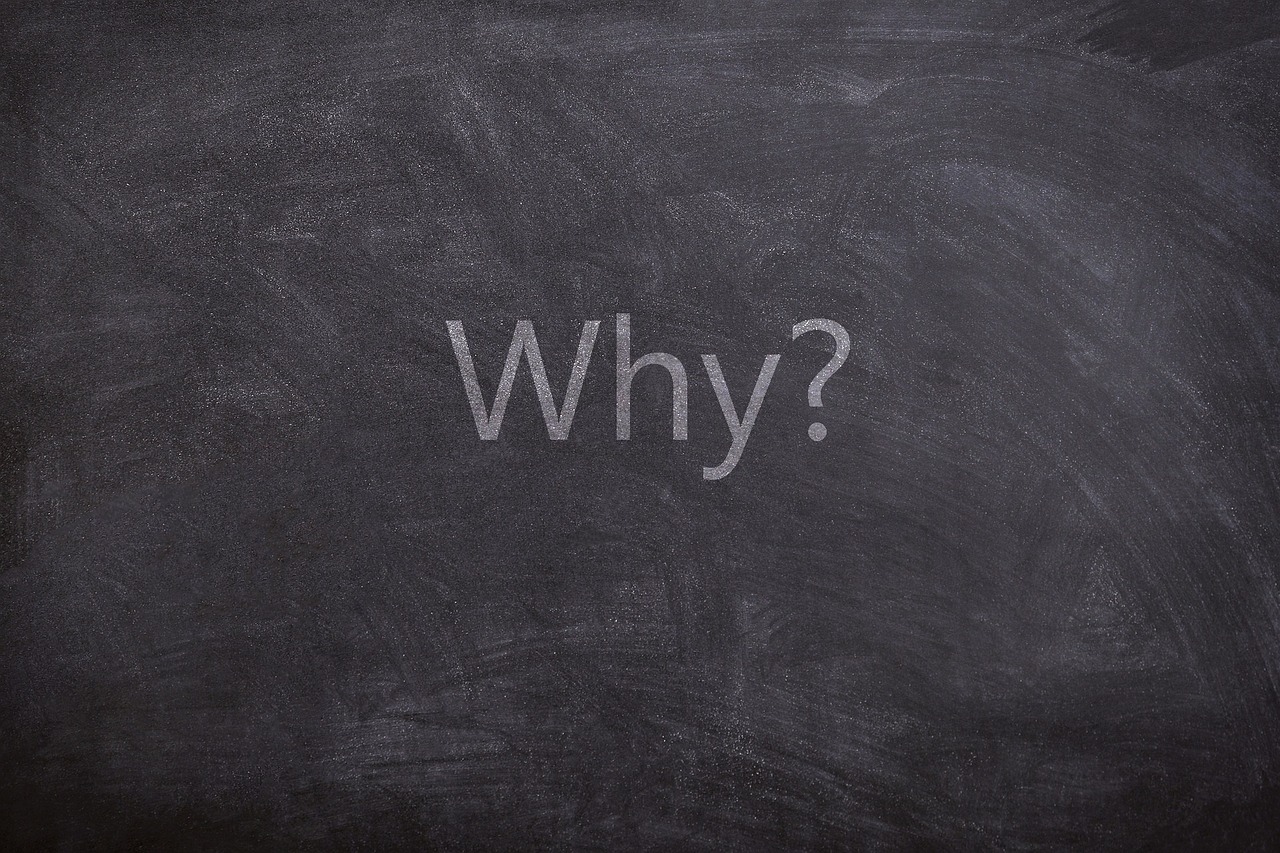
人材派遣会社と比べて多すぎるわけではないものの、人材紹介会社が増加傾向にあることは事実です。なぜ人材紹介会社は次々に立ち上げられているのでしょうか。人材紹介会社が多い理由として、次の2つが挙げられます。
利益率の高さ
1つ目の理由は、人材紹介会社の利益率の高さです。人材紹介会社の利益率(営業利益率)は20%前後と高い傾向があります。一般的な利益率は、5〜10%が標準または優良な経営状態の指標と言われています。人材紹介は無形サービスであり、求人企業や求職者を紹介するための直接的なコスト「売上原価」が発生しません。売上高から差し引かれる費用は人件費やオフィス代などの「販管費」だけとなり、高い利益率を実現しています。利益率の高さは事業を立ち上げるにあたって重要なポイントであるため、人材紹介会社を立ち上げる大きな理由となっています。
参入障壁の低さ
2つ目の理由は、人材紹介会社の参入障壁の低さです。人材紹介会社を設立するための資本金は500万円以上と定められています。資産から負債を除いた「基準資産額」で500万円を準備する必要があり、銀行からの借入などの負債は含まれません。個人にとって500万円は大きいですが、法人であれば小規模な会社でも比較的参入しやすい金額です。一方、人材派遣会社の基準資産額は2,000万円以上です。同じ人材業界であっても、人材紹介会社のほうが参入のハードルが低く、続々と新規企業が立ち上げられています。
人材紹介会社の倒産は増えている

多くの人材紹介会社が設立されていますが、倒産する企業も増加傾向にあります。人材紹介会社の倒産の実態について、統計をもとに説明します。
2024年度(4〜2月)は過去最多21件の倒産
株式会社東京商工リサーチの統計によると、人材紹介会社の倒産件数は2024年度2月時点における11ヶ月間の統計で21件発生しています(※3)。コロナ禍前である2019年度の人材紹介会社の倒産件数はわずか4件に留まっており、約5年間で5.25倍に増加しました(※4)。過去最多の倒産件数であり、2024年度末の3月分も統計に含まれるとさらに増える可能性があります。
倒産の主な原因は人手不足
人材紹介会社の倒産原因は、人手不足が中心です。人材紹介会社の社員が足りないのではなく、クライアント企業へ紹介する優秀な求職者を確保できずに倒産しています。人材紹介会社が増加していることから、人材獲得の競争が激化していると考えられます。また、少子高齢化による労働者不足の時代といえど、クライアント企業の需要に合う人材でなければ採用されません。さまざまなクライアントのニーズとマッチする人材を継続的に確保できない場合、人材紹介会社の経営は困難になるでしょう。
倒産の中心は中小規模の会社
倒産した人材紹介事業は、中小規模の会社が大半を占めています。東京商工リサーチの発表によれば、2023年度に倒産した16件のうち、8社が資本金1,000万円以下の企業でした(※4)。大手企業であれば、潤沢な資金による大量の広告宣伝で求職者の人気を集めやすく、豊富な人材を確保できます。一方、中小規模の会社は大手ほどの資金力がないため、大規模な宣伝が困難です。また、広告宣伝費による経営状況の圧迫も、倒産の一因となっています。
※3 参照:株式会社東京商工リサーチ「『人材関連サービス業』の倒産、過去10年で最多 人手不足と過当競争に加え、福利厚生も負担に」
https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1201152_1527.html
※4 参照:株式会社東京商工リサーチ「人手不足の時代に人材関連サービス業の倒産が急増 ~中小の人材紹介会社は長い冬の到来か~」
https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1198331_1527.html
人材紹介会社の市場規模は拡大している
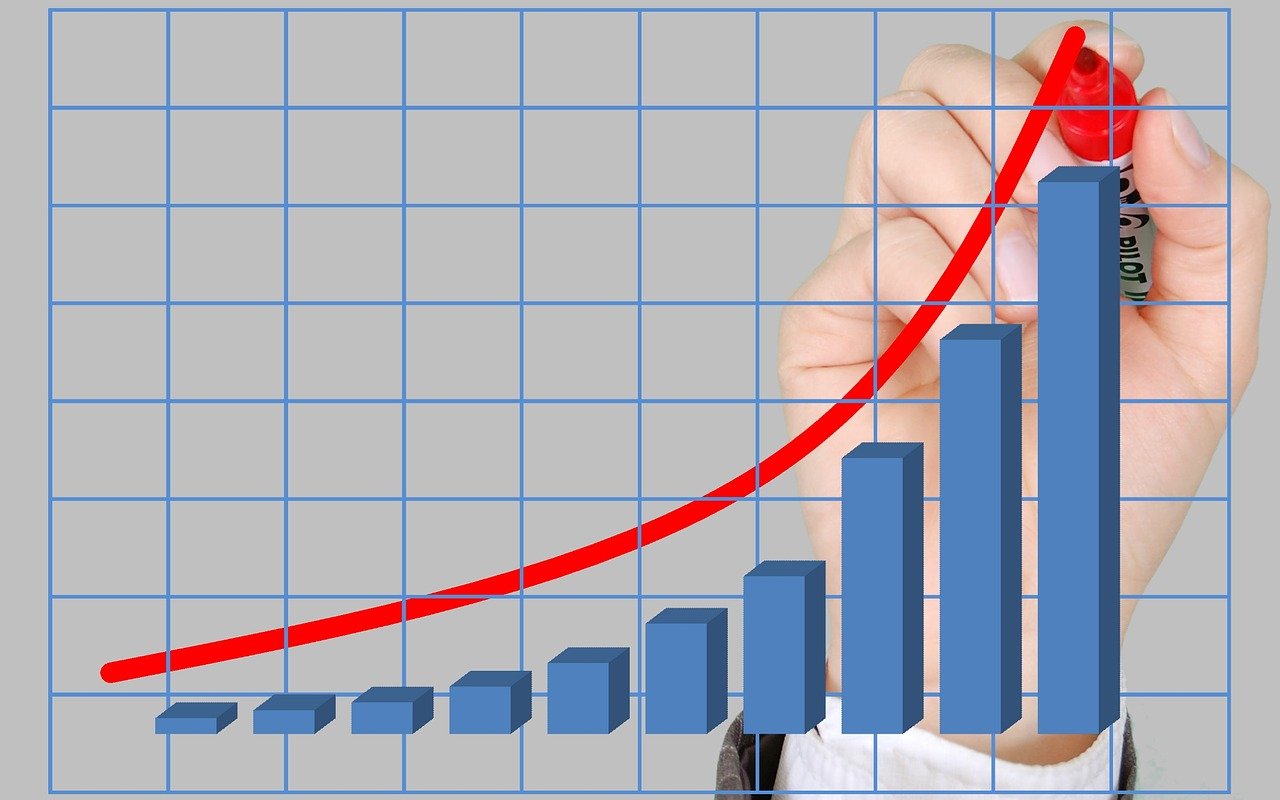
人材紹介会社の倒産件数が増えている一方で、市場規模は拡大しています。具体的な市場規模について見ていきましょう。
ホワイトカラー職種の人材紹介事業の市場規模は4,110億円
矢野経済研究所の統計資料によると、2023年度のホワイトカラー職種の人材紹介事業の市場規模は4,110億円でした(※5)。前年度比17.1%も成長しており、倒産件数が増えるなかで市場規模は拡大傾向にあります。なお、ホワイトカラー職種のみの統計であるため、市場全体の人材紹介事業ではさらに規模が大きいと考えられます。
手数料収入は約8,362億円に増加
2025年に発表された厚生労働省のデータによれば、人材紹介会社全体の2024年度の手数料収入は約8,362億円でした(※6)。前年度比で8.6%の成長です。ホワイトカラー職種に限定していない統計であるため、厚生労働省の統計のほうが人材紹介会社の市場規模の実態に近いと推測できます。
※5 参照:株式会社矢野経済研究所「人材ビジネス市場に関する調査を実施(2024年)」
https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3661
※6 参照:厚生労働省「職業紹介事業の事業報告の集計結果について - 令和5年度職業紹介事業報告書の集計結果(速報)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/shoukaishukei.html
人材紹介会社の将来性が高いと言える理由

倒産件数が増えていても、人材紹介の市場規模は成長しています。市場規模に加えて、以下3つの理由により人材紹介会社の将来性は高いと言えます。
常用求人数や新規求職申込件数が増え続けている
厚生労働省が発表した資料によると、2024年度における人材紹介会社の常用求人数や新規求職申込件数は増加傾向にあります(※6)。具体的な数値は、以下の通りです。
・常用求人数:11,856,612人(前年度比9.9%増)
・新規求職申込件数:38,608,712件(前年度比34.7%増)
常用求人数とは、雇用期間の定めのない求人で募集された人数です。新規求職申込件数とは、名前の通り新たに登録された求職申し込みの件数です。どちらも前年度比で大きく成長しており、求人企業と求職者の双方から高い需要が続いていると考えられます。
就職件数や手数料収入も伸びている
引き続き厚生労働省の同資料を見ると、常用就職件数および手数料収入の成長も好調だとわかります。
・常用就職件数:693,300件(前年度比 同 7.1%増)
・手数料収入:約5,418億円 (前年度比 21.9%増)
常用就職件数とは、人材紹介サービスを利用して雇用期間の定めのなく就職した件数です。手数料収入とは、紹介会社が得た紹介手数料の総額を意味します。人材紹介サービスによる求人企業と求職者のマッチングが成功していることから、いずれも前年から増加したと予想できます。
転職者が年々増加している
人材紹介会社の将来性が高い理由として、転職者の増加も挙げられます。総務省の統計によれば、2022年度の転職就業者は1,246万人でした(※7)。5年前から19万人も増えており、転職者は年々増加しています。転職者が増えることで、人材紹介サービスを利用する求職者の母数にも好影響が期待できるでしょう。求職者の母数が増えればマッチングの成約数も増え、人材紹介会社の安定した経営が見込めます。
※7: 参照:総務省「令和4年就業構造基本調査の結果 - 結果の要約」
https://www.stat.go.jp/data/shugyou/2022/index2.html
今後の人材紹介会社に求められるポイント

人材紹介会社の将来性は高いですが、倒産している企業が増えているのも事実です。激化する競争のなかで安定して事業を続けるためには、次の5つのポイントが重要になります。
マッチング精度の向上
クライアントである求人企業にむやみに人材を紹介するのではなく、企業にとって最適な人材の見極めが求められます。求人企業のニーズを満たすためには、綿密なヒアリングやさまざまな業界の知識が必要です。また、求職者のスキルや経験、希望の労働条件を正確に把握することで、求人企業と求職者の両者にとって最適なマッチングが可能になります。
大手との差別化
中小企業の場合、大手との差別化が不可欠です。大手は潤沢な資金により広告宣伝費にリソースを注ぎ込めますが、中小企業には限度があります。求人企業へ紹介する人材をコンスタントに確保できなければ、倒産のリスクが高まります。特定分野への求人特化や集客経路の多様化、求職者のキャリア相談およびトレーニングの充実など、自社ならではの魅力の強化が大切です。
柔軟な働き方が可能な求人の充実
働き方改革により、柔軟な働き方を希望する求職者が増えています。求人がどれほど多くとも、求職者が集まらなければ紹介手数料は得られません。従来の働き方のみに対応している求人だけでなく、リモートワークや時短勤務、フレックスタイム制といった柔軟な働き方を実現できる求人を獲得する必要があります。
多様な人材への対応
今後の日本は少子高齢化により生産年齢人口が不足していくため、さまざまな人材と企業のマッチングの実現がより重要になるでしょう。高齢者や中高年、外国人など、多様な人材への対応が求められます。加えて、求職者の集客や求人開拓の方法も増やすと、さまざまな層へリーチできます。広告だけでなく、ビジネスSNSやリファラル営業、セミナーや展示会への参加などの手段を取り入れることで、多様な人材および企業へのアプローチが可能です。
企業との長期的な信頼関係の構築
求人企業との長期的な信頼関係の構築も、事業の安定した運営に欠かせません。単発の求職者紹介だけで関係を終わらせず、次回の求人案件の獲得へつなぐ必要があります。採用決定後のアフターフォローを充実させるほか、採用戦略の支援やコンサルティング、人材育成のサポートといった活動も効果的です。
新規参入が多い人材紹介会社は競合との差別化が必要
人材紹介会社は多すぎるわけではないものの、利益率の高さや参入障壁の低さにより新規参入が多い事業です。人材紹介サービスを利用した就職件数は増えており、紹介手数料による収益も成長しています。将来性の高い事業といえますが、競争の激化により倒産件数が増えている点に注意が必要です。今後の人材紹介会社は、競合他社との差別化が一層重要となるでしょう。
この記事の監修者
長沢 ひなた
外資系アパレルで販売・チーム運営を経験後、美容クリニックのカウンセラーに転身。60名中3名のみのトップカウンセラーとして表彰され、マネージャーとして大規模なチームマネジメントも経験する。
「人生単位での変化」を支援したいとの想いからキャリアアドバイザー職へ転身し、入社半年での異例の昇格、1年でリーダーに就任。現在は、キャリアアドバイザー職への転職を専門に、業界構造を熟知した的確な支援を行っている。(▶︎詳しく見る)
基礎知識のおすすめ記事
-
2024/11/20
キャリアアドバイザー(人材紹介営業)で成果を出すコツとは?売上を伸ばす方法を8つのステップで徹底解説
-
2026/01/23
人材業界に向いている人の特徴とは? 仕事内容やスキルを鍛える方法を解説
-

2024/10/16
キャリアアドバイザー(人材紹介営業)職でホワイト企業に転職する方法
-

2024/10/16
キャリアアドバイザー(人材紹介)は未経験からでも転職できる?営業未経験でも応募可能な求人例あり