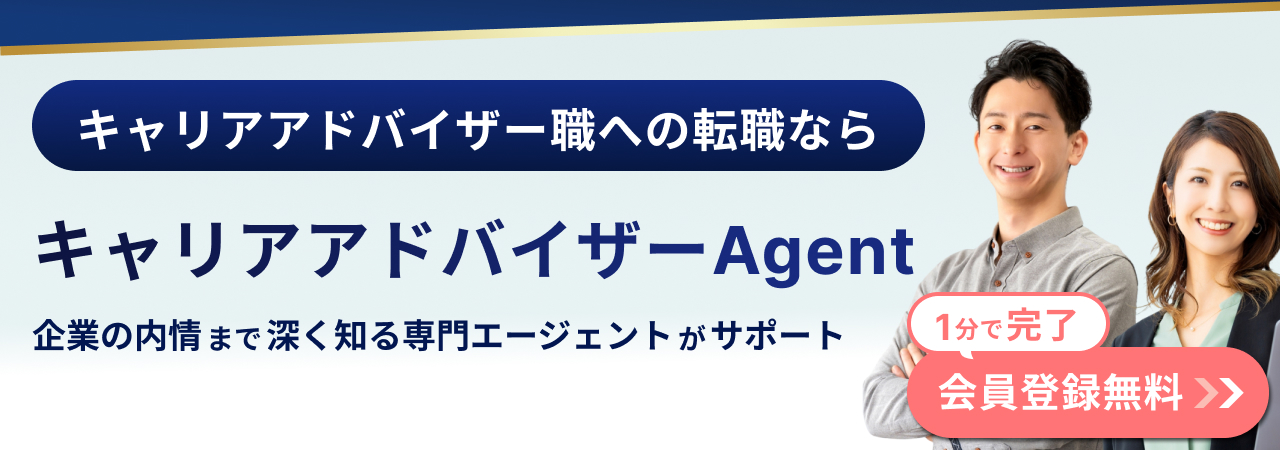2025年7月10日公開
最終更新日:2025年12月10日
人材紹介サービスとは? 手数料のシステムやメリット・デメリット、活用がおすすめな企業を解説
人材紹介サービスとは、求職者と求人企業をマッチングするサービスです。具体的には、どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか。この記事では、人材紹介サービスの詳細を解説します。人材紹介サービスの活用をおすすめできる企業や、採用者の内定・入社後のフォローについても紹介しますので、ぜひご覧ください。
【関連記事】当社が運営する「キャリアアドバイザーAgent求人ナビの転職支援サービス」の特徴や登録のメリットについてご紹介。
人材紹介サービスの基本情報
はじめに、人材紹介サービスの基本情報から確認しましょう。
人材紹介サービスとは
人材紹介サービスとは、新規人材の採用を考える企業と新しい職を探す求職者を結びつける有料サービスです。「転職エージェント」とも言われています。また、人材紹介サービスは、職業安定法における「有料職業紹介事業」に該当するビジネスです。有料職業紹介事業を開業する際は、事業所を管轄する労働局へ届け出て厚生労働大臣の許可を得る必要があります。一方、報酬を受け取らない「無料職業紹介事業」は、ハローワークが当てはまります。
人材紹介サービスに依頼できる内容
人材紹介サービスでは、企業と求職者の双方がさまざまな支援を受けられます。求人企業側は、求人票の作成や採用要件の整理、募集活動の代行、応募者との面接日程の調整といった業務を依頼できます。自社のみの採用活動では出会えない人材を、幅広いネットワークから探せる点が強みです。対する求職者側は、自分に合った求人情報の紹介から応募書類の作成サポート、面接対策、内定後の条件交渉までトータルで支援を受けられます。担当コンサルタントが間に立って企業とのやりとりを代行するため、安心して転職活動を進められます。
人材派遣との違い
人材紹介と人材派遣は似たイメージを持たれがちですが、両者は仕組みが大きく異なります。人材紹介は企業と求職者の直接雇用を前提としているため、採用が決まると求職者は紹介先企業の正社員や契約社員として雇用されます。一方、人材派遣は派遣会社が雇用主となり、派遣先企業へ一定期間労働者を派遣するシステムです。つまり、雇用契約の相手が人材紹介では求人企業、人材派遣では派遣会社となります。
人材紹介サービスの形態

人材紹介サービスにはいくつかの形態があり、企業の採用方針や求職者の状況に応じて使い分けられています。代表的な形態は、以下の3つです。
一般紹介型
一般紹介型とは、人材紹介サービスが保有する求職者データベースから、企業のニーズに合った人材を探して提案する形態です。データベースにはあらかじめ登録面談を受けた多様な求職者の情報が一覧化されており、希望条件やスキル、経験を踏まえて求人企業とのマッチングが行われます。多様な母集団から候補者を選定できるため、多くの企業に利用されています。さらに、幅広い業種・職種に対応する「総合型」と、特定分野を専門的に扱う「特化型」に分かれている点も特徴です。
サーチ型(スカウト型)
サーチ型(スカウト型)とは、求人企業が求める条件に合致する人材を紹介会社が主体的に探し出す形態です。データベースに登録済みの求職者だけでなく、場合によっては現在就業中の潜在的な転職希望者にもアプローチします。具体的には、SNSや外部の人材データベースの活用、求人広告の掲載、リファラルリクルーティングなどの手段で候補者ごとに個別に接触します。ヘッドハンティング型のサービスであるため、とりわけ経営層や管理職、専門職といった希少性の高い人材を採用したい場合におすすめできる形態です。
アウトプレースメント型
アウトプレースメント型とは、クライアント企業の従業員の再就職支援に特化した形態です。事業の縮小や経営統合で人員整理が必要になった際に、従業員がスムーズに就職先を見つけられるようにサポートします。従業員側にはキャリアカウンセリングや応募書類の作成支援、求人紹介といったフォローを実施して、企業側には解雇手続きや法的な紛争の防止・処理などの支援を行います。従業員側はサポートを受けながら再就職先を探せて、企業側は円満退職を実現できることから双方にとってメリットの大きいサービスです。
人材紹介サービスの手数料のシステム

人材紹介サービスの手数料は、誰がいつ支払うのでしょうか。サービスを利用する前に、きちんと理解しておきましょう。
求人企業が紹介手数料を支払う
人材紹介サービスの利用料金は、採用を行う求人企業が支払います。求職者の入社日に、「紹介手数料」として利用料金が発生する形式が一般的です。多くの場合、手数料の金額は採用する人材の理論年収に一定の料率を掛けて算出します。たとえば、料率30%の人材紹介サービスによって理論年収500万円の人材を採用した場合、紹介手数料は150万円になります。料率は人材紹介サービスによって異なり、30〜35%が平均的です。
料金体系は成功報酬型がメイン
人材紹介サービスの料金体系は、成功報酬型がほとんどです。成功報酬型では、人材の採用が成立しなければ紹介手数料は発生しません。ただし、経営幹部や専門職などの採用難易度が高いポジションを求める場合、契約時に「着手金(リテイナーフィー)」が必要になるケースもあります。着手金とは、候補者のリサーチやスカウト活動を行うための費用であり、採用の成否にかかわらず紹介手数料の一部が請求されます。候補者の採用確定後に、紹介手数料の残りを支払う仕組みです。一般的には、スカウト型の人材紹介サービスで用いられています。
求職者は無料で利用できる
求職者は、人材紹介サービスの利用料金がかかりません。職業安定法第32条によって、求職者からの手数料徴収は、芸能家やモデルといったごく一部の職種をのぞいて禁止されているからです。そのため、人材紹介会社への登録からキャリアカウンセリング、求人紹介、書類添削、面接対策、内定後のサポートまで、求職者は一貫して無料でサービスを受けられます。求職者は費用面の心配をせず、安心して転職活動に専念できるでしょう。
人材紹介サービスへの最新技術の導入による変革

近年、人材紹介サービスは最新テクノロジーの導入によって変革を遂げつつあります。従来は人の手による作業や経験に依存していた領域が、AIやデータの活用によってよりスピーディかつ精度の高いマッチングが実現し始めています。ここでは、中でも注目される3つの変革を見ていきましょう。
AI活用による業務効率化
従来はコンサルタントが1つひとつ手作業で0から作成していたスカウトメールや求人票を、AIがベースを自動生成することで作業時間の削減が可能です。AIは候補者のプロフィールや希望条件、企業の求人情報をもとに個別に最適化されたメッセージを作成します。もちろん、完全にAI任せではなく人の手による推敲が必要ですが、大幅に作業時間を短縮できます。CA(キャリアアドバイザー)やRA(リクルーティングアドバイザー)は候補者対応や企業との面談など、より付加価値の高い業務に注力できるでしょう。
求職者抽出の自動化
AIや機械学習によって、求人条件にマッチする求職者の抽出作業の自動化が可能です。通常、人材をマッチングするためには、担当者が膨大な候補者データベースから求職者を絞り込む必要があります。そこでAIを活用することで、求人条件と求職者の経歴や希望、スキルを自動的に照合して、マッチ度の高い候補者をリストアップできる仕組みが整いつつあります。候補者発掘のスピードと品質を向上できれば、クライアント企業への提案力が強化されるでしょう。
顧客体験の向上
最新技術の活用は、顧客体験の向上にもつながります。たとえば、人材紹介向けのCRM(顧客管理システム)を使えば、企業および求職者データの一元管理が可能です。求職者への対応履歴や応募履歴、希望条件と、企業側の求人状況を照合して、最適なマッチングを行えます。また、チャットボットを導入すると、ユーザーからの問い合わせに24時間自動で対応できます。求人情報の確認や面接の日程調整、選考状況の進捗確認などの案内をスムーズに行えるため、営業時間外のサポートが可能です。
人材紹介サービスを利用するメリット

企業が人材紹介サービスを利用するメリットを5つ解説します。
マッチング精度の高い人材に出会える
人材紹介サービスを利用すると、マッチング精度の高い人材に接触できます。人材紹介会社が保有するデータベースには、さまざまな業界や職種、年齢層の求職者の情報がまとめられています。そのうち、企業の採用条件に合致する人材を絞り込んで紹介されるため、自社だけではアプローチしきれない幅広い層とのマッチングが可能です。求職者のキャリアプランも踏まえて紹介されることから、ミスマッチを最小限に抑えたうえで選考を進められます。
採用活動の負担を減らせる
人材紹介サービスに求職者の応募受付や選定を任せられるため、採用活動における自社の負担を軽減できます。自社で採用活動を完結する場合、求人票の作成や応募受付、書類選考、面接の日程調整、候補者対応などの多岐にわたる関連業務が発生します。人材紹介サービスに採用活動の大部分を代行してもらうことで、求職者との面談といった重要な部分に自社のリソースを集中させられるでしょう。限られたリソースでも効率的に採用プロセスを進行できるため、採用担当者の負担を減らせます。
高度なスキルを持つ人材に接触できる
特定の業界や職種に特化した人材紹介サービスを活用すると、高度なスキルを持つ人材を探しやすくなります。具体的には、ITエンジニアや医療専門職、管理職クラスなどの専門的な人材に特化したサービスがあります。こうした専門性の高い職種や経験豊富な即戦力人材を採用したい場合、一般的な求人サイトではなかなか候補者が集まりません。特化型の人材紹介サービスによって、一般的な求人サイトや自社単独ではアプローチできない人材に接触できます。
採用できなくとも料金が発生しない
人材紹介サービスを利用した結果、求職者を採用できなかった場合でも成功報酬型の料金体系であるため、紹介手数料は生じません。初期費用が発生しないことから、無意味にコストを浪費せずに採用活動を行えます。ただし、サーチ型のサービスを利用する場合、契約時に着手金(リテイナーフィー)が必要になるケースが一般的です。サーチ型のサービスは採用の成否にかかわらず初期費用が発生するため、料金体系および契約内容は事前に確認しましょう。
早期退職は手数料が返金される
人材紹介サービスによって採用した求職者が早期退職した場合、手数料が返金されます。せっかく採用した求職者がすぐに辞めてしまうと、採用企業の費用と時間が無駄になってしまうでしょう。そのため、多くの人材紹介サービスは「返戻金制度」を設けており、一定期間以内に採用者が退職した場合に手数料が返金されます。よくある規定は、「1ヶ月未満の退職は手数料の80~100%返金」「1ヶ月から3ヶ月以内の退職は手数料50%返金」といった段階的なルールです。返戻金制度により、万一の早期退職があっても企業に大きな痛手は生じません。
人材紹介サービスを利用するデメリット

人材紹介サービスは多数のメリットがありますが、以下3つのデメリットも存在します。
採用活動の知識を蓄積できない
人材紹介サービスは便利な一方で、社内に採用ノウハウが蓄積されにくいといった側面があります。採用担当者が経験を積む機会を失いやすく、将来的に自社主導で採用を進める際に必要な知識や手順が不足する可能性が考えられます。自社の採用力を高めたいのであれば、人材紹介サービスに任せきりにせず、積極的にコミュニケーションを取って情報を共有してもらいましょう。
条件によっては求職者が紹介されにくい
求職者に求める条件を絞り込みすぎると、なかなか人材を紹介されない場合があります。人材紹介サービスでは、データベースに登録された求職者から人材を探したり、直接的に求職者をスカウトしたりして候補者を紹介する仕組みです。しかし、企業が求める条件が厳しすぎるほど、候補者が見つかりづらくなります。人材紹介サービスを活用する際は、求人条件に優先順位をつけましょう。絶対に必要な条件と妥協できる条件を柔軟に設定すれば、多様な候補者とマッチングできます。
費用が高額になるケースもある
人材紹介サービスの紹介手数料の料率によっては、費用が高額になる可能性があります。一般的な料率は30〜35%ですが、ハイレベルな人材紹介においては高い料率を設定しているサービスが珍しくありません。さらに、紹介手数料は採用者の理論年収に料率を掛けて算出するため、理論年収が高ければその分だけ費用が増します。予算を確保せずに進めると採用決定後に人材紹介サービス側とトラブルが生じかねないため、事前に見積もりや求人条件をしっかりと相談してから進めましょう。
人材紹介サービスの活用をおすすめできる企業

人材紹介サービスは多様な業界で利用されていますが、中でも相性が良い企業の特徴があります。ここでは、人材紹介サービスの活用をおすすめできる企業の特徴を5つ挙げます。
長期雇用の社員を求めている企業
長期雇用の社員を求める場合、人材紹介サービスの利用が向いています。人材紹介サービスで扱う雇用形態は、正社員や契約社員が一般的です。さらに、求職者は入社後に企業と直接雇用契約を結ぶため、自社で長期的に活躍してもらうことが前提となります。人材紹介サービスを使うことで、中長期的に事業を支えてくれる人材をすばやく確保できます。
急な欠員に対応する必要がある企業
人材紹介サービスはすぐに利用開始できるため、急な欠員へ対応できます。予期せぬ退職や人事異動、事業拡大などの理由で、突然新たな人材が必要になる事態は少なくありません。自社でいちから募集広告を出して選考を進めるよりも、人材紹介サービスのほうが短期間で候補者を集められます。人材紹介サービスはあらかじめ求職者の母集団を管理しているため、条件に合う人材が見つかれば即座に紹介してもらえます。
非公開で募集したい企業
非公開求人によって人員を募集したい企業にも、人材紹介サービスの利用が向いています。たとえば、新規事業の立ち上げや組織再編を行う際、採用活動は不特定多数に知られたくない場合があるでしょう。人材紹介サービスでは、非公開求人によってごく少数の候補者のみに求人情報を開示できます。非公開求人であっても人材をマッチングできるため、情報の公開範囲を限定しながらの採用活動を行えます。
専門的なスキルを持つ人材を獲得したい企業
特定の資格や高度な専門知識、マネジメント経験を持つ人材は、市場全体で常に不足している傾向があります。ハイクラス人材や専門職に特化した人材紹介サービスを利用すれば、求めるスキルや経験をピンポイントで持つ求職者に出会いやすくなります。手数料は高くなりやすいですが、自社ではアプローチしにくいハイレベル人材を確保したい企業にとっては有効な手段となるでしょう。
採用活動のノウハウが足りない企業
採用経験が浅い企業や、採用を担当する部署や担当者が充分に整っていない企業にとって、人材紹介サービスの活用は効果的です。求人票の作成から内定後のフォローまで経験豊富なエージェントがサポートすることで、採用ノウハウが不足している企業でも問題なく採用プロセスを進められます。また、転職市場の動向を考慮したうえで適切な採用戦略を練ってもらえるため、的外れな募集条件を設定するリスクも避けられます。
人材紹介サービスを選ぶ際の比較ポイント

人材紹介サービスは、得意な分野や職種が会社によって大きく異なります。自社に合う人材紹介サービスを選ぶためには、次の5つの比較ポイントに注目しましょう。
サービスの取り扱い業界・職種
人材紹介サービスが取り扱う業界や職種が、自社の求める人材とマッチしているかを確認しましょう。人材紹介サービスの取り扱い範囲は、あらゆる業界や職種を広く扱う「総合型」と、特定の業界や職種のみ扱う「特化型」の2種類があります。総合型は登録者が多いことから、幅広い人材から選考したい場合に向いています。一方の特化型は、ITや医療、福祉などの専門性の高い人材を探しやすい点が強みです。人材の採用要件に合わせて、利用するサービスを絞り込みましょう。
採用実績と登録者数
人材紹介サービスの選び方として、採用実績や登録者数も大切です。これまでにどういった業種や職種でどの程度の採用支援を行ってきたのか、公式ホームページや資料請求から実績をチェックしましょう。自社の業界や求める職種の採用実績が豊富であれば、充実した人材紹介が期待できます。加えて、サービスの登録者数も確認しましょう。求職者の母集団が多いほど多様な人材とマッチングできるため、スピーディな採用選考が可能です。
担当者の知識や理解度
人材紹介サービスの質を左右するポイントの1つが、担当者の知識や理解度です。業界に詳しい担当者ばかりではなく、経験が浅い担当者が自社につく場合もあります。担当者が幅広い業界知識を持っていると、転職市場の動向をふまえた的確なアドバイスや、スムーズな採用要件のすり合わせが期待できます。商談や打ち合わせの段階で、自社の業界特有の課題や職種の要件についてしっかり理解してもらえるか、担当者のスキルを見極めましょう。
担当者の業務範囲
人材紹介サービスの担当体制は、「分業型」と「両手型(統一型)」に分かれます。分業型とは、求職者にはCA(キャリアドバイザー)が、企業にはRA(リクルーティングアドバイザー)が個別に担当する体制です。それぞれの役割に専念できることから、充実したサポートを受けられます。一方の両手型(統一型)とは、同じスタッフが企業と求職者を担当する体制です。情報の抜け漏れが起きづらく、双方の状況を細やかに把握しながら選考を進められます。人材紹介サービスの体制を確認して、自社と相性の良い会社を選びましょう。
サポート内容
人材紹介サービスによって具体的なサポート内容は違うため、あらかじめ自社が求める支援内容を定義しておきましょう。求人票の作成支援、応募者へのアプローチ、面接日程調整、条件交渉、入社後フォローなどの基本的なサポートに加えて、さらなるサポートを提供しているサービスもあります。たとえば、採用ブランディングや採用コンサルタント、求職者向け研修・セミナーの実施といったサポートが該当します。自社にとって必要な支援を明確にしたうえで、最適なサービスを洗い出しましょう。
人材紹介サービスの利用で成果を出すポイント

人材紹介サービスを単に契約しただけでは、期待通りの成果が出ないケースもあります。人材紹介サービスの利用で成果を出すためには、以下5つのポイントを実践してみてください。
採用したい人物像をすり合わせる
人材紹介サービスの担当者としっかり打ち合わせして、採用したい人物像を共有しましょう。担当者との打ち合わせでは、求人票に記載する表面的な条件だけでなく、組織文化やチームの雰囲気、理想的な人物像まで具体的に伝えます。具体的には、「1分単位で残業代を支給するので、残業を受け入れられる人」「お客様との折衝が多いため、一定以上のコミュニケーション能力と柔軟性を持った人」といった細かな人物像です。求める人物像をはっきりと伝えることで、一貫性のある求職者を紹介してもらえます。
自社の強みを明らかにする
求職者へのアピールポイントとして自社の強みを明らかにして、人材紹介サービスの担当者へ伝達しましょう。近い待遇で求人を出している他社との違いがわからなければ、自社は求職者からなかなか選ばれません。フレックスタイム制やリモートワークなどの勤務体制、風通しの良い社風、スキルアップ支援、自社ならではの福利厚生など、他社との違いを明確にして担当者に共有しましょう。求職者への訴求力が高まるだけでなく、入社後のミスマッチ防止にもつながります。
担当者へフィードバックを行う
紹介された求職者に関するフィードバックは、必ず行いましょう。不採用や内定事態などの場合でも、求職者のどのようなポイントが自社と合わなかったのかの共有が重要です。担当者はフィードバックをもとに選考基準を見直すため、次回以降のマッチング制度の向上が見込めます。フィードバックを怠ると条件に合わない人材の紹介が繰り返されてしまい、採用活動が長期化しかねません。短期で成果を出すには、丁寧なフィードバックが不可欠です。また、今後もサービスを利用するのであれば、採用決定者の評価点も伝えましょう。
無理な要求をしない
人材紹介サービスを利用するうえで、担当者に無理な要求や過度なプレッシャーをかけるのは逆効果です。信頼関係が崩れてしまうと、担当者にとって自社の優先度が下がるリスクがあります。通常、人材紹介サービスのエージェントは複数の企業を担当しているため、自社の優先度が低ければ他社に優秀な人材を紹介されてしまうかもしれません。想定より採用に時間がかかっても担当エージェントへは丁寧に対応して、不用意に自社の印象を下げるような行動は避けましょう。
人材紹介サービスに任せきりにしない
採用活動の一部を代行してもらえるからといって、人材紹介サービスに任せきりにしてはいけません。面接を通じて、最終的に求職者の内定の意思決定を後押しするのは企業の役目です。求職者と面接の場で丁寧にコミュニケーションを取って、内定へのモチベーションを保ちましょう。さらに、担当者との定期的な連絡や進捗確認を怠らず、情報をすばやくキャッチしましょう。能動的に動くことで、良い候補者が現れたタイミングを逃さずスピーディに採用を決められます。
人材紹介サービスによる内定後・入社後のフォローアップ

人材紹介サービスによるサポートは、内定後までが基本です。しかし、中には入社後のフォローアップまで行うサービスも存在します。内定後および入社後のよくあるフォローアップ内容は、次の4つです。
オファー面談の実施
内定が決定した求職者には、人材紹介サービスが主導してオファー面談を行います。最終的な入社の意思確認と内定辞退を防ぐための重要な機会です。具体的には、雇用条件や業務範囲、評価制度、入社日などの情報をあらためて確認します。また、求職者が漠然とした不安を抱えている場合、オファー面談で疑問を解消して最終的に入社を決断できるように支援します。オファー面談を通じて条件面の行き違いを防ぐことで、内定辞退や入社後のミスマッチを減らせるでしょう。
実際の業務や労働条件の確認
求職者の入社後は、入社前に提示されていた業務内容や労働条件が正しいかを人材紹介サービスの担当者が確認します。たとえば「仕事内容が面接時の説明と違う」「給与の条件が一部反映されていない」といったトラブルは、双方の認識のずれから起こりやすい問題です。人材紹介サービスの担当者が間に立ち、企業側へ条件の再確認や必要に応じた改善交渉を行います。人材紹介サービスが公平に状況を把握して調整することで、求職者の早期退職やトラブルを防止できます。
悩みや課題のヒアリング
入社後しばらく経つと、新しい環境への適応に悩みや不安を感じる求職者も出てくるでしょう。入社から1ヶ月後や3ヶ月後などの一定期間が経過したタイミングで人材紹介サービスの担当者が求職者にヒアリングを行って、現場での課題やメンタル面の不安を聞き取ります。電話や面談、入社後アンケートなどの手段で、入社後でも求職者が相談できる機会を設けることで企業に長く定着できるように支援してくれます。
契約社員の更新対応
人材紹介サービスを通じて契約社員を採用した場合、契約期間が終了するタイミングで更新や今後の働き方に関するフォローが行われます。人材紹介サービスの担当者が求職者と面談して、現職に対する満足度や今後の希望をヒアリングしたうえで契約更新の意思を確認します。さらに、企業側とも契約継続の可否や条件について調整を進めるため、双方ともに契約更新に関して適切に判断できるでしょう。また、正社員として登用する場合は契約切り替えの手続きも支援してもらえるため、トラブルなく新たに契約を交わせます。
人材紹介サービスの活用で優秀な人材の獲得を実現
人材紹介サービスは企業の採用を効率化して、ハイクラス人材の確保や入社後の定着支援まで幅広くサポートします。基本的には成功報酬型の料金体系であるため、初期費用が発生しません。コスト面のリスクを抑えられる一方、想定外の費用負担や採用ノウハウの蓄積不足には注意が必要です。人材紹介サービスを選ぶ際は、採用実績や担当者の知識を比較して自社に合う会社を絞り込みましょう。
また、特化型のサービスの場合、自社が求める業種や職種の人材を効率的に探せます。たとえば、CA(キャリアアドバイザー)に特化した株式会社9Eの「キャリアアドバイザーAgent」であれば、採用ニーズに合う専門的なスキルを持つCA人材とマッチングできます。
キャリアアドバイザーAgentの転職支援サービスではキャリアアドバイザー職を募集する企業の裏側まで熟知したエージェントが転職を支援いたします。推薦文でも、なぜキャリアアドバイザーを目指しているのかなど言語化を行い書類通過率を高めます。
さらに、応募書類作成のサポートや企業ごとの面接対策など徹底した伴走型の転職支援を提供。「書類も面接もこれまでより通過率がダントツに上がった」「年収交渉をしてもらい希望年収が叶えられた」など口コミでも高い評価をいただいています。自身の志向にあったキャリアアドバイザー職を目指している方はぜひ以下ボタンから面談予約してください。
この記事の監修者
長沢 ひなた
外資系アパレルで販売・チーム運営を経験後、美容クリニックのカウンセラーに転身。60名中3名のみのトップカウンセラーとして表彰され、マネージャーとして大規模なチームマネジメントも経験する。
「人生単位での変化」を支援したいとの想いからキャリアアドバイザー職へ転身し、入社半年での異例の昇格、1年でリーダーに就任。現在は、キャリアアドバイザー職への転職を専門に、業界構造を熟知した的確な支援を行っている。(▶︎詳しく見る)
基礎知識のおすすめ記事
-
2024/11/20
キャリアアドバイザー(人材紹介営業)で成果を出すコツとは?売上を伸ばす方法を8つのステップで徹底解説
-
2026/01/23
人材業界に向いている人の特徴とは? 仕事内容やスキルを鍛える方法を解説
-

2024/10/16
キャリアアドバイザー(人材紹介営業)職でホワイト企業に転職する方法
-

2024/10/16
キャリアアドバイザー(人材紹介)は未経験からでも転職できる?営業未経験でも応募可能な求人例あり