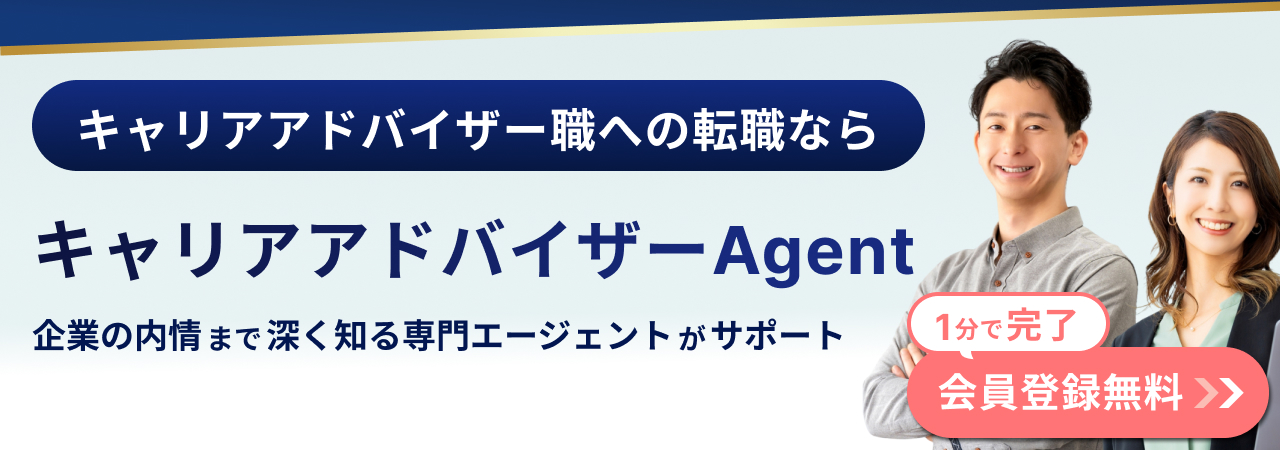2025年10月27日公開
最終更新日:2025年12月11日
人材紹介の不正行為「中抜き」とは? バレる理由やトラブルを防ぐための対策を解説
人材紹介における中抜きは、事業収益に甚大な影響を与える不正行為です。キャリアアドバイザーやコーディネーターとして職務に従事するのなら、そのリスクと実態を認識しておく必要があります。
この記事では、人材紹介における中抜きとは何を指すのか、その定義や具体的な事例を紹介します。中抜きがバレる理由や未然に防ぐための対策なども解説しますので、知識として押さえておきましょう。
【関連記事】当社が運営する「キャリアアドバイザーAGENT」に関する評価・評判は、『キャリアアドバイザーAgent 求人ナビの評判は?CA転職特化エージェントの実績と口コミを徹底解説』の記事を参照してください。
人材紹介における「中抜き」とは?
人材業界では、「中抜き」と呼ばれる不正行為が大きな問題になっています。中抜きとは、人材紹介会社が紹介した人材を、求人企業が内密に採用し、紹介手数料の支払いを回避する行為を指します。
実際に中抜きは以下のようにして行われます。
1. 人材紹介会社が求人企業に人材を紹介し、書類選考・面接が実施される
2. 選考中または不採用通知を出した後に、求人企業が人材に接触し、直接取引を持ちかける
3. 人材紹介会社を通さずに、求人企業と人材が雇用契約を結ぶ
人材紹介会社の多くは、成功報酬型のビジネスモデルを採用しています。そのため、中抜きが発生すると売上の減少や業績悪化につながってしまいます。
中抜きを放置するリスク
中抜きが頻発すると、多額の紹介手数料が回収できなくなるため、成功報酬型の人材紹介会社は大きなダメージを受けます。
人材紹介の紹介手数料の相場は、理論年収の30~35%程度です。仮に、年収400万円の人材の中抜きが3回発生した場合、人材紹介会社の損失は360〜420万円に達します。これは経営を圧迫するに十分な額です。
特に小規模な人材紹介会社では、中抜きが横行すると事業の継続が困難になり、最悪の場合、倒産に至るリスクもあります。
人材紹介の中抜き事例! 3つの手口を紹介

実際に、中抜きはどのような手口で行われているのでしょうか。
ここでは、代表的な3つの中抜きの手口を取り上げます。
事例1. 求職者にボーナスの上乗せを持ちかける
求人企業が選考中の求職者に対し、「本来なら人材紹介会社に支払う手数料分をボーナスとして上乗せするので、人材紹介会社を通さずに直接雇用契約を結んで欲しい」などと持ちかけるケースです。
金銭的なメリットに惹かれて応じてしまう求職者もいますが、実際には、入社後にボーナスを支払う約束を反故にされたり、支払われたとしても少額であったりするなど、結果的に求職者が不利益を被る事例が多発しています。
事例2. 直接応募を採用の条件とする
意図的に不採用通知を出し、後から求職者に接触して直接応募を唆すのも、よくある中抜きの手口です。「人材紹介会社には内緒で直接応募してくれたら採用する」などと求職者に持ちかけます。
中には、求職者に不正行為を悟られないよう、「人材紹介会社には不採用と連絡をしたが、もう一度採用を検討したいので、申し訳ないが直接履歴書を送ってほしい」などと、まるで自然なやり取りであるかのように装い、中抜きを図るケースもあります。
求職者が不審に感じなければ、そのまま採用、契約という流れになり、人材紹介会社側が不正に気付くきっかけがないまま中抜きが成立してしまいます。
事例3. 時間を置いて直接契約を提案する
中抜きがバレるリスクを減らすために、しばらく時間を置いてから求職者に接触を図る手口も見られます。人材紹介会社から紹介された求職者を一旦不採用にした後、数週間〜数ヵ月など一定期間を経て直接連絡を取り、採用を持ちかけます。
人材紹介会社と求職者が密に連絡を取り合っている状況下では、直接契約を持ちかけられたことを人材紹介会社に報告されるリスクが高まります。そのため、中抜きを狙う企業は、両者の関係が薄れるタイミングを見計らって求職者に声をかけます。
求人企業が中抜きをする理由

中抜きは、紹介手数料の支払いを免れる目的で行われることが大半です。「高額な紹介手数料を払いたくない」というのが一番の理由です。
人材紹介会社を利用して人材を採用する場合、求人企業は人材紹介会社に対して紹介手数料を支払う必要があります。一般的に、紹介手数料は理論年収の30~35%程度に設定されることが多く、年収400万円の人材を採用した場合は120〜140万円、年収700万円の人材であれば210〜245万円の高額な費用が発生します。
特に、人の入れ替わりが激しい企業や、財務基盤が脆弱な企業では、紹介手数料の支払いが大きな負担になります。「紹介手数料の支払いをどうにかして回避したい」「高額な採用コストを払うのがもったいない」という心理が、企業を中抜きへと駆り立てる要因となっています。
意図せず中抜きしてしまうケースも
求人企業が人材紹介に関するルールを十分に把握しておらず、無自覚に中抜き行為をしてしまうことがあります。
具体的な事例を以下に挙げます。
企業側に悪意がなかったとしても、このような事例が発生すれば、人材紹介会社は本来得られるはずの手数料が回収できず、損害を受けることになります。
故意か過失かを問わず、中抜きを発生させないための対策が求められます。
求職者からの申告によって中抜きはバレる

中抜き行為は、求職者からの申告や求人企業の不審な行動によって発覚します。
特に多いのが、求職者からの情報提供です。中抜きがバレる主なケースを以下に挙げます。
多くの求職者は、不正な行為に加担してまで職を得ようとは考えていません。そのため、求人企業が直接採用を持ちかけた時点で、その情報が人材紹介会社に共有されるケースが殆どです。
求職者に対する不適切な接触や中抜き行為は発覚しやすく、求人企業にとってリスクの高い行為といえます。
中抜きが発覚すると違約金の支払いや訴訟に
通常、人材紹介契約には、中抜きを禁止する条項や、禁止行為を行った場合の違約金に関する規定が盛り込まれています。中抜きが発覚した際、人材紹介会社はこの契約に基づいて求人企業に請求を行うことができます。
人材紹介契約の内容にもよりますが、多くのケースでは紹介手数料相当額の支払いや違約金を請求する形になります。
企業が支払いに納得せずトラブルになった場合は、まずは話し合いで解決を目指しますが、それでも決着しない時は訴訟に発展することもあります。
求人企業の中抜きはどう防ぐ? 3つの対策

中抜きを防止するための対策として、以下の3つが挙げられます。
1. 契約書で中抜きの禁止を明確に定める
中抜きを未然に防ぐためには、契約書で直接取引の禁止を明確に定めることが有効です。禁止する行為や期間、禁止行為を行った場合の対処などを具体的に記載しましょう。
<契約書作成時のポイント>
・人材紹介会社に無断で求職者に連絡すること、直接採用することを禁止する
・求職者への連絡や直接契約を禁止する期間を設定する
・禁止事項に違反した場合の対処を明記する
上記を踏まえて、契約書への記載例を以下に紹介します。
(※実際の契約書では、人材紹介会社を「甲」、求人企業を「乙」、求職者を「丙」のように表記します)
求人企業だけでなく、関連会社を含む中抜きを禁止したい場合は、以下のような文言を追記します。
2. 違約金を設定する
違約金を設定することも、中抜きを防ぐ有効な対策です。中抜きが発覚した際には、追加で違約金を請求する旨を契約書に記載します。
意図的に中抜きを行う企業は、金銭的なデメリットを嫌います。「もしバレたら、紹介手数料以上の額を請求されて損をする」と考えるため、違約金が設定されていると中抜きを実行しづらくなります。
中抜きを完全に排除することはできないにしても、違約金の存在は強力な抑止力になります。
3. 求人企業と求職者に禁止事項について説明する
求人企業と求職者に対して、事前に中抜き行為の禁止を周知することも大切です。禁止事項を明確に伝えることで、不正を抑止する効果が期待できます。
求人企業|契約内容と違約金について十分な説明を行う
求人企業が契約内容をよく理解しておらず、無自覚に中抜きをしてしまうケースもあるため、禁止事項について十分に説明を行うことが必要です。
伝えるべき要点の一覧を以下にまとめました。
・求職者に直接連絡し、雇用契約を結ぶことは契約違反にあたる
・求職者を不採用とした後、一定期間、直接採用することができない
・求職者からの直接応募による採用であっても、中抜きとみなされる
・中抜きが発覚した際は、紹介手数料の支払いや違約金が請求される
どのような行為が禁止されているのか、もし契約に違反したらどうなるのか、具体例を挙げて説明すると伝わりやすくなります。実際に過去に起こったトラブルの事例を紹介するのも良いでしょう。
特に、初めて人材紹介会社を利用する企業は、中抜き行為自体を知らないことも多いため、丁寧に説明を行いましょう。
求職者|中抜きの危険性や対応方法を知ってもらう
中抜きの実態とリスクを周知することで、求職者からの情報提供や通報が増えるでしょう。
人材紹介会社を通さずに企業と求職者が雇用契約を結ぶことは禁止されていることを説明し、もし企業から直接採用を持ちかけられた場合は、すぐに人材紹介会社に相談するよう伝えましょう。
また、直接契約を条件に、採用時の好待遇(ボーナス上乗せ等)を提示しておきながら、入社後にその約束が果たされないトラブルも散見されます。中抜きをするような企業は信用性に欠け、後になって様々なトラブルに見舞われる可能性があることもあわせて伝えておきましょう。
中抜きだけじゃない! 人材紹介業でよくあるトラブル事例

人材紹介業では、中抜きのほかにも様々なトラブルが発生します。
最後に、人材紹介業で発生する代表的なトラブルを紹介します。
求人企業に関する人材紹介トラブル
まずは、求人企業に関するトラブルから見ていきましょう。
求人票と実際との相違
採用時に提示された労働条件と、入社後の待遇が異なることで、求職者から苦情が入るケースです。トラブルの原因は、誤解や認識の差異によるものや企業側の過失など様々です。
このままでは求職者の早期退職につながるため、人材紹介会社と企業間で協議し、対応策を検討します。
内定取り消し
一度出した内定を企業側の都合で取り消すトラブルです。内定取り消しは、求職者に大きなショックを与えます。人材紹介会社に対して不信感が募り、サービスの利用をやめてしまったり、競合他社に乗り換えられたりする可能性もあります。
万が一、内定取り消しが発生した場合は、求職者に対するその後のケアが重要になります。
中抜き行為
本記事のテーマである中抜きのトラブルです。
中抜きが横行すると、人材紹介に費やした時間や労力が無駄になり、人材紹介会社にとって多大な売上損失につながります。
紹介手数料の未払い
企業側による紹介手数料の未払いや、支払い拒否といった問題も発生しています。
紹介手数料が支払われない主な原因として、求人企業の資金繰りの悪化や、紹介した人材に後から重大な問題が発覚したケースなどが挙げられます。
人材紹介業は、採用が成立して初めて収益が発生する成功報酬型のビジネスです。いわゆる後払い方式であるがゆえに、その対価を確実に回収できないリスクがあります。
紹介手数料の返還トラブル
紹介した人材が早期に退職した場合、人材紹介会社は返金規定に基づき、紹介手数料の全額または一部を求人企業に返金します。通常、返金が行われるのは、企業側に過失がない場合に限られます。
上記の事例のように、ハラスメントを訴えて辞めるケースや、労働条件の相違によって退職するケースでは、責任の所在を特定するのが困難です。そのため、紹介手数料の返還を巡って、人材紹介会社と求人企業で見解が分かれ、トラブルになることがあります。
▼人材紹介の返金トラブルについてはこちらの記事で詳しく解説しています。
人材紹介における返金トラブルと対処法|主な事例や予防策、返金規定についても詳しく解説
求職者に関する人材紹介トラブル
ここからは、求職者に関連するトラブルを紹介していきます。
経歴やスキルの詐称
求職者の経歴詐称も、人材紹介においてよくあるトラブルの一つです。経歴やスキルを詐称していたことが入社後に発覚します。実務能力が不足していることで、業務に対応できない、ミスを頻発するといった問題が起こります。
入社後に経歴詐称が発覚した場合、人材紹介会社は求人企業から紹介手数料の返還を求められる可能性があります。基本的には、人材紹介契約の返金規定に則って対応しますが、フリーリプレイスメント(代わりの人材を無料で紹介する制度)を適用するなど、柔軟に解決を図るケースも多く見られます。
直前の面接辞退・内定辞退
直前の辞退やドタキャンは、求人企業に多大な迷惑をかける行為です。求職者本人だけでなく、人材紹介会社の信用にも悪影響を及ぼす可能性があります。
正当な理由がない場合は、後ろめたさや気まずさから、その後音信不通になってしまうケースが多いです。
入社後の早期退職
紹介した人材が自己都合で早期退職した場合、人材紹介会社は求人企業から受け取った紹介手数料を返還しなければなりません。通常、返金額は在籍期間に応じて定められており、「入社後60日未満の退職は紹介手数料の50%を返還」といった規定に従って返金を行います。
人材の早期退職は、売上の損失につながるため、ミスマッチが起きないよう事前のヒアリングを徹底し、入社後は定期的なフォローアップを行うことが大切です。
人材紹介の中抜き行為はバレるが実際に発生している
この記事では、人材紹介の中抜きの手口や対策について解説しました。中抜き行為はバレるリスクが高いにもかかわらず、至る所で発生しています。人材紹介会社には、厳格な対策の実施が求められます。
中には意図せず中抜きをしてしまうケースもあるため、あらかじめ求人企業に対して、禁止行為や違約金について詳しく説明をしておくことが重要です。
この記事の監修者
長沢 ひなた
外資系アパレルで販売・チーム運営を経験後、美容クリニックのカウンセラーに転身。60名中3名のみのトップカウンセラーとして表彰され、マネージャーとして大規模なチームマネジメントも経験する。
「人生単位での変化」を支援したいとの想いからキャリアアドバイザー職へ転身し、入社半年での異例の昇格、1年でリーダーに就任。現在は、キャリアアドバイザー職への転職を専門に、業界構造を熟知した的確な支援を行っている。(▶︎詳しく見る)
基礎知識のおすすめ記事
-
2024/11/20
キャリアアドバイザー(人材紹介営業)で成果を出すコツとは?売上を伸ばす方法を8つのステップで徹底解説
-
2026/01/23
人材業界に向いている人の特徴とは? 仕事内容やスキルを鍛える方法を解説
-

2024/10/16
キャリアアドバイザー(人材紹介営業)職でホワイト企業に転職する方法
-

2024/10/16
キャリアアドバイザー(人材紹介)は未経験からでも転職できる?営業未経験でも応募可能な求人例あり