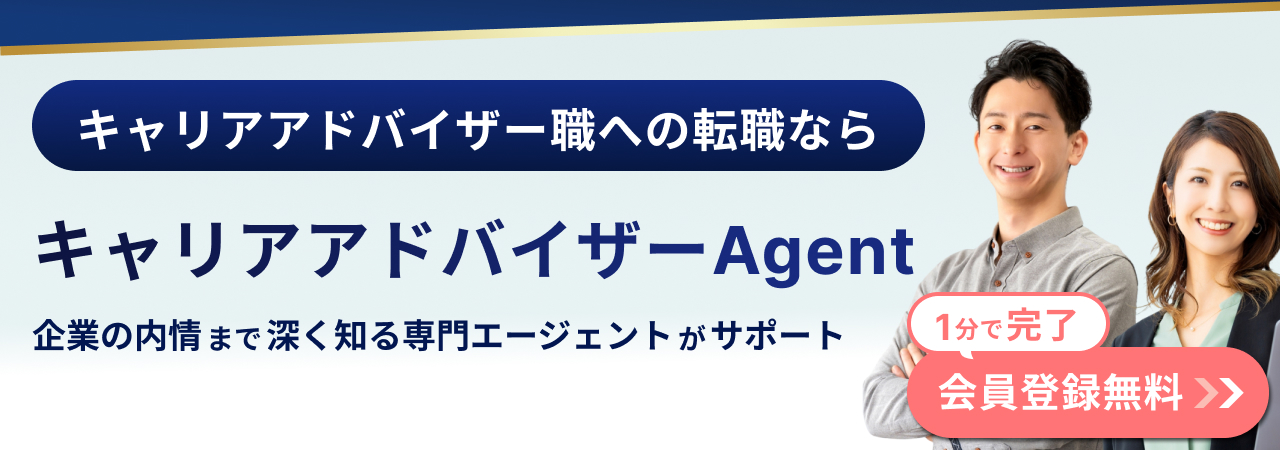2025年7月10日公開
最終更新日:2025年12月9日
人材紹介契約書とは? 必要な記載事項や作成時の注意点、リスク対策を徹底解説!
人材紹介契約書は、企業間のトラブル防止や責任範囲の明確化といった重要な役割を担います。人材紹介事業を円滑に遂行するためには、あらゆるリスクを想定した人材紹介契約書の作成が不可欠です。
本記事では、人材紹介契約書に関する基礎的な知識を分かりやすく解説します。必要な記載事項や作成時の注意点、締結後のトラブル事例とリスク対策など、実務においても役立つ情報をお届けします。
【関連記事】当社が運営する「キャリアアドバイザーAGENT」に関する評価・評判は、『キャリアアドバイザーAgent 求人ナビの評判は?CA転職特化エージェントの実績と口コミを徹底解説』の記事を参照してください。
人材紹介契約書の基本知識
はじめに、人材紹介契約書にまつわる基礎的な知識を解説します。
人材紹介契約書とは
人材紹介契約書とは、人材紹介会社と求人企業の間で締結される契約書のことです。企業が人材紹介会社に対して人材の斡旋を依頼する際に必要となります。契約書の内容には、紹介手数料の発生条件や金額、返金規定、責任の範囲、禁止事項などが明記されます。
平たく言うと、人材紹介契約書は、人材紹介に関する金銭的な取り決めとトラブル時の責任範囲をまとめたもので、求人企業と人材紹介会社が円滑かつ公正に取引を行うための基盤となります。万が一、両者の間で問題が発生した場合は、人材紹介契約書の内容に則って対処するため、慎重に作成することが求められます。
なお、人材紹介契約書は、「職業紹介契約書」や「採用コンサルティング契約書」という名称で作成される場合もあります。
人材紹介業の仕組み
人材紹介業の仕組みについておさらいしておきましょう。
人材紹介業は国の許認可事業で、有料職業紹介事業に分類されます。厚生労働省が定める職業安定法の規定に従う必要があり、人材紹介契約書の記載事項についてもルールが存在します。
人材紹介会社では、人材を採用したい企業と求職者をマッチングし、雇用につなげるサービスを提供します。サービスの主な流れとしては、まず、企業から求人依頼を受けた人材紹介会社が、自社に登録済みの求職者の中から最適な候補者を選定します。その後、書類選考と企業面接を経て、内定、入社手続きへと進みます。この際の雇用契約は、企業と候補者との間で直接結ばれます。
人材紹介会社のビジネスモデルは「成功報酬型」と呼ばれ、企業から支払われる報酬(紹介手数料)で成り立っています。紹介した候補者が企業に入社した時点で報酬が支払われるケースが一般的です。
人材紹介と人材派遣の違い
人材紹介と人材派遣は、どちらも企業に対して人材を紹介するサービスですが、その仕組みは大きく異なります。
人材紹介は、直接雇用の採用支援を行うサービスです。人材紹介会社はあくまでも、企業と求職者の仲介役に過ぎず、雇用契約は企業と求職者の間で結ばれます。
一方、人材派遣は、人材派遣会社が雇用する派遣スタッフを一定の期間、企業に派遣するサービスになります。求職者は人材派遣会社と雇用契約を結び、決められた期間、派遣スタッフとして派遣先企業で働きます。
人材紹介と人材派遣の違いをまとめると、以下のようになります。
人材紹介契約書に必要な記載事項

人材紹介契約書の内容は人材紹介会社ごとに異なりますが、必ず盛り込まなければならない事項が存在します。
ここでは、人材紹介契約書に必要な記載事項を、「職業安定法に基づく義務的な事項」と「その他の記載すべき事項」に分けて解説していきます。
職業安定法に基づく記載事項
職業安定法では、人材紹介会社が企業に対して人材紹介サービスを提供する際に、特定の事項を明示することが義務付けられています。
出典:e-Gov法令検索「職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)」
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141#Mp-Ch_3-Se_1-At_32_13
したがって、人材紹介契約書の作成時には、職業安定法で定められている以下の事項を盛り込む必要があります。
取扱職種の範囲等
紹介する職種の範囲と取り扱う地域について記載します。
職業安定法32条の11第1項では、有料職業紹介事業において、港湾運送業務と建設業務に関する職種を斡旋することが禁止されています。よって、人材紹介契約書には以下のような文言を入れます。
・取扱職種は全職種(港湾運送業務および建設業務を除く)
・取り扱い地域は国内に限る
手数料に関する事項
人材紹介会社が企業から受け取る報酬(紹介手数料)について明記します。後々のトラブルを防ぐためにも、紹介手数料の発生条件や算出方法は明確に規定しておく必要があります。
一般的に、紹介手数料が発生するタイミングは入社日に設定されることが多いです。この場合では、雇用契約の締結と採用者の勤務開始を以って紹介手数料の請求が行われます。
なお、紹介手数料は「採用者の理論年収の30~35%」が相場とされています。
苦情の処理に関する事項
企業および求職者から苦情の申し出があった際の責任者を明記します。通常、厚生労働大臣に届出を行っている職業紹介責任者が、苦情処理の責任者となります。
求人者の情報及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項
情報セキュリティ対策の規定を記載します。人材紹介会社は事業を行う上で、求人者である企業の内部情報や求職者の個人情報を扱うため、それらの情報を適切に管理する責任があります。
返戻金制度に関する事項
返戻金制度とは、紹介した求職者が早期に退職した場合に、人材紹介会社が企業から受け取った紹介手数料の一部または全額を返金する制度のことです。
一般的に、返戻金は「1か月以内の退職で手数料の80%を返還」など、退職時期に応じて段階的に設定されます。就業開始から退職までの期間が長くなるほど、返還する手数料の割合が下がっていきます。
その他の記載すべき事項
職業安定法上、記載が必要な事項を紹介してきましたが、ここからはそれ以外の記載すべき事項について解説していきます。
業務委託の内容
人材紹介会社と企業の間でどのような業務を委託するのかを記載します。具体例を挙げると、「職業安定法に定める求職者の紹介とそれに伴う相談、助言」というような文言を入れます。
直接取引の禁止
人材紹介における直接取引とは、企業が人材紹介会社を介さずに求職者と直接連絡を取り合い、雇用契約を結ぶことを指します。このような不正行為によって、紹介手数料の支払いを免れようとする企業が存在するため、直接取引の禁止の規定が必要です。
人材紹介契約書には、直接取引の禁止に加え、規定に違反した場合の罰則についても明記します。罰則金として、紹介手数料相当の金額を請求するケースも多く見られます。
秘密保持
重要情報の外部流出を防ぐために、守秘義務を課すべき情報の範囲を規定し、人材紹介契約書に記載します。
人材紹介サービスを通じて、人材紹介会社と企業は様々な情報を共有します。時には、営業秘密など、普段表に出ることのない情報に触れることもあるため、秘密保持に関する規定が必要となります。
損害賠償
人材紹介会社が負う責任の範囲を明確に規定します。求職者が入社した後に発生した損害に関しては、人材紹介会社は責任を負わないとするのが一般的です。具体的には、求職者が企業に与えた損害や、求職者が企業から受けた損害、個人間のトラブルなどが該当します。
あらかじめ人材紹介契約書に、人材紹介会社の責任の範囲を明記しておくことで、無用なトラブルやリスクを回避できます。
反社会的勢力の排除
反社会的勢力による悪影響や被害を防ぐための対策として、反社会的勢力の排除に関する規定を明記します。
人材紹介会社と企業の双方が反社会的勢力とは無関係であることや、違反発覚時には直ちに契約を解除できること、その際に損害賠償を請求できることなどを、人材紹介契約書に盛り込みます。
準拠法
準拠法とは、国際的な取引や契約において問題が発生した際に、判断基準として適用される法律のことを指します。分かりやすく言うと、「どの国(地域)の法律を適用するか」ということです。
例えば、外資系企業と人材紹介契約を締結する場合は、準拠法を明確に定める必要があります。「本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈される」というような文言を契約書に記載します。
合意管轄
将来、人材紹介会社と企業との間で紛争が発生した場合に備えて、どこの裁判所で裁判を行うかを事前に定めておきます。当事者間の合意で指定できるのは第一審に限られます。
「〇〇地方裁判所を第一審専属的合意管轄裁判所とする」といった記載の仕方になります。
契約の解除
契約違反が発生した際の解除規定を設けます。これにより、契約条項に違反した場合や、契約解除に値する事実が発覚した場合には、契約期間内であっても契約を打ち切ることが可能となります。契約解除の条件だけでなく、違約金や罰則金についても明記します。
人材紹介契約書の雛形を作成するメリット

人材紹介契約書は、人材紹介サービスを提供するにあたって、取引条件や責任範囲を明文化した法的文書です。人材紹介事業を行う上で必須の書類であり、人材紹介会社と企業との間で人材紹介契約が締結される度に必要となります。
人材紹介契約書は頻繁に用いられるため、あらかじめ雛型を作成しておくと効率的です。雛形を利用すれば、必要箇所のみを書き換えるだけで人材紹介契約書が完成します。作成時間の短縮だけでなく、文書品質の均一化や、内容の不備・抜け漏れの防止など多くのメリットがあります。
人材紹介契約書を作成する際の注意点

ここでは、人材紹介契約書を作成する際に注意すべき3つのポイントを解説します。
配布テンプレートをそのまま使用しない
人材紹介契約書を新たに作成する場合は、Web上で公開されているテンプレートを参考にするのも一つの方法です。初めから必要事項が盛り込まれており、構成も出来上がっているため、一から作成するよりも効率的といえます。
ただし、Web上やダウンロードで取得したテンプレートをそのまま使用するのは避けるべきです。不足している事項があったり、法律改正に対応しておらず古い情報のままになっていたりすることがあるからです。
配布テンプレートは細部まで確認した上で、あくまでも契約書の基礎として活用することをおすすめします。
正確性を重視する
人材紹介契約書は、人材紹介会社と企業の間で締結される、法的な効力を持つ文書です。不備や曖昧な表現があると後々トラブルになるため、正確性が求められます。内容はもちろん、誤字脱字や数字の誤りがないかなど、入念な確認が必要です。
特に注意したいのが数字の記載ミスです。紹介手数料や返金規定に関する数字の誤りは、直接的な金銭的損失につながりかねません。
顧問弁護士に確認を依頼する
人材紹介契約書の雛形を作成したら、必ず顧問弁護士にリーガルチェックを依頼しましょう。人材紹介業は、職業安定法をはじめとする様々な法律の規制を受けます。そのため、契約書に不備があると、法律違反として行政指導や罰則などの法的リスクに晒される可能性があります。
また、Web上で公開されているテンプレートを利用する場合は、そのテンプレートを使用して問題がないか、事前に顧問弁護士に目を通してもらうといいでしょう。内容に不備があったり、法律改正の影響で使用できなくなっていたりするケースもあるため、注意が必要です。
人材紹介契約書を取り交わした後のトラブル事例とリスク対策

人材紹介契約を締結した後に起こり得るトラブルとその対策を紹介します。
トラブル1. 入社後に求職者の経歴詐称が発覚した
求職者が学歴や職歴を偽っていたことが、入社後に発覚するケースです。「採用条件に合わない人材を紹介された」「業務を遂行する能力が不足している」といった理由から、企業が人材紹介会社に返金を求める場合があります。
このようなトラブルが発生した際、人材紹介会社に法的な返金義務があるかどうかは、人材紹介契約書の内容に基づいて判断されます。経歴詐称が発覚した際の責任の所在と返金規定について、あらかじめ明記しておくことが必要です。
トラブル2. 紹介した人材がすぐに退職してしまった
入社後の早期退職もよくあるトラブルです。中には入社から数日で退職してしまうようなケースもあります。
早期退職のリスクに備えて、人材紹介契約書には返金規定を詳細に記載します。下記の例のように、在籍期間に応じて一定の割合で返金を行うのが一般的です。
<記載例>
入社後1か月以内の退職:紹介手数料の80%を返還
入社後1か月~3か月以内の退職:紹介手数料の50%を返還
また、どのような場合に返金を認めるのか、返金事由を明確に規定することも重要です。さもなければ、パワハラや雇用契約違反など企業側に非がある退職においても返金の対象となってしまいます。
「自己都合で退職した場合に限る」「雇用主の責めに帰すべき事由による退職は除く」といった条件を付け加えておくことが必要です。
トラブル3. 求人企業が紹介手数料を支払ってくれない
ごく稀にですが、企業が紹介手数料の支払いを拒むトラブルが発生します。人材紹介契約書に記載された内容について、企業と人材紹介会社の間で認識の齟齬があった場合、支払うべき手数料の金額や計算方法に関して、両者の意見が食い違うことがあります。
このようなトラブルは、人材紹介契約書の内容の曖昧さや、事前の説明不足によって引き起こされます。よって、「紹介手数料の発生条件や算定方法を明記すること」「契約締結にあたって企業と共通認識を持つこと」この2点が重要となります。
また、企業から紹介手数料が支払われない場合のリスク対策として、未払い時の法的対応や、支払い遅延時のペナルティについて契約書に記載することも必要です。
人材紹介事業で扱う書類一覧

ここまで人材紹介契約書について解説してきましたが、人材紹介事業を行う上で必要になる書類は他にもあります。
「求人企業に関連する書類」と「求職者に関連する書類」の2つに分けて紹介します。
求人企業に関連する書類
人材紹介会社と企業の間で扱う書類には、以下のようなものがあります。
・人材紹介契約書
・求人票
・内定通知書
人材紹介契約書は、人材紹介に関する規定をまとめたものです。人材紹介会社と企業間でトラブルにならないよう、責任の範囲や手数料について詳細に定めた文書となります。
求人票は、企業が求める人材要件を集約したものです。ヒアリングの内容をもとに、人材紹介会社側で求人票を作成します。
内定通知書は、内定が決定した際に企業から発行してもらう書類です。内定通知書は基本的に企業側が作成しますが、サービスの一環として人材紹介会社がテンプレートを提供する場合があります。
求職者に関連する書類
人材紹介会社と求職者の間で扱う書類には、以下のようなものがあります。
・ヒアリングシート
・履歴書、職務経歴書
・推薦状
・入社承諾書
ヒアリングシートは、求職者に向けての質問項目をリスト化したものです。マッチングに必要な情報を効率的に収集できます。
求職者が企業に応募する際は、履歴書と職務経歴書に加えて推薦状も提出します。通常、推薦状の作成は担当キャリアアドバイザーが行います。
入社承諾書は、求職者が企業への入社を正式に承諾したことを示す書類です。最終的な意思確認や内定辞退の抑制を主な目的とします。
人材紹介契約を電子契約で締結する企業が増えている

DX促進の流れを受けて、近年では紙の契約書の代わりに電子契約を導入する企業が増えてきています。人材紹介契約においても電子契約が可能で、今後は紙による契約ではなく、電子契約が主流になっていくと推測されます。
人材紹介契約を電子契約で締結する場合は、契約書に条項を追記する必要があります。雛形の修正を忘れないように注意しましょう。
人材紹介契約書の作成は慎重に行おう
この記事では、人材紹介契約書に記載すべき事項や作成時の注意点、締結後のリスク対策について解説しました。人材紹介契約書の役割は非常に重要であり、慎重かつ綿密に作成することが求められます。法改正や電子契約の導入によって内容に修正が必要になることがあるため、常に最新の情報を把握し、適宜反映させるようにしましょう。
この記事の監修者
長沢 ひなた
外資系アパレルで販売・チーム運営を経験後、美容クリニックのカウンセラーに転身。60名中3名のみのトップカウンセラーとして表彰され、マネージャーとして大規模なチームマネジメントも経験する。
「人生単位での変化」を支援したいとの想いからキャリアアドバイザー職へ転身し、入社半年での異例の昇格、1年でリーダーに就任。現在は、キャリアアドバイザー職への転職を専門に、業界構造を熟知した的確な支援を行っている。(▶︎詳しく見る)
基礎知識のおすすめ記事
-
2024/11/20
キャリアアドバイザー(人材紹介営業)で成果を出すコツとは?売上を伸ばす方法を8つのステップで徹底解説
-
2026/01/23
人材業界に向いている人の特徴とは? 仕事内容やスキルを鍛える方法を解説
-

2024/10/16
キャリアアドバイザー(人材紹介営業)職でホワイト企業に転職する方法
-

2024/10/16
キャリアアドバイザー(人材紹介)は未経験からでも転職できる?営業未経験でも応募可能な求人例あり