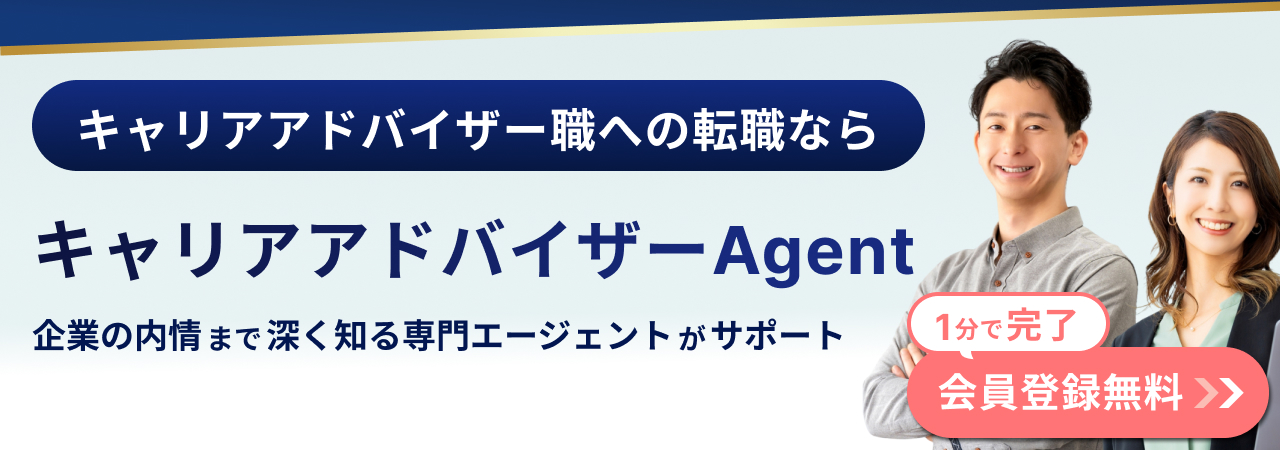2025年7月11日公開
最終更新日:2025年12月10日
人材紹介会社の起業について解説! 許認可の要件や申請の流れ、成功のポイントとは
転職エージェントなどの人材紹介会社を起業する場合、さまざまな要件を満たしたうえで厚生労働大臣へ許認可を申請する必要があります。許可が下りないかぎり、人材紹介会社は開業できません。この記事では、人材紹介会社の起業について詳しく解説します。人材紹介会社を立ち上げたい方に向けて、具体的な許認可の要件や申請の流れを紹介します。
【関連記事】当社が運営する「キャリアアドバイザーAGENT」に関する評価・評判は、『キャリアアドバイザーAgent 求人ナビの評判は?CA転職特化エージェントの実績と口コミを徹底解説』の記事を参照してください。
人材紹介会社の起業に必要な基本情報
人材紹介会社を起業するためには、ビジネスモデルや市場動向、関連する法律への正確な理解が大切です。ここでは、人材紹介会社を立ち上げるうえで知っておきたい基本情報を解説します。
人材紹介のビジネスモデル
人材紹介事業の収益は、求人企業から受け取る成功報酬型の紹介手数料が中心です。一般的に、求人企業が採用した求職者の理論年収×30〜35%が紹介手数料として発生します。たとえば、理論年収600万円の求職者が採用されると、紹介手数料180万〜210万円が人材紹介会社に支払われる仕組みです。紹介手数料は採用が決定してから発生するため、収益の安定化には継続的なマッチングと企業開拓を可能にする体制作りが求められます。
人材紹介の市場動向
厚生労働省が2024年に発表した統計によると、2023年度の人材紹介事業全体の手数料収入は約8,362億円でした(※1)。さらに、2022年度が約7,703億円、2021年度が約6,315億円、2020年度が約5,240億円であるため、人材紹介の市場規模は拡大傾向にあるとわかります(※2)。
市場規模が成長する一方で、倒産件数も増加しています。2025年に株式会社東京商工リサーチが公表したデータによれば、2024年度2月までの11ヶ月間の集計で職業紹介事業の倒産件数は21件発生しました(※3)。年度別で過去最多の倒産件数であり、充分な求職者を確保できずに倒産しているケースが多いようです。
人材紹介事業に関連する法律
人材紹介事業を運営する際は、複数の法令を遵守しなければいけません。もっとも関連性の高い法律が「職業安定法」です。職業安定法には、人材紹介における手数料や運営のルールが規定されています。さらに、求職者に適切な求人を紹介するためには「労働基準法」や「労働契約法」が関わります。その他、性別による雇用の差別を禁止する「男女雇用機会均等法」や、高齢者が安定して働くための「高齢者雇用安定法」などの法律も重要です。各種法律と求人企業が提示する労働条件や雇用契約の内容を照らし合わせて、問題点がないかを確認しましょう。
人材紹介会社の起業にかかる期間
人材紹介会社を立ち上げる際は、「有料職業紹介事業」としての免許が必要です。免許申請の準備から取得までの期間は、およそ3ヶ月間を要します。さらに、免許取得後から開業までは約2ヶ月間がかかります。トータルで約半年間は必要と考えて、余裕を持ってスケジュールを確保しましょう。なお、有料職業紹介事業は次章で詳しく解説します。
※1 厚生労働省「職業紹介事業の事業報告の集計結果について - 令和5年度」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/shoukaishukei.html
※2 厚生労働省「職業紹介事業の事業報告の集計結果について - 令和4年度、令和3年度、令和2年度」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/shoukaishukei.html
※3 株式会社東京商工リサーチ「『人材関連サービス業』の倒産、過去10年で最多 人手不足と過当競争に加え、福利厚生も負担に」
https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1201152_1527.html
人材紹介会社(有料職業紹介事業)の起業に必要な要件

人材紹介会社は、職業安定法が定める「有料職業紹介事業」に該当します。有料職業紹介事業を起業するためには、次の要件をすべて満たしたうえでの免許申請が求められます。
資本金の要件
資産から負債を差し引いた「基準資産額」の要件は、1事業所につき500万円以上が基準です。基準資産額のうち150万円以上は、自己名義の現金・預金でなければいけません。さらに、事業所が2つ以上ある場合は、(事業所数-1)× 60万円を加算した現金・預金の確保が必要です。たとえば、事業所が2つであれば、150万円+60万円=210万円以上を現金・預金で準備します。なお、同じ人材業界の人材派遣事業の基準資産額は2,000万円以上です。そのため、人材材紹介事業の要件は比較的ハードルが低いと言えます。
個人情報管理の要件
人材紹介サービスで扱う個人情報の管理方法について、以下2つの要件が定められています。
・個人情報適正管理規程を設ける
・個人情報を適正に管理するための措置を講じている
個人情報適正管理規程では、個人情報を扱う職員の範囲や当該職員への研修、求職者から個人情報の開示や削除を求められた際の規定といった各種ルールを明記します。一方、個人情報を適正に管理するための措置としては、個人情報を最新かつ正確に保ったり、不正アクセスやデータの改ざん・破壊を防いだりするための対策が必要です。
事業所の要件
事業所の要件は、オフィスの構造についての規定です。次の2つのどちらかの要件を満たすオフィスを用意しましょう。
1.プライバシーを保護する構造(個室やパーティションによる相談スペース など)
2.他の求職者や求人起業との同室を避け、プライバシーを保護する措置(予約制や貸部屋の確保 など)
なお、従来は事務所の面積を「おおむね20㎡以上」とする規定がありましたが、2017年の職業安定法改正によって撤廃されました。現行法では、上記のプライバシーを保護するための設備や措置へと要件が緩和されています。
職業紹介責任者や役員の要件
有料職業紹介事業を開業するためには、「職業紹介責任者」の設置が義務づけられています。職業紹介責任者とは、個人情報の管理や苦情処理、業務の改善、ハローワークとの連絡・調整といった仕事を担う役職です。1つの事業所につき、職業紹介に関わるスタッフ50人に対して1名以上の職業紹介責任者を配置します。例として、スタッフが51人の事業所の場合、2名以上の職業紹介責任者が必要です。また、代表者や役員の規定では、生活根拠の安定や次の欠格事由に該当しないことが挙げられます。
【補足】欠格事由
上記すべての要件を満たしていても、職業安定法第32条による欠格事由に当てはまる場合は有料職業紹介事業の免許を取得できません。主な欠格事由は、以下の通りです。
・拘禁刑以上の刑に処せられ、執行終了または執行猶予が完了した日から5年未満の者
・職業安定法や労働・保健に関する法律に違反して罰金刑に処せられ、執行終了または執行猶予が完了した日から5年未満の者
・自己破産しており、なおかつ破産による制限が解除されていない者
・現役の暴力団員や、暴力団員でなくなった日から5年未満の者
上記の他にもさまざまな欠格事由があるため、開業前に職業安定法を確認しましょう。
人材紹介会社を起業するための許認可申請の流れ
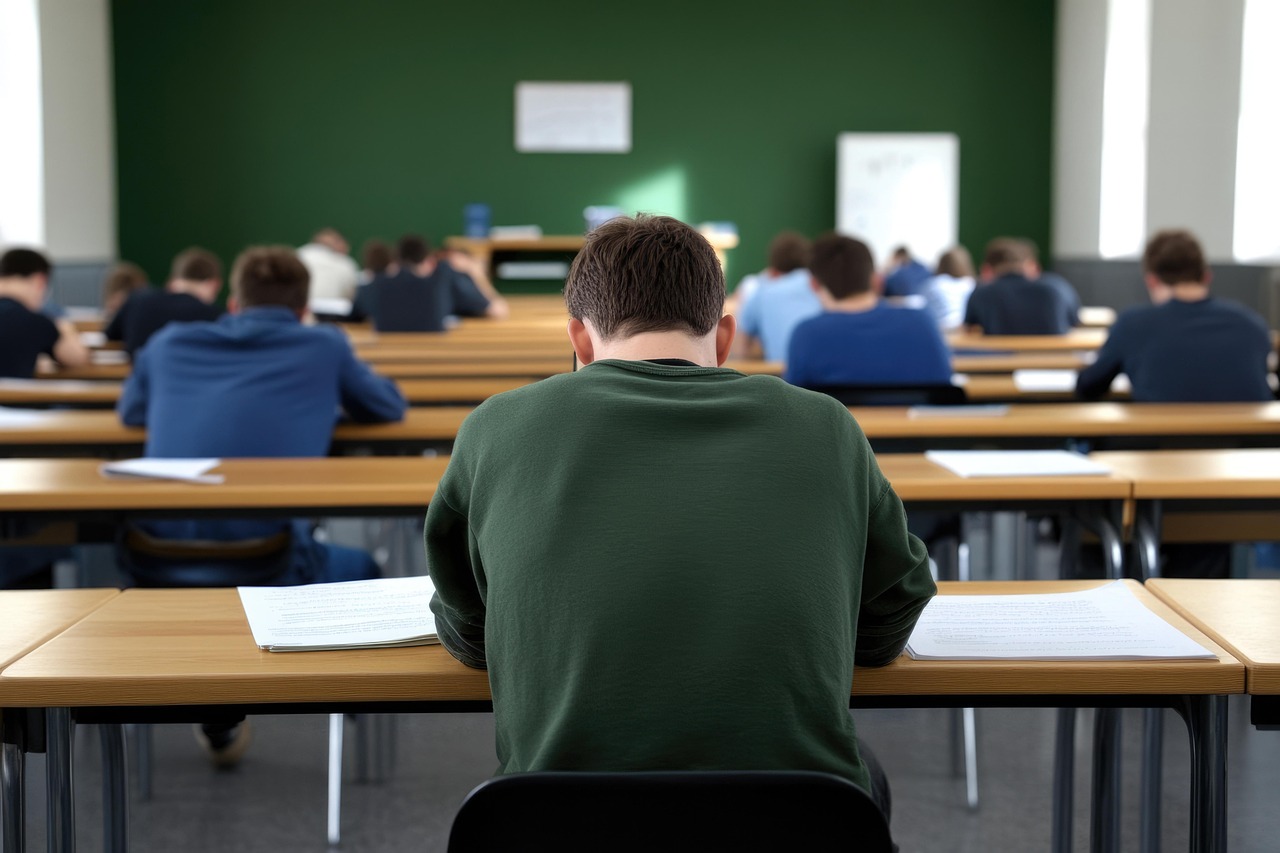
人材紹介会社(有料職業事業)の要件を満たしていると確認できたら、次は厚生労働大臣に許認可を求めます。人材紹介会社を起業するための許認可申請の流れを見ていきましょう。
「職業紹介責任者講習」の受講
人材紹介会社を設立する際は、職業紹介責任者を必ず置かなければなりません。職業紹介責任者に任命されるためには、厚生労働省指定の事業者が実施する「職業紹介責任者講習」の受講が必要です。講習は、全国の主要都市で定期的に開催されています。また、講習会場に赴いて現地参加する講習のほかにオンライン講習もあるため、自社に合う方法で参加しましょう。職業紹介責任者講習で交付される受講証明書は、許認可の申請時に提出します。
職業紹介事業許可申請書の作成
続いて、「職業紹介事業許可申請書」を作成しましょう。人材紹介会社の立ち上げを厚生労働大臣に許可してもらうための書類です。事業所を管轄する都道府県の労働局へ提出します。労働局を経由して、厚生労働大臣から許可をもらう仕組みです。
有料職業紹介事業計画書の作成
「有料職業紹介事業計画書」とは、人材紹介会社の事業計画について記す書類です。事業所名や従業員の人数、資産状況、年間における職業紹介の計画を詳しく記載します。職業紹介事業許可申請書と同様に、管轄の労働局へ提出します。
有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書の作成
「有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書」とは、人材紹介サービスで取り扱う職種や地域をあらかじめ限定するための書類です。職業安定法第5条の6は、一定の法律違反がある求人者をのぞいてすべての申し込みを受理する義務を定めています。それと同時に、職業安定法第32条の12では、取り扱う職種や地域について事前に届け出た場合は範囲を限定できると規定しています。日本全国かつ全職種に対応できる人材紹介サービスは少ないため、「有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書」に自社が取り扱う職種や地域を明記するケースが一般的です。
届出制手数料届出書の作成
人材紹介事業の手数料は、「上限制手数料」と「届出制手数料」の2つの方式があります。上限制手数料とは、採用決定者に支払われた6ヶ月分の賃金の11%を手数料の上限とする方式です。対する届出制手数料とは、事前に届け出た料率の範囲内で手数料を徴収できる方式です。届出制手数料のほうがより高い手数料を得られることから、ほとんどの人材紹介サービスに採用されています。これから立ち上げる人材紹介サービスで届出制手数料を採用する場合、「届出制手数料届出書」に具体的な料率を記載して許可申請と同時に提出しましょう。
必要書類の提出
人材紹介会社の許認可に必要な書類を「申請書類」「添付書類」「手数料・税金」の3つに分けて、下記の一覧表にまとめました。書類を揃えた後は、管轄の労働局へ提出します。
人材紹介会社の起業にかかる費用

人材紹介会社を立ち上げるには、初期費用と運営費用の双方を考慮する必要があります。どのような費用が発生するのか把握して、計画的に資金を調達しましょう。
初期費用
人材紹介会社における初期費用の内訳と目安は、次の通りです。
運営費用
多くの種類がある初期費用に比べて、人材紹介会社の運営費用は限られています。主な固定費は、毎月のオフィスの月額賃料や人件費です。一方、変動費には広告宣伝費やWebサイトの保守運用費、求人データベースの利用料金などの費用が含まれます。いずれも人材紹介会社の規模によって大きく金額が変動します。運営費用を削減したい場合、変動費の見直しが必要です。
人材紹介会社の起業を成功させるポイント

人材紹介サービス市場は成長傾向にありますが、競合他社が多いことから計画性なく立ち上げると早期撤退に追い込まれるリスクが高まります。ここでは、人材紹介会社の起業を成功させる7つのポイントを解説します。
ターゲットと分野の明確化
自社の人材紹介サービスは、どの分野に特化してどのようなターゲットを支援するのかを明確にしましょう。自社ならではの強みを作ることで、競合他社と差別化できます。たとえば、ITエンジニアや介護職、グローバル人材、経営幹部といった専門的に扱う分野を絞り込みましょう。そのうえで、どのような課題やニーズを持つ求人企業と求職者にアプローチするのかも具体的に決めます。また、採用コンサルティングや入社後のフォローなど、付加価値の高いサポート体制の提供も他社との差別化につながります。
市場の調査
ターゲットや求人分野の決定後、対象の市場を調査します。求職者が多い業種や企業の採用ニーズなど、対象市場の求人情報や業界レポートから活用して調べましょう。さらに、競合他社のサービス内容や強み・弱み、利用者の評判、取引先の傾向などの情報を深掘りすれば、自社のサービス設計や差別化戦略に活用できます。市場調査の結果、新規参入が困難と判断した場合はあらめてターゲットや求人分野を考案しましょう。
ビジネスプランの策定
人材紹介サービスの方向性を固めるため、ビジネスプランを立てます。人材紹介ビジネスにおける目標や、目標を達成するための具体的な手段を決めていきましょう。売上目標やサービス内容、人員配置、収益構造、市場や顧客の分析結果など、事業成功に必要な現実的な計画をまとめます。加えて、人材紹介会社の起業で資金調達を考えている場合、助成金の利用や金融機関への融資申請などの計画も立てます。
求職者の集客経路の設計
人材紹介会社を軌道に載せるためには、求職者の集客経路の設計が不可欠です。どれほど求人案件が多くとも、求職者が集まらなければ人材紹介ビジネスは成立しません。自社のWebサイトのSEO(検索エンジン最適化)対策や求人サイトへの広告出稿、リスティング広告、スカウトメール、ビジネスSNSでの情報発信、リファラル営業など、複数のチャネルを組み合わせて求職者との接点を増やしましょう。
求人獲得の営業活動
求職者の確保と同様に、インバウンド営業とアウトバウンド営業による求人獲得も欠かせません。インバウンド営業とは、Webサイトや広告、セミナーなどの経路で企業側から問い合わせを受ける方法です。一方のアウトバウンド営業とは、テレアポや訪問営業、人脈を活用して自社から能動的にアプローチする手法です。立ち上げたばかりの人材紹介会社は知名度が低いため、創業初期はアウトバウンド営業が重要になります。加えて、他社が保有する求人情報を利用できる「求人データベース」を導入すれば、効率的な求人開拓が可能です。
ツールの選定
人材紹介に用いるツールを導入すると、業務の効率化やマッチング精度の向上につながります。代表的なツールに、「ATS(採用管理システム)」があります。ATSとは、求職者や求人情報を一元管理するシステムです。求人票の作成や応募者情報の管理、選考ステータスの更新、面談日程の調整などの作業を1つのシステムで行えます。また、「CRM(顧客管理システム)」では、企業と求職者の情報管理、入金情報、マーケティング支援などの機能を利用できます。自社のサービスや規模、業務内容などの要素から、必要に応じてツール導入を検討しましょう。
コストの試算
人材紹介会社にかかるコストを試算して、計画的に資金を準備しましょう。人材紹介会社は比較的少ない資本金で開業できるからといって、充分に運転資金を確保しないままの立ち上げはおすすめできません。立ち上げ時の資本金や法人登記などの初期費用だけでなく、事業開始後のオフィス賃料や人件費といった運営費用も算出しましょう。ビジネスが軌道に乗るまでの運転資金をしっかり確保することで、倒産のリスクを軽減できます。
人材紹介会社を起業した後の注意点

人材紹介会社を起業した後は、次の5つの注意点に気をつけながら事業を運営しましょう。
集客経路の効果測定を行う
集客経路ごとの効果測定は、必ず行いましょう。求人広告やビジネスSNS、検索エンジンからのWebサイトへの流入、無料相談、セミナーなど、集客経路の違いによって成果は異なります。各経路の効果を測定することで、改善すべきチャネルを可視化できます。また、客観的に検証するためにはKPI設定も大切です。内定承諾数や面接通過数、面接設定数、スカウトメールの開封数といった数値で測れるKPIがあれば、データにもとづいて改善策を立案できます。
従業員を育成する
人材紹介事業を成長させるためには、従業員のスキルアップが重要です。CA(キャリアアドバイザー)やRA(リクルーティングアドバイザー)の育成制度を構築して、個人の業務経験の違いにかかわらずメンバー全体のスキルを高めましょう。研修プログラムを考案する際は、求人企業の業界知識や関連法律への理解、ヒアリング能力など、従業員へ求めるスキルを定義して反映させます。また、成功事例およびノウハウの共有やトークスクリプトの活用も効果的です。
状況に応じて集客方法を変更する
立ち上げ当初の集客方法にこだわりすぎず、定期的に施策の効果を見直して柔軟に変更しましょう。ビジネスのトレンドや顧客のニーズが変わるにつれて、これまで効果があった集客方法の成長が鈍化するケースはよくあります。状況に応じて集客方法を柔軟に切り替えることで、安定して求職者に訴求し続けられます。環境の変化に慌てて新たな集客チャネルを用意するのではなく、あらかじめ複数の集客チャネルを運用していればスムーズに対処できるでしょう。
免許の更新を忘れない
有料職業紹介事業の免許は有効期限があるため、更新が必要です。新規取得した場合の有効期間は3年間です。「職業紹介事業許可有効期間更新申請書」を作成して、管轄の労働局へ提出しましょう。また、1つの事業所につき、手数料として18,000円の収入印紙も納めます。更新後の有効期間は、以降5年ごとです。注意点として、更新申請の受理日から5年以内に職業紹介責任者講習会を受講していない場合、免許の更新は認められません。更新申請までに、あらためて職業紹介責任者講習を受講しましょう。
事業報告を行う
職業安定法第32条の16によって、有料職業紹介事業は毎年4月30日までの事業報告が義務づけられています。人材紹介の実績の有無にかかわらず必要なため、開業したばかりで紹介実績がない場合でも必ず行いましょう。職業紹介事業報告書に活動状況や収入状況を詳しく記載して、管轄の労働局へ4月1日から4月30日の間に提出します。
事前に戦略を立てて人材紹介会社の起業を成功させよう
人材紹介会社を起業する際は、自社サービスが狙うべきターゲットや求人分野などの戦略を立てましょう。求職者を確保するための集客経路は、求人広告やオウンドメディアなどの複数経路の活用がおすすめです。また、開業当初の求人獲得は訪問やテレアポなどのアウトバウンド営業が中心になるでしょう。合わせて求人データベースも利用すると、他社が保有する求人情報の紹介が可能になります。人材紹介会社の起業後は免許の更新や事業報告が必要になるので、忘れずに行いましょう。
この記事の監修者
長沢 ひなた
外資系アパレルで販売・チーム運営を経験後、美容クリニックのカウンセラーに転身。60名中3名のみのトップカウンセラーとして表彰され、マネージャーとして大規模なチームマネジメントも経験する。
「人生単位での変化」を支援したいとの想いからキャリアアドバイザー職へ転身し、入社半年での異例の昇格、1年でリーダーに就任。現在は、キャリアアドバイザー職への転職を専門に、業界構造を熟知した的確な支援を行っている。(▶︎詳しく見る)
基礎知識のおすすめ記事
-
2024/11/20
キャリアアドバイザー(人材紹介営業)で成果を出すコツとは?売上を伸ばす方法を8つのステップで徹底解説
-
2026/01/23
人材業界に向いている人の特徴とは? 仕事内容やスキルを鍛える方法を解説
-

2024/10/16
キャリアアドバイザー(人材紹介営業)職でホワイト企業に転職する方法
-

2024/10/16
キャリアアドバイザー(人材紹介)は未経験からでも転職できる?営業未経験でも応募可能な求人例あり