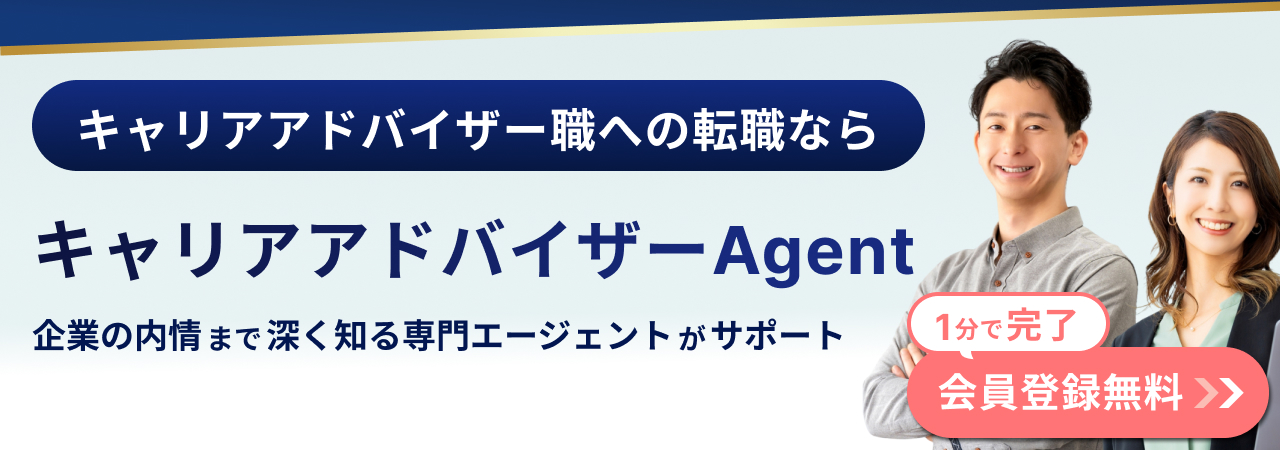2025年6月2日公開
最終更新日:2025年12月9日
人材紹介業で免許がないとどうなる? 免許が必要な理由、違法性がある事例などわかりやすく解説
人材紹介業の業務の中で、免許が必要なもの、そうでないものが存在します。人材紹介業で免許がないとどのような問題があるのでしょうか。本記事では、免許が必要な理由や、免許が必要な事例、免許が不要な事例について解説します。
【関連記事】当社が運営する「キャリアアドバイザーAgent求人ナビの転職支援サービス」の特徴や登録のメリットについてご紹介。
人材紹介業は免許が必要?
人材紹介業を行うには、厚生労働大臣の許可(いわゆる免許)が必要です。これは、「職業安定法」という法律により義務付けられています。しかし、人材紹介業を始めたいと考える多くの方が最初に抱く疑問が、「免許は本当に必要なのか?」という点です。この記事では、この疑問に対する答えとともに、詳しく解説していきます。
有料職業紹介事業と無料職業紹介事業
人材紹介業に免許が必要かどうかは、事業の形態によって異なります。人材紹介業には、「有料職業紹介事業」と「無料職業紹介事業」の2種類があります。有料職業紹介事業とは、サービスの対価として手数料を受け取る、一般的な人材紹介会社のことを指します。具体的には、求職者の就職が決まった際に、紹介先の企業から手数料を受け取る仕組みです。この事業を行うには、「有料職業紹介事業許可」を取得することが法的に義務付けられており、許可を得ずに事業を行った場合は、職業安定法違反となります。
一方、無料職業紹介とは、手数料を受け取らずに職業紹介を行うものです。例えば、学校や自治体、NPO法人などの団体が主に行っているのがこれにあたります。無料職業紹介を行う場合は、厚生労働大臣の許可ではなく「届出」のみで事業を開始できます。ただし、「完全無料」であることが絶対条件であり、わずかでも金銭の授受がある場合は、有料職業紹介事業に該当します。
営利・非営利を問わず、「職業紹介」という行為そのものが法的に規制されています。そのため「報酬を受け取らないから問題ない」と自己判断するのは危険です。事業の内容によっては、法令違反に該当する可能性があるため、十分な注意が必要です。もし、「自分の行っていることに許可が必要なのでは?」と不安に感じた場合は、迷わず労働局に相談しましょう。
免許(許認可)がないとどうなる?
人材紹介業を免許なしで行うと、法律違反となり、罰則の対象となります。具体的には、無許可で職業紹介を行った場合、「職業安定法」に基づき、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。それだけでなく、行政指導や事業停止命令を受ける可能性もあり、求職者および企業からの信用を大きく損なう結果となるでしょう。また、無料職業紹介事業についても、届出を提出せずに行った場合は処罰の対象となります。
継続的に求職者と企業をマッチングし、採用に至らせた場合は、「職業紹介」とみなされるリスクが高く、免許なしで行うのは非常に危険です。特に、副業や個人で紹介ビジネスを行おうとするケースでは、無意識のうちに法令違反となることも少なくありません。「知らなかった」では済まされないため、事業を始める前に必ず制度を確認し、適切な手続きを踏むようにしましょう。
人材紹介業に免許が必要な理由

人材紹介業に免許が必要な理由は、求職者と求人企業の双方を保護するためです。人材紹介は、人材と企業を結びつける重要なサービスであり、適切な知識や運営体制が求められます。仮に運営が適切でない場合、以下のようなさまざまなトラブルが発生するリスクがあります。
- 求職者の個人情報の漏洩
- 不適切なマッチングによる採用
- 入社後の労働トラブル
こうしたリスクを防ぐため、厚生労働省は「職業安定法」に基づき、紹介業を営む事業者に対して遵守すべき要件を定め、審査を行ったうえで免許を付与する仕組みを設けています。この仕組みによって、無許可で人材紹介業を行った場合、利用者に損害が生じても適切な補償体制が整っていないため、被害が拡大しやすくなります。
法令に基づいた運営を行うことは、社会的信用を確保し、安心・安全なサービスを提供するうえで不可欠です。
無許可の人材紹介の事例

本来は許可が必要であるにもかかわらず、無許可で実施されている事例は少なくありません。これは、本人が自覚のないまま職業安定法に違反している場合が多いです。具体的にどのような事例があり、どこが違法行為に該当するのか、そのポイントを解説します。
SNS上での人材紹介
X(旧Twitter)やInstagramなどのSNS上にて、知人やフォロワーに仕事を紹介する投稿が見受けられます。よくある例としては、求職者向けに「この企業が人材を募集しています。希望者はDMください」などと投稿を送ることです。これは一見情報共有のように見えますが、内容や継続性によっては職業安定法上の「職業紹介」とみなされる場合があります。
もし紹介に対して報酬や謝礼を受け取る場合は、完全に有料職業紹介と見なされる可能性が高く、無許可であれば違法行為となります。また、SNSで収集した求職者の個人情報を企業に伝えることも、個人情報保護法の観点から問題となる場合があります。本人は気軽な気持ちで行っていても、法的責任を問われることがあるため、注意が必要です。
医師のあっせん
医師や看護師などの医療従事者を無許可であっせんする行為は、一般の職業紹介以上に重大な法的問題を含みます。実際に医療関係者を対象にした紹介サービスを免許なしで行い、職業安定法違反で逮捕された事例も存在します。医師の紹介は専門性が高く、誤ったマッチングは患者の安全にも関わるため、行政は特に厳しく監視しています。報酬の有無に関わらず、第三者が医師と病院をつなぐ行為そのものが職業紹介と判断されるケースが多く、免許なしで行うことは絶対に避けなければなりません。
相手の健康を考え善意で行ったとしても、医療従事者の紹介に関わる場合は、必ず有料職業紹介事業の許可を取得し、法令を順守した形で行うことが重要です。
有料人材紹介業で起こりやすい違法行為
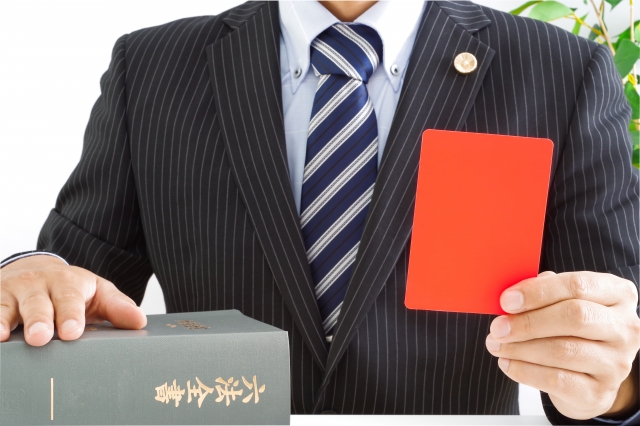
有料人材紹介業は免許が必須ですが、具体的にどのような業務が違法行為とみなされるのでしょうか。ここでは、有料人材紹介業で特に注意すべき違法行為について、その事例を紹介します。
免許・許認可を持たない個人・法人による人材紹介
人材紹介業を行うには免許が必要であるにもかかわらず、実際には免許を持たない個人や法人による人材紹介が行われているケースがあります。たとえば、フリーランスの紹介業者が「知り合いの企業に人材を紹介し、報酬を受け取る」といった場合も、報酬を受け取っている以上、無許可であれば違法行為に該当します。
このような無許可の人材紹介は、トラブルが発生した際に責任の所在が不明確となり、求職者・求人企業の双方に不利益をもたらす可能性があります。また、将来的に罰則を受けるリスクも伴うため、十分な注意が必要です。
業務委託として人材紹介業の運営を委託する
自社が職業紹介の免許を取得していないため、免許を保有する他社から名義だけを借りて、実質的に紹介業を行う業者も存在します。一見すると「業務委託」の形式に見えるものの、実態として紹介業務を自社主導で運営している場合には、違法と判断される可能性があります。
人材紹介業では、紹介元となる事業者自身が免許を保有し、責任を持って求職者と求人企業をマッチングすることが求められます。名義貸しや、責任の所在が曖昧な委託関係では、トラブル発生時に適切な対応ができず、行政処分の対象となることもあります。外注や業務提携を検討する際は、紹介行為の主体が誰であるかを明確にし、法的に適正な形で体制を構築することが重要です。
中抜き行為
中抜き行為とは、求人企業から受け取った紹介手数料の一部を、不適切に第三者や求職者へ還元する行為を指します。たとえば、企業から受け取った報酬の一部を紹介者にキックバックしたり、求職者に「成功報酬」として現金を渡したりすることは、職業安定法や労働者派遣法に抵触する可能性があります。
中抜き行為は、一見すると求職者への還元のように見えますが、実際には契約の透明性を損ね、業界全体の健全性を脅かす問題行為です。報酬の二重取りなど、紹介手数料に関するトラブルに発展しやすく、企業側の信頼を失う原因にもなりかねません。
人材紹介業の免許が必要な事例

人材紹介業を行うには免許が必要ですが、実際には免許が必要かどうか気づかず人材紹介を行い、職業紹介とみなされてしまう事例は多いです。これを防ぐためには、事前に何の業務において免許を必要なのか知っておかなければいけません。ここでは、人材紹介業において免許が必要な事例として、以下の3つを解説します。
- 人材紹介をして報酬を受け取る
- 業務委託の人材を紹介する
- 人材紹介はするが手数料は受け取らない
この3つの事例において、どの部分が違法行為にあたるのか、解説します。
人材紹介をして報酬を受け取る
免許が必要な事例1つ目は、企業に人材を紹介し、その対価として報酬を受け取る行為です。これは「有料職業紹介事業」に当たります。たとえ一度きりであっても、報酬を受け取った時点で職業安定法の対象となり、免許がなければ違法とみなされます。
このとき、報酬の形態はあらゆる利益が対象となります。例えば現金以外にも商品券や紹介手数料、物品の提供なども含みます。また、紹介相手が個人・法人を問わず、知人やネット経由でも同様です。「人材を紹介する代わりに謝礼をもらう」といった行為そのものに違法リスクがあります。特にSNSで無意識のうちに人材紹介を行って謝礼をもらい、法令違反になるケースが多いです。
業務委託の人材を紹介する
フリーランスや個人事業主など業務委託の契約で働く人材を紹介する場合も、職業紹介とみなされる可能性があります。これは、「雇用契約の成立をあっせんする行為」全般が職業安定法の規制対象となっているためで、業務委託や請負契約も例外ではありません。
例えば、継続的に企業に委託人材を紹介し、報酬を受け取っている場合は、有料職業紹介とみなされます。無許可で行うと労働局からの指導や処分の対象となることがあり、紹介先の企業にも迷惑がかかります。「正社員でなければ紹介にあたらない」と誤解しないように注意しましょう。
人材紹介はするが手数料は受け取らない
「報酬を受け取るから違法になるのであり、報酬を受けとらなければ免許なしでも問題ない」と思われるかもしれませんが、これは誤りです。仮に手数料や謝礼を一切受け取っていなくても、継続的に何度も人材を企業に紹介すると、その行為は「無料職業紹介事業」にあたります。無料職業紹介事業は厚生労働省への届け出が必要になるため、届け出をしていない場合は違法行為とみなされます。
学校、NPO、地域団体などが行う無料の紹介でも、法的には適正な手続きが求められます。個人の好意やボランティア的な紹介であっても、組織的な活動と判断されれば、法令違反になる可能性があります。たとえ無償であっても、人と企業を結ぶ行為には慎重な対応が必要です。
人材紹介業で免許が不要な事例

人材と企業をつなぐ活動すべてが免許の対象になるわけではありません。実際には、人材紹介業務の中でも職業安定法上の「職業紹介」に該当せず、免許が不要なケースが存在します。その代表的なものが「リファラル採用」と「求人マッチングサイト」です。これらは求職者と企業の間を直接的につなぐのではなく、情報提供や自己応募を前提とした仕組みであるため、法律上は紹介行為に該当しません。ここでは、特に注目されている2つの手法について、なぜ免許が不要とされているのか、解説します。
リファラル採用
リファラル採用とは、社員や知人が自社の求人に適した候補者を紹介する仕組みのことです。これは一般的に企業内で行われます。紹介された人材が採用された場合、紹介者にインセンティブが支払われることもあります。そのため、紹介者も採用された人もメリットが得られるおすすめの人材紹介方法といえるでしょう。また原則として、リファラル採用は職業安定法の「職業紹介」には該当しません。なぜなら、リファラル採用が業務として行われておらず、組織内の内部制度の一環と見なされるためです。
ただし、企業外の第三者が継続的に紹介を行い、報酬を受け取る場合は、職業紹介と判断される可能性があります。
求人マッチングサイト
求人マッチングサイトは、求職者と求人企業の情報を一覧にまとめWeb上で掲載・公開し、ユーザー自身が応募や問い合わせを行う仕組みです。マッチングサイトの運営者が個別に紹介や斡旋を行わない限り、職業紹介には該当しません。そのため免許がなくとも問題ありません。
代表例としては求人情報サイトや副業マッチングプラットフォームなどが挙げられます。企業と求職者の間に直接的な関与をせず、掲載のみであれば、免許なしにサイト運営できます。ただし、求職者と求人企業の間に立って面談を設定したり、選考に関与し働きかけを行ったりすると、「紹介行為」とみなされる可能性があります。サービスの範囲には十分注意しましょう。
人材紹介業の免許なしに求人マッチングサービスをする場合の注意点

求人マッチングサービスの運営は免許がなくとも運営できますが、注意しておくべき点がいくつかあります。これを押さえておかないと「紹介行為」とみなされ違反と判断される可能性があるため、必ずご確認ください。
求人情報の作成・加筆はしてはいけない
免許を取得せずに求人マッチングサイトを運営する場合、掲載する求人情報の「作成」や「加筆・修正」を行ってはいけません。これは、求人内容に対して運営者が介入し、マッチング精度を高めようとする行為が、「職業紹介」に該当すると見なされる可能性があるためです。特に、求職者に対して「この求人が合っている」といったコメントや推薦を加える行為は、紹介の意思があると判断されるおそれがあります。
求人マッチングサイトはあくまでも、企業が自ら作成した原文をそのまま登録・掲載する「情報掲示板」としての立場を維持しなければなりません。たとえ編集の意図が善意であっても、法律上の基準は厳格に定められているため、注意が必要です。
求人企業と求職者のやりとりの内容に関与してはいけない
求人マッチングサービスの運営者は、求人企業と求職者との間で行われるやり取りに直接関与することが禁止されています。例えば、以下のような行為は「職業紹介」に該当すると判断される可能性があります。
- 求人応募後の面談日程調整や条件交渉の代行
- 採用選考への関与
- 採用結果(合否)の連絡
法的には、求職者と求人企業が直接やり取りを行う状態を保っている状態だと、職業紹介とはみなされないとされています。運営者は、あくまで応募ボタンや問い合わせフォームなどを通じて両者をつなぐ役割にとどめ、それ以降の連絡には一切関与しないというルールを徹底することが重要です。
人材紹介業の免許を取得する方法

人材紹介業を始めるのに必要となる免許「有料職業紹介事業許可」を取得するには、各都道府県の労働局を通じて申請を行い、審査を経て許可を得る必要があります。まず申請を行うための要件として、以下の3点が挙げられます。
- 専用の事業所を設置
- 専任の職業紹介責任者を配置
- 財務要件を満たす
また、申請時には、事業計画書や社内規程、個人情報管理体制の説明資料等を記載し、提出する必要があります。申請に必要な資料は各都道府県の労働局ホームページからダウンロードできるので、活用してみてください。
▼人材紹介業の免許を取得するために必要な書類や申請の流れ、関連情報については、以下の記事でも詳しく解説しています。そちらもあわせて御覧ください。
人材紹介(有料職業紹介)業の免許(許認可)を取得するには? 要件や費用、申請方法を解説
人材紹介業は免許がないとリスクがある
人材紹介業を行うには、免許(有料職業紹介事業許可)が必要です。免許を取得せずに業務を行った場合、法律違反となり、罰則の対象となるだけでなく、求職者や求人企業からの信用を失い、これまで築いてきた事業基盤を失う可能性があります。特に、報酬の受け取りや継続的・反復的な紹介行為は、免許が必要な業務とみなされる可能性が高いため、十分な注意が必要です。
一方で、リファラル採用や求人情報の掲載のみであれば、免許がなくても合法的に実施可能です。ただし、求人情報の加筆や、応募者とのやりとりを仲介するような行為は、人材紹介に該当すると判断されるおそれがあるため、慎重な対応が求められます。
人材ビジネスの経営を始めたいと考えている場合は、まず制度を正しく理解し、必要に応じて免許の取得を視野に入れながら準備を進めましょう。
この記事の監修者
長沢 ひなた
外資系アパレルで販売・チーム運営を経験後、美容クリニックのカウンセラーに転身。60名中3名のみのトップカウンセラーとして表彰され、マネージャーとして大規模なチームマネジメントも経験する。
「人生単位での変化」を支援したいとの想いからキャリアアドバイザー職へ転身し、入社半年での異例の昇格、1年でリーダーに就任。現在は、キャリアアドバイザー職への転職を専門に、業界構造を熟知した的確な支援を行っている。(▶︎詳しく見る)
基礎知識のおすすめ記事
-
2024/11/20
キャリアアドバイザー(人材紹介営業)で成果を出すコツとは?売上を伸ばす方法を8つのステップで徹底解説
-
2026/01/23
人材業界に向いている人の特徴とは? 仕事内容やスキルを鍛える方法を解説
-

2024/10/16
キャリアアドバイザー(人材紹介営業)職でホワイト企業に転職する方法
-

2024/10/16
キャリアアドバイザー(人材紹介)は未経験からでも転職できる?営業未経験でも応募可能な求人例あり