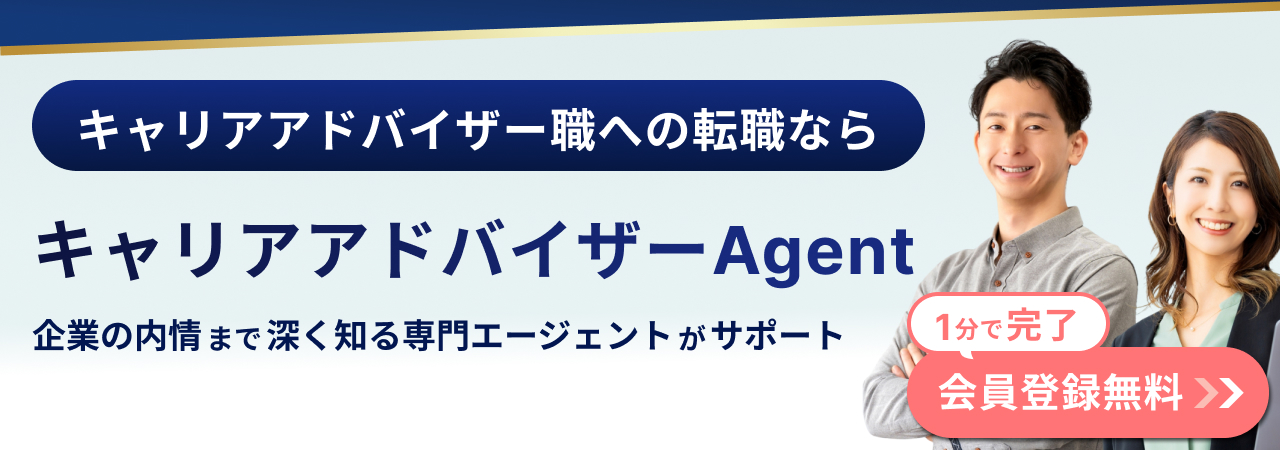2025年4月19日公開
最終更新日:2025年12月9日
人材紹介の利益率は? 事業の収益構造や売上・費用、人材派遣との違いを徹底解説
近年、転職エージェントなどの人材紹介会社が数多く登場しています。起業が相次ぐ理由の1つとして、人材紹介事業の利益率の高さが挙げられます。人材紹介事業の利益率はなぜ高いのでしょうか。この記事では、人材紹介の利益率について詳しく解説します。収益構造や具体的な売上・費用の内訳から説明するので、ご興味のある方はぜひご覧ください。
【関連記事】当社が運営する「キャリアアドバイザーAGENT」に関する評価・評判は、『キャリアアドバイザーAgent 求人ナビの評判は?CA転職特化エージェントの実績と口コミを徹底解説』の記事を参照してください。
人材紹介事業の収益構造
人材紹介の利益率について正しく理解するため、まずは人材紹介事業の収益構造から確認しましょう。そもそも人材紹介事業とは、新たな人材を求める企業と就職・転職したい求職者をマッチングするビジネスです。人材紹介サービスは企業と求職者の双方へヒアリングを行い、求める人材の要件や転職先の希望条件を固めます。マッチ度の高い求人企業を求職者へ紹介して、選考のサポートを行います。最終的に求職者の採用が決まると、採用した求人企業から「紹介手数料」を受け取れる仕組みです。
人材紹介事業の収益は、紹介手数料で成り立っています。人材紹介サービスによって異なりますが、理論年収×30〜35%が紹介手数料の目安です。ほとんどの場合、成功報酬型の料金体系であるため、求職者を紹介しても採用されなければ紹介手数料は支払われません。ただし、「着手金(リテーナーフィー)」の制度を採用している場合、採用結果にかかわらず紹介手数料の一部が事前に支払われます。求職者の採用決定後、残りの紹介手数料がまとめて支払われる仕組みです。
厚生労働大臣の許可が必要な「有料職業紹介事業」
人材紹介サービスは、「有料職業紹介事業」に該当する事業です。有料職業紹介事業は、職業安定法により手数料や情報開示などのルールが厳密に定められています。新たに事業を立ち上げる際は、厚生労働大臣による許可が必要です。また、「港湾運送業務」および「建設業務」の人材紹介は認められていません。一方、手数料などの報酬を受け取らずに人材紹介を行う場合は「無料職業紹介事業」と呼ばれます。たとえば、ハローワーク(公共職業安定所)は無料職業紹介事業に当てはまります。
人材紹介事業の利益率
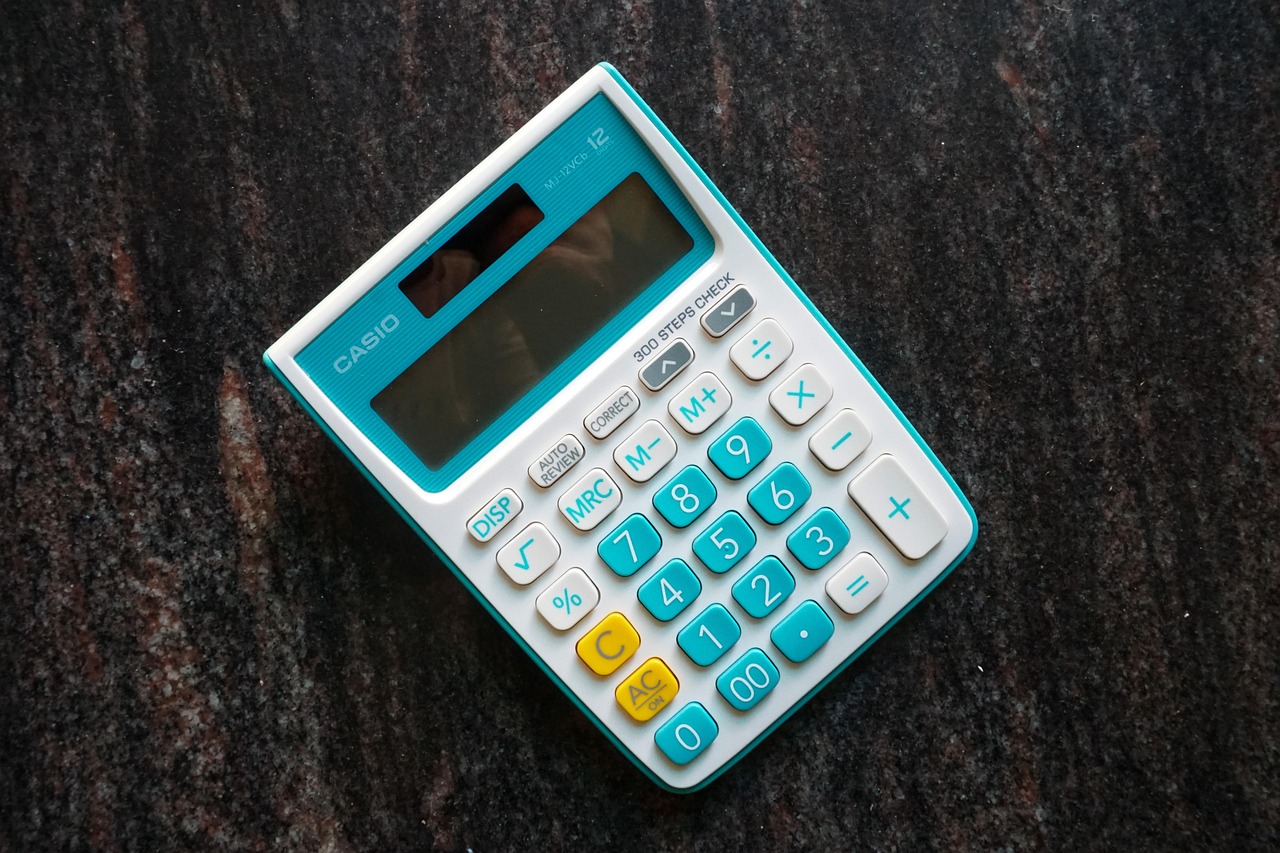
一般的に、人材紹介事業の利益率(営業利益率)は20%前後です。業種によって差異があるものの、利益率が5〜10%であれば標準または優良な事業とされています。10%を超えると非常に収益性が高い事業であるため、人材紹介事業は数ある業界の中でもとりわけ利益の大きいビジネスと言えます。
利益率(営業利益率)の考え方
売上高のうち、営業利益が占める割合が利益率(営業利益率)です。元となる営業利益は、以下の計算式で算出します。
■営業利益の計算式
売上高 - 売上原価 - 販管費 = 営業利益
売上原価とは、原材料の仕入れや商品・サービスの製造および提供にかかる費用です。販管費とは、販売費と一般管理費を合わせた略称です。販売費は商品・サービスの販売に必要な費用で、一般管理費は会社全体の管理によって生じる費用を指します。販管費には、人件費や広告宣伝費、オフィスの賃料といった費用が含まれます。
人材紹介事業の利益率が高い理由
人材紹介は、物質的な形のない無形サービスです。さらに、サービスを提供するための直接的なコストもありません。そのため、原材料の仕入れや製造といった「売上原価」が発生しません。人材紹介事業の営業利益は、売上原価を除外して次のように計算します。
■人材紹介事業の営業利益の計算式
売上高 - 販管費(人件費 + 広告宣伝費 + その他関連費用)= 人材紹介事業の営業利益
人材紹介事業の売上高は、ほとんどが顧客である求人企業から得る紹介手数料で構成されています。紹介手数料を得るためにかかる費用が少ないことからことから、高い利益率を実現しています。
人材紹介事業の売上

続いて、人材紹介事業の売上について説明します。具体的な収益源や売上の計算方法について見ていきましょう。
紹介手数料が売上の中心
人材紹介事業の売上は、人材紹介手数料が中心になります。求職者の採用が1件確定するごとに紹介手数料が発生するため、収益性が高いビジネスです。なお、ヘッドハンティングによって人材を獲得する場合、着手金として紹介手数料の一部を事前に得るケースもあります。ヘッドハンティングおよび着手金は、ハイクラス人材を対象とする人材紹介サービス向けの仕組みです。
多くの人材紹介事業は、「届出制手数料」の仕組みによって紹介手数料を得ています。届出制手数料とは、厚生労働大臣に届け出た数値の範囲で手数料の料率を決められる制度です。最大50%の料率を設定できますが、目安は30〜35%です。届出制手数料のほかに「上限制手数料」の制度もあるものの、採用決定者に支払われた6ヶ月分の賃金の11%が上限になります。届出制手数料よりも利益率が低いため、ほとんど使われていません。
売上の計算方法
紹介手数料の金額は、求職者の採用1件あたり理論年収×30〜35%の設定が一般的です。理論年収とは、採用された求職者の年収の推定額です。例として理論年収400万円、料率30%の場合、紹介手数料は120万円になります。
■理論年収400万円、料率30%の計算例
理論年収400万円 × 30% = 紹介手数料120万円
このように、人材紹介事業は1件につき高額の売上が発生します。また、売上高は以下のように計算します。
■人材紹介事業の売上高の計算式
採用者の人数 × 平均単(紹介手数料の平均値)= 売上高
たとえば、1ヶ月間の採用決定人数が5名、平均単価が150万円であれば月次売上高は750万円となります。
人材紹介事業に必要な費用

人材紹介事業に必要な費用は、大きく分けて「初期費用(イニシャルコスト)」と「運用費用(ランニングコスト)」の2種類です。それぞれの費用の内訳を紹介します。
初期費用(イニシャルコスト)
人材紹介事業の初期費用(イニシャルコスト)は、「会社設立費用」「免許申請手数料」「資本金」の3つです。
会社設立費用
会社設立費用とは、法人を新たに立ち上げる際に発生する諸経費です。具体的な経費は、以下の一覧表をご確認ください。
上記の諸経費は、株式会社または合同会社といった会社の形態によって有無や料金が異なります。株式会社よりも合同会社のほうが会社設立費用は安くなります。
免許申請費用
人材紹介事業を設立する際は、「職業紹介責任者講習」を受講した職業紹介責任者を1つの事業所に1名配置する義務があります。職業紹介責任者を適切に配置することで、人材紹介事業の免許を取得するための「職業紹介事業許可申請書」を労働局へ提出できます。労働局を経由して厚生労働大臣から許可を得ると、職業紹介事業を開業できる仕組みです。免許申請費用として、「登録免許税」と「収入印紙代」の2つが徴収されます。また、事前に受講する職業紹介責任者講習の受講料金も生じます。
資本金
会社を設立するための法人登記を行う際は、資本金が必要です。2006年5月に施行された会社法により、資本金1円でも会社の設立が可能です。しかし、人材紹介事業は資産から負債を差し引いた「基準資産額」に固有のルールが定められています。1つの事業所につき500万円以上の基準資産額があれば、人材紹介事業の開業を認められます。金融機関からの融資や借入は負債となるため、自己資金のみで500万円以上の資本金を準備しなくてはいけません。加えて、基準資産額のうち、150万円は現預金による確保が求められます。
運用費用(ランニングコスト)
人材紹介事業の利益率の算出に関わる主なコストは、運用費用(ランニングコスト)です。運用費用は、「固定費」と「変動費」の2種類に分かれます。
固定費
人材紹介事業の固定費は、オフィス代と人件費が大半を占めます。人材紹介事業を開業するためには、「パーティションや個室によるプライバシーの保護」「利用者同士が同室にならない構造」といった事業所の要件があります。要件さえ満たしていれば、自社ビルや賃貸オフィスのほか、レンタルオフィスおよびシェアオフィスなどの形態でも開業可能です。
オフィス代は要件を満たせば費用を圧縮しやすい一方で、人件費は固定費の中でも大きくなりやすい費用と言えます。求職者に対応するCA(キャリアアドバイザー)や法人営業を担当するRA(リクルーティングアドバイザー)、バックオフィスといった従業員の給与であるため、一定のコストがかかります。
変動費
変動費とは、固定費とは違って一定ではないコストです。人材紹介事業の運営には、以下のような変動費が生じます。
・広告宣伝費
・Webサイトの運用費用
・求人データベースの利用料金
・スカウトサービスの利用料金
・テレアポ代行費用
上記の変動費は、いずれも求職者の集客や求人企業の新規開拓のために使われています。変動費が過剰に増えると経営状況に悪影響をもたらすため、コストの最適化が重要です。
参考:主要求人データベース8選
人材紹介事業と人材派遣事業の利益に関する違い

人材紹介と似ている事業として、「人材派遣」が挙げられます。混同されがちな事業ですが、利益に関して大きな違いがあります。「収益構造」「費用」「利益率」の3つに分けて、具体的な違いを見ていきましょう。
収益構造の違い
人材派遣事業とは、自社に登録しているスタッフをクライアント企業へ派遣するビジネスです。収益源となる売上は、クライアント企業から受け取る派遣料金です。派遣料金からスタッフへの報酬(売上原価)を差し引いた分が、粗利益となります。スタッフと雇用契約を結ぶのは人材派遣会社であり、派遣先のクライアント企業ではありません。
対する人材紹介事業は、自社に登録している人材をクライアントである求人企業へ紹介するビジネスです。紹介人材が採用された場合、雇用契約を結ぶのは求人企業であり人材紹介事業者ではありません。求人企業から支払われる紹介手数料が収益源であり、売上となります。
費用の違い
人材派遣事業の費用は、人材紹介事業にはない「売上原価」が含まれます。誤解されやすいポイントですが、派遣スタッフの給与や社会保険料は販管費における人件費ではなく売上原価に該当します。派遣スタッフの維持にかかる費用は、商品(派遣サービス)の提供に必要なコストであるためです。
一方の人材紹介事業の費用には、売上原価がありません。人材の紹介は無形サービスであるうえ、サービスを提供するための直接的なコストも生じません。そのため、人材紹介事業と比較すると人材派遣事業のほうが費用は膨らみます。
利益率の違い
人材派遣事業の利益(営業利益)は、以下の計算式で算出します。
■人材派遣事業の営業利益の計算式
売上高 - 売上原価(派遣スタッフの給与等) - 販管費(派遣スタッフ以外の人件費+広告費+その他関連費用)= 人材派遣事業の営業利益
人材紹介事業は上記の計算式に売上原価を含めないため、人材派遣事業よりも利益が大きいです。また、売上高に対する利益率も、人材紹介事業のほうが高くなります。
人材紹介事業の利益率を上げるためのポイント

人材紹介事業は利益率が高い業種ですが、事業を発展させるためにはさらに利益を追求することが大切です。利益率を上げるうえで売上の拡大と費用の削減は不可欠です。人材紹介事業の利益率の向上に必要なポイントを6つ解説します。
紹介手数料の最適化
求人企業を集客して売上を高める手法として、紹介手数料の最適化は重要です。売上単価を上げたいからといって単に紹介手数料を高く設定しても、サービスを利用したいと思う求人企業は少ないでしょう。求人企業が求める人材の経験やスキル、サポート体制の手厚さといった要素を考慮して、納得感のある料率にしましょう。最適な紹介手数料を設定することで、求人企業を開拓しやすくなります。
社内人材のスキル向上
売上を拡大するためには、成約数(求職者の採用人数)の増加が必要です。社内人材のスキルを高めれば、成約数の増加が見込めるでしょう。中でも、リクルーティングアドバイザーやキャリアアドバイザーは、求人企業や求職者と深く関わる職種です。ヒアリング力や提案力、課題解決力などのスキルが高いほど、マッチ度の高い人材紹介および成約の可能性が高まります。社内でノウハウを共有して業務の属人化を防ぐことで、会社全体でのスキル向上を実現できます。
求職者へのフォローの拡充
求職者へのフォローを充実させると、選考通過や内定率の向上につながります。結果的に採用される求職者が増えれば、成約数の増加によって売上を拡大させられます。求人企業と求める人物像のすり合わせをしたうえで、求職者へ面接対策や書類の添削といった選考の通過率を高めるためのサポートを提供しましょう。また、内定辞退の防止も大切です。転職の希望条件や保有スキルを丁寧にヒアリングして、求職者の経験や業界動向を踏まえた最適な求人企業を紹介しましょう。ミスマッチを防止して入社まで丁寧な支援を続けることで、求職者の入社意欲を高められます。
広告宣伝費の抑制
人材紹介事業の費用のうち、広告宣伝費は比較的減らしやすいコストです。広告宣伝費を抑えるためには、広告の費用対効果の改善が求められます。たとえば、もっともコンバージョン率が高い広告への予算集中が効果的です。あるいは、同じ予算でより多くの顧客にアプローチが可能なチャネルへ変更する施策も選択肢となるでしょう。具体的な改善策を立てる際は、現状の各広告の効果測定を行うことで客観的に現状を把握できます。新たに取り組むべきチャネルや予算の優先対象がわかり、広告宣伝費のコストパフォーマンス向上に役立ちます。
集客経路の増加
集客経路を増やして、より多くの利用者を獲得する方法も売上拡大に貢献します。また、広告の最適化につながり、宣伝広告費の削減も可能です。人材紹介サービスの集客経路は、Web広告やマスメディアのCMだけでなく、以下の通り多様な手段があります。
・リファラル営業
・オウンドメディア
・展示会、セミナー
・ビジネスSNS
リファラル営業とは、サービスを利用した求人企業や求職者から新たな人材を紹介してもらう手法です。オウンドメディアは自社で運営するWebサイトであり、コラムや動画などの有益なコンテンツを提供することで集客します。展示会やセミナー、ビジネスSNSを活用すれば、求人企業や求職者と直接的に知り合うことが可能です。
ツール導入や業務フロー見直しによる効率化
業務の効率化を実現すると、残業代の削減や生産性の向上によって利益率を上げられます。たとえば、MA(マーケティングオートメーション)やCRM(顧客関係管理)などのツールを導入すると、スムーズに業務効率化を実現できます。加えて、現在の業務フローも見直しましょう。無駄な作業やボトルネックを解消することで、生産性の向上へつながります。そのほか、適切なKPI管理も大切です。求職者向けと求人企業向けの業務にそれぞれKPIを設定すれば、作業の優先度や進捗を可視化できます。できる限り業務を効率的に回すことにより、利益率を向上できるでしょう。
人材紹介の運営にかかる費用は少なく利益率が高い
人材紹介事業の売上は、紹介した人材を採用した企業から支払われる紹介手数料が中心です。採用決定者の理論年収×30〜35%が目安であり、高単価なビジネスと言えます。さらに、人材紹介事業は売上原価が発生しません。事業運営にかかる費用が少ないため、利益率20%の高い収益性を実現しています。
この記事の監修者
長沢 ひなた
外資系アパレルで販売・チーム運営を経験後、美容クリニックのカウンセラーに転身。60名中3名のみのトップカウンセラーとして表彰され、マネージャーとして大規模なチームマネジメントも経験する。
「人生単位での変化」を支援したいとの想いからキャリアアドバイザー職へ転身し、入社半年での異例の昇格、1年でリーダーに就任。現在は、キャリアアドバイザー職への転職を専門に、業界構造を熟知した的確な支援を行っている。(▶︎詳しく見る)
基礎知識のおすすめ記事
-
2024/11/20
キャリアアドバイザー(人材紹介営業)で成果を出すコツとは?売上を伸ばす方法を8つのステップで徹底解説
-
2026/01/23
人材業界に向いている人の特徴とは? 仕事内容やスキルを鍛える方法を解説
-

2024/10/16
キャリアアドバイザー(人材紹介営業)職でホワイト企業に転職する方法
-

2024/10/16
キャリアアドバイザー(人材紹介)は未経験からでも転職できる?営業未経験でも応募可能な求人例あり