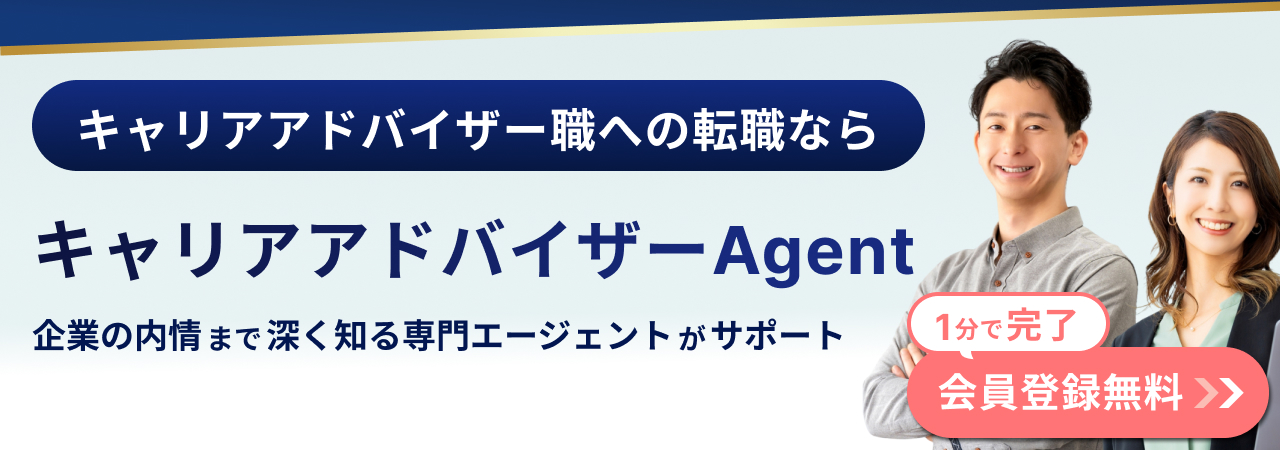2025年4月19日公開
最終更新日:2025年12月9日
人材紹介の手数料は誰が払う? 仕組みや相場、算出方法、早期退職による手数料の返還とは
人材紹介とは、人材を求める採用企業と仕事を探す求職者をマッチングさせるサービスです。マッチ度の高い人材や企業を効率的に探せるため、多くのユーザーが利用しています。人材紹介サービスの利用時は手数料が発生しますが、誰が払うのでしょうか。
この記事では、人材紹介における手数料の仕組みや相場について詳しく解説します。また、紹介手数料の具体的な算出方法や返還についても説明しますので、ぜひご一読ください。
【関連記事】当社が運営する「キャリアアドバイザーAgent求人ナビの転職支援サービス」の特徴や登録のメリットについてご紹介。
【結論】人材紹介の手数料を支払うのは採用企業
結論から言うと、人材紹介の手数料を支払うのは求職者を採用する企業です。多くの場合、人材紹介サービスへの求人情報の提供や、求職者とのマッチングなどの段階では手数料が発生しません。求職者の採用決定後にはじめて紹介手数料が生じる形式が主流です。紹介した求職者が採用されなかった場合、紹介手数料は発生しません。人材紹介会社は採用企業から手数料を受け取るビジネスモデルであるため、求職者は無料でサービスを登録・利用できます。
手数料が発生するタイミング
ほとんどの人材紹介サービスでは、採用決定者(求職者)の入社日に手数料が発生します。入社日を請求日として、採用決定者が出社しているかを確認してから採用企業へ紹介手数料を請求する流れが一般的です。詳しくは次章で述べますが、「着手金(リテーナーフィー)」を採用している人材紹介サービスも存在します。採用企業に着手金を請求するタイミングは、人材紹介サービスが当該企業にマッチする候補者をリサーチする段階です。
求職者への手数料は職業安定法で規制されている
人材紹介サービスの法律上の正式名称は、「有料職業紹介事業者」と言います。有料職業紹介事業者は、職業安定法第32条3項にて原則として求職者から手数料を徴収できないように定められています(※1)。ただし、芸能家や調理師、家政婦(夫)といった伝統的な職業のみ、求職者へ1件710円までの「求職受付手数料」を請求できます。詳しくは次章の「受付手数料」の項目をご覧ください。
※1 参照:e-Gov 法令検索「職業安定法 第三十二条の三」
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141#Mp-Ch_3-Se_1-At_32_2
人材紹介手数料の仕組み

人材紹介の手数料は、以下4つの種類ごとに仕組みが異なります。
・届出制手数料
・上限制手数料
・受付手数料
・着手金(リテーナーフィー)
それぞれの仕組みを説明します。
届出制手数料
届出制手数料とは、あらかじめ厚生労働大臣へ届け出た料率の範囲内で手数料を決める仕組みです。求職者の採用決定時に手数料が発生する「成功報酬型」の一種であり、採用されなかった場合は発生しません。採用決定者の理論年収に料率を掛けて、紹介手数料を算出します。法律上は事業者が任意の料率を設定できますが、実務上では50%を超える料率の届出は基本的に受理されません。そのため、届出制手数料の料率は、30〜35%が一般的です。とはいえ、50%以下であれば柔軟に料率を決められることから、多くの人材紹介サービスが届出制手数料を採用しています。届出制手数料を適用するためには、紹介手数料の具体的な料率を記載した「届出制手数料届出書」を管轄の労働局に提出して、厚生労働大臣へ届け出る必要があります。
上限制手数料
上限制手数料とは、採用決定者が6ヶ月を超えて雇用された場合、6ヶ月分の賃金の11%を紹介手数料の上限とする仕組みです。免税事業者は10.3%が上限です。届出制手数料と同じく、成功報酬型の料金体系に該当します。理論年収の50%まで報酬を得られる届出制手数料と異なり、上限制手数料の報酬は最大でも6ヶ月分の賃金の11%に留まります。例として、理論年収500万円の紹介手数料は以下のように大きな差があります。
■理論年収500万円の紹介手数料の最大値
・届出制手数料:最大250万円
・上限制手数料:最大27万5000円(※6ヶ月分の賃金を250万円と仮定)
このように紹介手数料の最大値が大きく異なり、上限制手数料は人材紹介サービスにとってメリットが薄い制度と言えます。そのため、制度上は存在するものの現在ではほとんど使われていません。なお、上限制手数料を利用する場合のみ、次の受付手数料も請求できます。
受付手数料
受付手数料とは、人材紹介サービスが利用者の求人・求職の依頼を受け付けた時点で請求できる手数料です。上限制手数料を採用した場合のみ設定できるため、届出制手数料を用いる場合は受付手数料を徴収できません。さらに、受付手数料は人材を求める求人企業から得る「求人受付手数料」と、就職先を探す求職者から得る「求職受付手数料」の2種類があります。どちらも1件あたり710円(免税事業者は660円)を請求できますが、求職受付手数料を設定できる職種は以下の6つに限定されます。
・芸能家
・モデル
・調理師
・配膳人
・家政婦(夫)
・マネキン(※店頭や展示会で販促活動を行う職業)
上記の6つの職種のみ、求職受付手数料の請求が可能です。同じ求職者に対しては、ひと月につき3件まで求職受付手数料を請求できます。
着手金(リテーナーフィー)
人材紹介の手数料として、成功報酬型の仕組みではなく着手金(リテーナーフィー)を用いるケースもあります。企業が人材紹介サービスへ依頼した際に、紹介手数料の一部を着手金として支払う仕組みです。求職者の採用決定後、紹介手数料の残りを成功報酬として支払います。求職者の採用可否にかかわらず、支払った着手金は返金されません。人材紹介サービスのうち、ヘッドハンティングによって人材を確保・紹介する「サーチ型」の会社は着手金を設定しているケースが多いです。人材紹介サービス側が能動的に優れた求職者を探す必要があり、運営コストが高くなることから着手金を求められます。
人材紹介手数料の算出方法
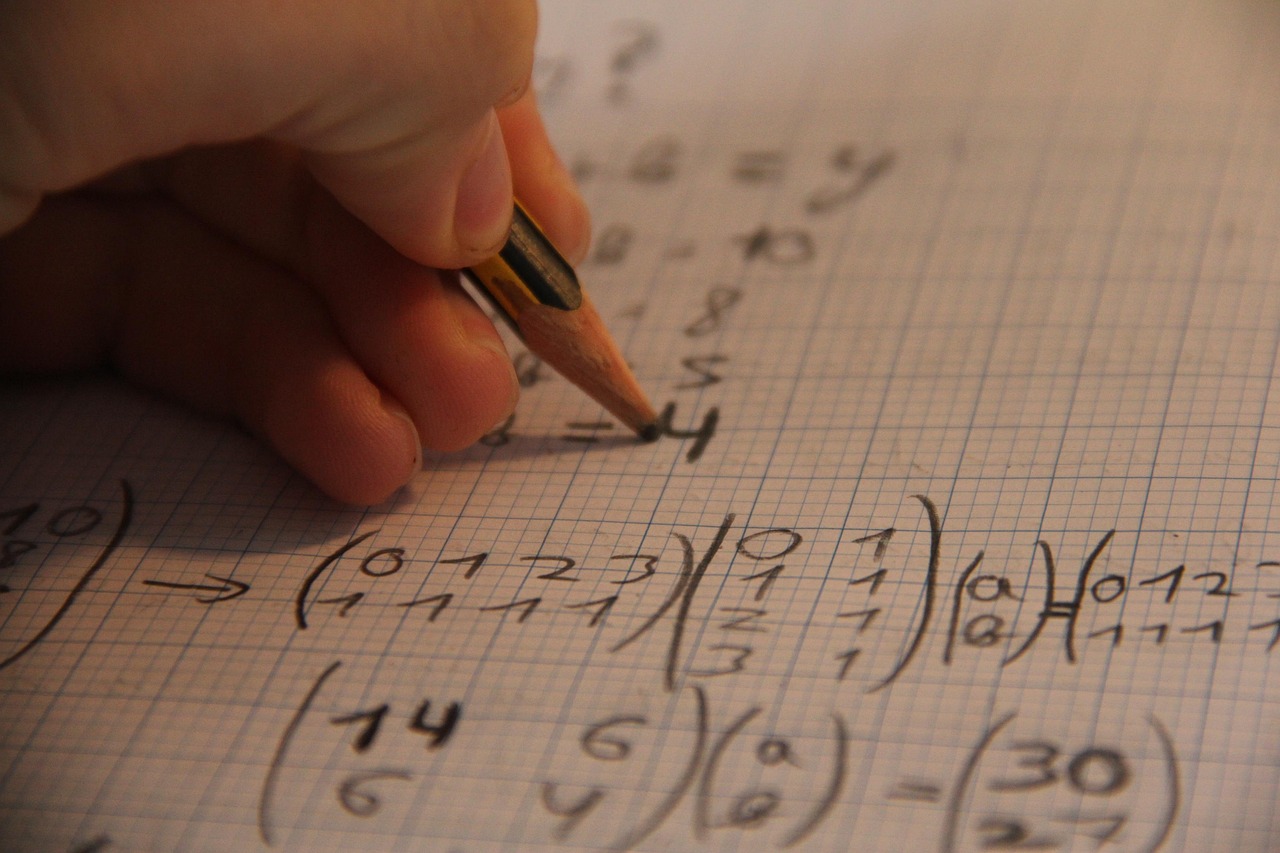
人材紹介サービスの手数料は、基本的に理論年収をもとに算出しています。ここでは、人材紹介手数料や理論年収の具体的な計算方法や、理論年収と手取りの違いを解説します。
人材紹介手数料の計算式
現在、ほとんどの人材紹介サービスは、最大料率50%の届出制手数料によって企業へ請求する報酬を決定しています。届出制手数料による計算式は、次の通りです。
■人材紹介手数料(届出制手数料)の計算式
理論年収(円)× 届出制手数料率(%)= 人材紹介手数料(円)
例として、理論年収600万円、届出制手数料30%の場合、人材紹介手数料は180万円となります。同条件で35%の場合、人材紹介手数料は210万円です。同じ理論年収でも、採用企業が支払う料金は料率によって大きく異なります。
■理論年収600万円、届出制手数料30%の計算式
理論年収600万円 × 届出制手数料30% = 人材紹介手数料180万円
■理論年収600万円、届出制手数料35%の計算式
理論年収600万円 × 届出制手数料35% = 人材紹介手数料210万円
理論年収の計算式
届出制手数料を算出する際は、理論年収を計算式に当てはめます。理論年収とは、採用決定者が1年間働いた場合に支給される年収の推定額です。以下の計算式で理論年収を求めます。
■理論年収の計算式
(採用決定者の基本給 + 諸手当)× 12ヶ月分 + 賞与 = 理論年収
理論年収に含まれる諸手当には、次のように入社前にある程度算出できる手当等が該当します。
・固定残業代
・資格手当
・扶養手当
・住宅手当
・深夜勤務手当
・役職手当
・その他、企業独自の手当等
通勤手当は従業員の所得とならないことから、理論年収に含まれません。加えて、通常の残業代は従業員や月によって変動するため、理論年収から除外して計算します。
■理論年収の計算例
基本給30万円、住宅手当2万円、資格手当2万円、賞与60万円
(30万円 + 2万円 + 2万円)× 12ヶ月 + 60万円 = 理論年収468万円
理論年収と手取りの違い
理論年収はあくまで推定の金額に過ぎず、採用者が実際にもらえる手取りとは異なる点に注意しましょう。一般的に、理論年収×0.8で手取りに近い現実的な数値がわかると言われています。賞与は個人差があるうえ、業績の影響も受けるものです。また、「年2回」と賞与の支給タイミングが分かれている場合、満額を受け取れるのは入社2年目以降です。さらに、社会保険料や住民税が支給額から差し引かれます。こうした実情を踏まえて理論年収に0.8を掛けることで、手取りに近い数値を算出できます。
人材紹介手数料の相場
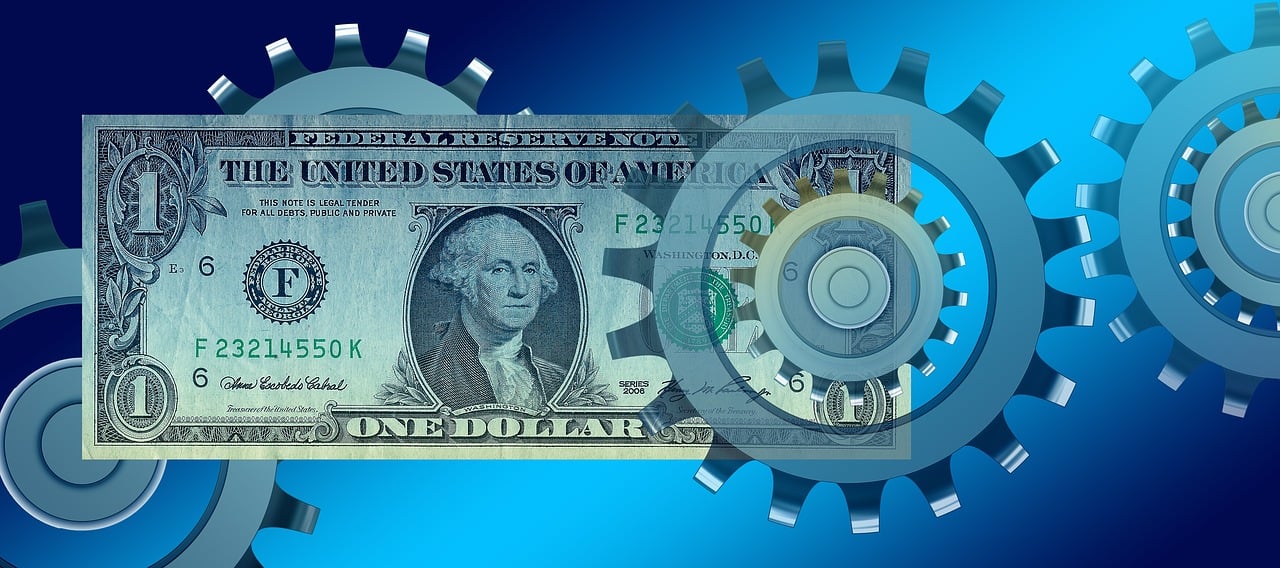
人材紹介手数料の相場は、「届出制手数料」と「上限制手数料」によって変動します。それぞれの相場について見ていきましょう。
届出制手数料の相場
届出制手数料の相場は、理論値×30〜35%が目安になります。たとえば、理論年収500万円であれば、紹介手数料の相場は150万〜175万円です。専門職や経営層などの採用難易度が高い求人であれば、35%よりも高く設定する場合があります。ただし、厚生労働大臣への届出が受理される手数料は50%以下であるため、届出制手数料が50%よりも高くなる可能性はありません。
上限制手数料の相場
上限制手数料は、手数料を計算する際の料率が11%に固定されています。さらに、6ヶ月を超えて雇用される場合、6ヶ月間に支払われた賃金×11.0%が上限かつ相場となります。例として6ヶ月間の賃金が180万円であれば、上限手数料は19万8000円です。前述の通り、ほとんどの人材紹介サービスは、より多くの報酬を受け取れる届出制手数料を採用しています。したがって、上限制手数料で紹介手数料が算出されるケースはごく稀です。
紹介手数料の相場一覧表
理論年収ごとの紹介手数料の相場を一覧表にまとめます。届出制手数料30%と35%におけるそれぞれの紹介手数料は、以下の通りです。
人材紹介の早期退職による保証

紹介手数料は成功型報酬であり、採用決定者の入社日に請求されます。しかし、採用決定者の中には、入社後すぐに辞めてしまう人もいるでしょう。こうした早期退職への備えとして、ほとんどの人材紹介サービスは採用企業への保証を契約書に明記しています。具体的には、「手数料の返還」や「フリーリプレイスメント」によって保証します。
手数料の返還
人材紹介によって入社した採用者が早期退職した場合、人材紹介サービスは採用企業に対して手数料を返還します。採用企業が支払う紹介手数料は理論年収の30〜35%になるため、安価とは言えません。たとえば、理論年収600万円の求職者を採用した場合、180万〜210万円もの紹介手数料の支払いが必要です。採用企業にとって、採用決定者の早期退職は人材を獲得できないばかりか、多大なコストを無駄に失ってしまうわけです。そこで、手数料を返還することで、採用企業のダメージを最低限に抑えられます。
なお、2018年1月に施行された職業安定法改正により、人材紹介サービスには「返戻金制度」の情報提供が義務づけられました。返戻金制度の有無や具体的な保証内容に関して、利用者へわかりやすく明示する必要があります。返戻金制度の設定自体は「望ましい」とされているものの、義務ではありません。とはいえ、これまでの商習慣により、返戻金制度を設けている人材紹介サービスが多いです。注意点として、医療・介護・保育の人材紹介に関しては、入社後6ヶ月以内の退職に対する返戻金制度の設定が義務化されています。
手数料返還の保証期間と金額
手数料返還の保証期間は、90日間(3ヶ月間)と定めている人材紹介サービスが一般的です。また、手数料の返還率は、採用決定者が退職したタイミングによって異なります。よくある返還率は以下の通りです。
・入社1ヶ月未満の退職:手数料の80%を返還
・入社1ヶ月以上3ヶ月未満の退職:手数料の50%を返還
人材紹介サービスによっては、保証期間を180日間(6ヶ月間)としている会社や入社後1ヶ月ごとに返還率を設定している会社もあります。手数料の返還率も会社によって違いがありますが、採用決定者の在籍期間が長いほど返還率は低くなります。
フリーリプレイスメント
フリーリプレイスメントとは、早期退職した採用決定者の代わりに新たな求職者を無償で紹介するシステムです。採用企業は再び紹介手数料を支払らわずに人材を確保できます。また、人材紹介サービスも手数料を返還する必要がないため、返還金の損害や手続きが生じません。フリーリプレイスメントは、手数料の返還の代わりに行われます。したがって、フリーリプレイスメントを保証とする場合、早期退職があっても手数料は返還されません。
人材紹介手数料の決まり方

人材紹介サービスの手数料は、届出制手数料であれば最大50%までの範囲であれば自由に設定可能です。相場は30〜35%であるものの、細かな料率は人材紹介サービスによって違います。人材紹介サービスの手数料は、どのような基準によって決められているのでしょうか。主な5つの基準について、くわしく説明します。
求める人材のスキルや経験
採用企業が求める人材のスキルや経験によって、人材紹介の手数料は変動します。未経験者が応募可能な求人であれば、人材獲得の難易度が下がることから手数料は低くなります。さらに、経験者と比べて未経験者の教育コストは高くなるものです。採用企業は総合的なコストを考慮するため、未経験者可の求人は手数料の安さが重視される傾向があります。一方、高度な専門知識や経験を持つハイクラス人材の場合、人材獲得の難易度が高いために手数料も高くなりやすいです。
業種・職種の採用難易度
採用企業が属する業界の採用難易度が高いほど、紹介手数料も高くなります。具体的には、医療従事者や研究職、ITエンジニアなど、慢性的に人手不足な業種および職種が当てはまります。こうした売り手市場が続いている業種・職種を求める採用企業は、自社のみで効率的に人材を確保することが困難です。人材紹介サービスを活用することで優秀かつマッチ度の高い人材を獲得できるため、高価格帯の手数料でも広く利用されています。
返還規定の厳格さ
人材のスキルや採用難易度だけでなく、返還規定の厳格さも手数料に影響します。人材紹介サービスの中には、早期退職による返還規定が他社より厳しくなる代わりに手数料を安くしている会社が存在します。早期退職の保証期間が短くなったり、手数料の返還率が低くなったりする厳しい条件が発生しますが、採用決定時の手数料を安く抑えられます。反対に、早期退職へのサポートが手厚い人材紹介サービスであれば、手数料は高くなるでしょう。保証期間が長く手数料の返還率も高いため、早期退職によるリスクを低減できます。
ヘッドハンティングの有無
ヘッドハンティングにより個別に人材を探す人材紹介サービスであれば、相場よりも手数料が高くなりやすいです。ヘッドハンティングを行う場合、経営幹部などのエグゼクティブ人材や、管理職や専門職などのハイクラス人材へ積極的にアプローチする傾向があります。優れた人材が多い点も、手数料の高さに影響しているでしょう。また、ヘッドハンティングによりスカウトした人材の紹介先が一社のみの場合、手数料はさらに高くなります。加えて、ヘッドハンティング型のサービスは着手金が必要になるケースが多く、求職者の採用決定前から費用が発生する点も特徴的です。
人材紹介会社の規模
人材紹介会社の規模によって、手数料が変動するパターンもあります。シェアオフィスを使用する会社や少数精鋭の会社の場合、人件費などの固定費が低いです。トータルで運営コストを抑えられるため、手数料を安く設定できます。さらに、「ビジネスSNSによって求職者を直接スカウトする」「求職者データベースを使用しない」などの戦略により、広告宣伝費を抑えている人材紹介会社も安価な手数料を実現しています。対する大手の人材紹介会社はオフィスや従業員、広告宣伝の費用が高いため、小規模な会社と比べると手数料が高い傾向があります。
人材紹介手数料の返還によるトラブルを防ぐ方法

多くの人材紹介サービスは、早期退職の保証として手数料の返還を規定しています。一般的な保証期間は90日間であり、手数料の50〜80%を返還しなくてはいけません。手数料の返還にはトラブルが起きる可能性があるため、事前に対策を講じておく必要があります。人材紹介手数料の返還によるトラブルを防ぐためには、次の6つの方法を参考にしてみてください。
返還規定を明示する
2018年1月の職業安定法改正にて定められた通り、人材紹介サービスは利用者が返還規定を確認できるように明示する義務があります。手数料返還の規定の有無、保証期間、退職日による返還率の違い、返還の条件など、人材紹介サービスのWebサイトや契約書に記載しましょう。手数料の返還を巡る訴訟が起きた事例もあるため、「どのような条件であれば手数料を返還するのか」をわかりやすく示すことが重要です。なお、早期退職の保証として手数料を返還せずフリーリプレイスメントを行う場合でも、手数料を返還しない点についての明示が必要です。
返還規定や労働条件を最新状態に保つ
手数料の返還規定を変更した際は、Webサイトなどの情報をすばやく更新しましょう。いつまでも古い情報が残っていると、手数料の返還について採用企業の誤解を招き、トラブルに発展するかもしれません。同じく、採用企業の労働条件に変更があった場合も、すみやかに求人情報へ反映しましょう。求人情報と契約書面の労働条件に差異があると、求職者の早期退職の要因になります。給与や福利厚生、業務内容を常に最新状態に保つことで、早期退職を防ぎやすくなります。
手数料の返還フローを決める
早期退職による手数料の返還フローは、あらかじめ決めておきましょう。明確な返還フローがない場合、採用企業から手数料の返還を求められた際に作業が混乱して、ミスが起きてしまうおそれがあります。返還金を請求された時点から支払いが完了するまでの一連の流れを洗い出して、やるべき作業と担当者や決裁者を定めましょう。明確な返還フローがあれば、実際に採用企業から手数料の返還を求められても、スムーズに作業を進められます。
採用企業との連携を高める
手数料の返還トラブルの防止には、そもそも早期退職を防ぐことも大切です。採用決定者が早期退職する要因として、「仕事内容が想定と違う」「求人情報の労働条件と違う」「想定していた年収より低い」といったミスマッチが挙げられます。こうしたミスマッチを防ぐためには、採用企業が求める人物像やスキルなどの具体的な人材要件のヒアリングが重要です。また、実際の労働条件と求人情報の内容が合っているかの確認も欠かせません。採用企業の人事担当者や管理職と密接に連携することで、求職者にとっても最適な求人情報の提供が可能になります。
フリーリプレイスメントを設定する
手数料の返還ではなく、フリーリプレイスメントを早期退職の保証とする方法もトラブルの予防に効果的です。フリーリプレイスメントであれば手数料の返還によるトラブルが起こらないうえ、採用企業は追加のコストをかけずに新たな人材を確保できます。また、新たな人材紹介サービスを探したり依頼したりする手間もかからないため、一から採用活動をやり直す必要がない点もメリットです。人材紹介サービスも単に手数料の返還が不要になるだけでなく、クライアントである採用企業と長期的な関係を築けるといった恩恵も受けられます。フリーリプレイスメントは、人材紹介サービスと採用企業の双方にとってメリットの大きい保証方法と言えます。
厚生労働省の案内を確認する
厚生労働省は、「人材紹介を取り扱う事業者に向けたトラブル事例・解決パンフレット」を配布しています。同資料は、人材紹介サービスに向けてトラブルの事例と解決策を示したパンフレットです。手数料の返還に加えて、以下のようなトラブルの対応ポイントを示しています(※2)。
・依頼された候補者を紹介できない
・面接時に求職者と求人者が相互に理解できていない
・募集時の労働条件と違うという苦情を受けた
・求職者の期待と求人者の期待が乖離していた
・求職者のスキル不足
・求職者への教育訓練の不足
・手数料や返戻金をめぐるトラブル
(※2より引用)
上記のトラブル例ごとに細かい対応方法が示されています。人材紹介サービスの運営で起きがちなトラブルが網羅されているので、ぜひ一度確認してみてください。
※2 引用:厚生労働省「人材紹介を取り扱う事業者に向けたトラブル事例・解決パンフレット」
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/001101552.pdf
人材紹介サービスの手数料は理論年収の30〜35%を採用企業が支払う
人材紹介サービスは、新たな人材を確保したい採用企業からの紹介手数料によって収益を得ています。したがって、就職先・転職先を探す求職者は、手数料0円で人材紹介サービスを利用できます。採用企業が支払う紹介手数料は、採用決定者の理論年収の30〜35%が目安です。紹介手数料は決して安くないため、採用決定者の早期退職時は「手数料の返還」や「フリーリプレイスメント」といった保証があります。
この記事の監修者
長沢 ひなた
外資系アパレルで販売・チーム運営を経験後、美容クリニックのカウンセラーに転身。60名中3名のみのトップカウンセラーとして表彰され、マネージャーとして大規模なチームマネジメントも経験する。
「人生単位での変化」を支援したいとの想いからキャリアアドバイザー職へ転身し、入社半年での異例の昇格、1年でリーダーに就任。現在は、キャリアアドバイザー職への転職を専門に、業界構造を熟知した的確な支援を行っている。(▶︎詳しく見る)
基礎知識のおすすめ記事
-
2024/11/20
キャリアアドバイザー(人材紹介営業)で成果を出すコツとは?売上を伸ばす方法を8つのステップで徹底解説
-
2026/01/23
人材業界に向いている人の特徴とは? 仕事内容やスキルを鍛える方法を解説
-

2024/10/16
キャリアアドバイザー(人材紹介営業)職でホワイト企業に転職する方法
-

2024/10/16
キャリアアドバイザー(人材紹介)は未経験からでも転職できる?営業未経験でも応募可能な求人例あり